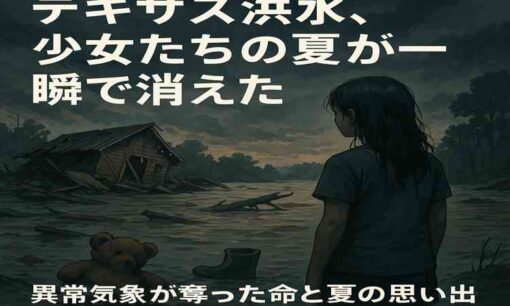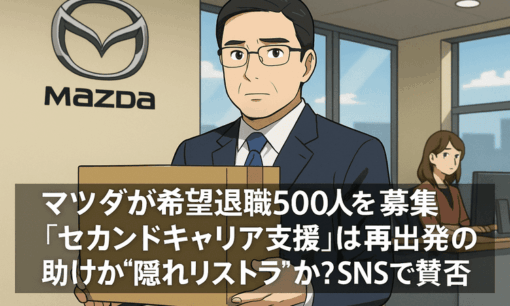三井住友銀行が、日本企業に根付く育児休業の課題に対し、先駆的な制度で新たな道を切り拓いた。男性行員の育休を原則1カ月間の取得必須とするとともに、育休取得者本人だけでなく、業務を支える同僚にも報奨金を支給するという試みだ。
新たな育休制度の全容:報奨金が示す「チーム育児」の視点
2025年10月、国内最大手金融機関の一つである三井住友銀行(以下、同行)が、働き方改革における新たな一歩を踏み出す。男性行員を対象とした育児休業(以下、育休)の取得を、これまでの「推奨」から「原則必須」へと変更するのだ。この大胆な方針転換の背景には、育休取得率こそ2023年度に100%に達したものの、平均取得日数が社内目標の30日に対し、わずか12日に留まっていたという課題があった。育児への関与を促すため、量だけでなく質の向上を目指す同行の強い意志が窺える。
この制度変更の最大の特色は、育休取得を社員個人の問題として捉えるのではなく、組織全体の課題として解決しようとする姿勢にある。同行は、1カ月以上の育休を取得する行員本人に対し、報奨金として5万円を支給する。これだけでも育休取得へのインセンティブとしては十分に機能するが、今回の制度が画期的なのは、育休期間中に業務を代行する部署の同僚にも、同様に1人当たり5万円の報奨金が支給される点にある。
報奨金の支給対象は、約2万4千人の全行員に及び、男性行員だけでなく、女性行員の育休取得時にも適用される。ただし、6カ月を超える長期の育休の場合、代替人員が配置されることを考慮し、この報奨金の対象外としている。育休という名目で個人が休むことで、同僚に業務負担が集中するという、これまでの企業文化にありがちだった負の側面を、報奨金という形で正面から解消しようとする試みは、3メガバンクとしては初の取り組みであり、日本企業の働き方改革に一石を投じるものとして注目される。
「100%取得、でも平均12日」が示す日本の育休の現実
同行が今回の制度改革に踏み切った背景には、日本の企業における男性育休の現状が色濃く反映されている。2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、企業には男性育休の取得促進が義務付けられた。しかし、法整備が進む一方で、育休取得は「短期間で済ます」という風潮が根強く残っている。厚生労働省のデータによると、2022年度の男性の育休取得率は17.13%にまで上昇したが、取得日数の内訳を見ると、「5日未満」が全体の25.0%、「5日以上2週間未満」が30.2%を占めており、合計で半数以上が2週間以内の短期取得となっている。
三井住友銀行のケースもこの傾向と一致する。2023年度の取得率100%は素晴らしい実績であるが、平均取得日数が社内目標の半分にも満たなかったことは、育休を取得した行員が「職場に迷惑をかけたくない」という心理的負担を感じ、業務の引き継ぎや円滑な職場復帰を優先した結果であると推測される。また、育休取得を推奨する声が高まる一方で、同僚の「本音」とのギャップも無視できない課題であった。誰かの育休は、別の誰かの残業や業務量増加に直結する。この見えない負担感が、育休取得を躊躇させる要因の一つになっていたのだ。
今回の制度は、この「心理的負担」と「同僚への負担」という二つの側面を同時に解決しようとする点で、極めて戦略的である。報奨金を支給することで、育休取得者本人の「申し訳なさ」を和らげるとともに、業務をカバーする同僚には、その貢献に対する正当な対価を支払う。これにより、「育休はチームで乗り越えるイベント」というポジティブな文化を醸成し、互いに協力し合う土壌を築くことを目指している。
チームインセンティブの可能性
これまでの育休制度は、あくまでも個人が権利として取得するという側面が強かった。しかし、今回の報奨金制度は、育休取得を部署やチームの功績として捉える初めての試みだ。報奨金は直接的な経済的メリットだけでなく、職場の仲間から育休取得への協力に対する感謝を伝えるツールとなる可能性がある。これにより、社員のエンゲージメント向上や、離職率の低下に繋がる可能性も秘めている。
育児の社会化が叫ばれる中、企業がその一翼を担う具体的な行動として、この制度は大きな意味を持つ。特に、日本の企業文化では「皆で同じように働く」ことが美徳とされる傾向が強かったが、この制度は多様な働き方をチーム全体で支え、評価する新たなモデルを提示している。これにより、女性だけでなく、男性も主体的に育児に関わることを促し、性別役割分業意識の解消にも繋がるだろう。
制度導入後の展望と波及効果
三井住友銀行の今回の取り組みは、男性育休取得の促進を通じて、多様な働き方を許容する企業文化を根付かせ、優秀な人材の獲得競争における大きな武器となることを目指している。特に、Z世代と呼ばれる若手層は、給与や役職だけでなく、ワークライフバランスや企業の社会貢献度を重視する傾向が強い。育児への理解が深く、柔軟な働き方を認める企業は、彼らにとって魅力的な選択肢となるはずだ。
また、3メガバンクという影響力の大きな企業が先陣を切ったことで、今後は他の金融機関や大手企業にも同様の制度が波及する可能性も考えられる。育休取得に伴う同僚の負担をどう解消するかは、多くの企業が直面している共通の課題だからだ。
育休取得が特別なことではなく、当たり前の選択肢となり、それがチーム全体の成果として評価される社会の実現に向け、この小さな一歩が大きな一歩となることが期待される。