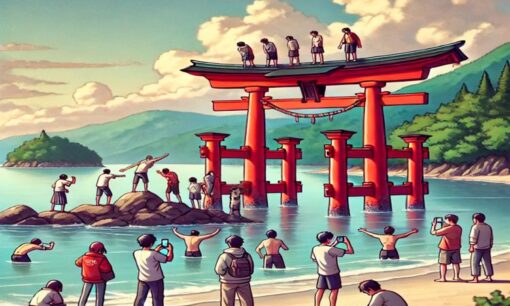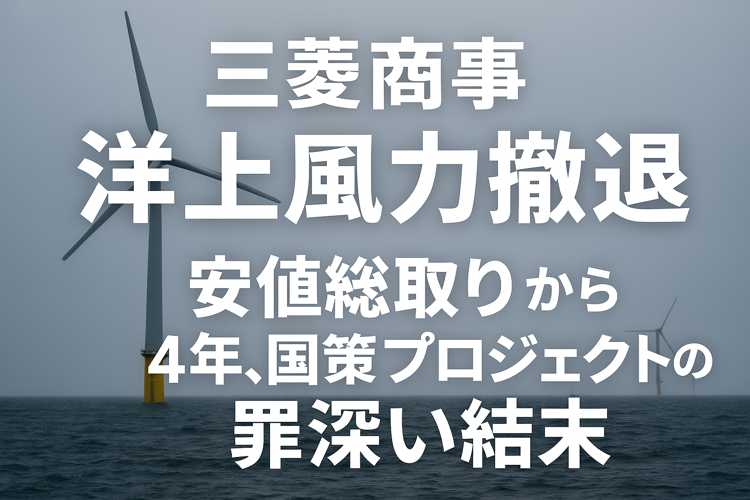
秋田県・千葉県沖の大規模洋上風力発電計画について、三菱商事が撤退の方向で最終調整していると日本経済新聞の報道を基にNHKや日経新聞が伝えた。
対象は2021年の第1回国家入札で三菱商事主導の連合が権利を得た3区域で、総出力は約1.7GWに達する。事業環境の悪化と採算性の崩れが主因とされ、同社は「計画を見直し中」との立場だが、国策の象徴案件の頓挫は避けがたい様相だ。
「やれるのか」と当初から問われていた前提
第1回入札では、三菱商事連合が秋田・能代三種男鹿(478.8MW、13.26円/kWh)、秋田・由利本荘(819MW、11.99円/kWh)、千葉・銚子(390.6MW、16.49円/kWh)を“総取り”した。価格は当時の上限29円/kWhを大きく下回り、最低は11.99円/kWh。業界では「価格破壊」と映る一方、「果たして実行できるのか」という疑義が根強かった。のちに政府系・業界資料も、落札価格の低さと制度設計の課題を併せて指摘している。
実務の裏付けも揺らいだ。三菱商事は25年2月、国内洋上風力に関し522億円の減損を計上し、同月に「マクロ環境の大変動を受け事業計画を再評価する」と公表した。コスト上振れの要因に、資材インフレ、円安、金利上昇などを列挙している。
日本の海が突きつける現実 深海・浮体式・系統
日本は沿岸の水深が深く、欧州の主流である着床式よりもコスト高の浮体式の出番が相対的に増えやすい。第7次エネルギー基本計画も30年10GW、40年30~45GW(浮体式を含む)を掲げるが、海象・地盤・港湾・作業船・系統接続という“日本特有の壁”が連なる。
制度側も入札の運営期間延長や船舶規制の明確化など改善案を検討してきたが、需要家価格との綱引きに耐えるコスト低減の道筋はなお険しい。
「数字」の冷たさ LCOEと落札価格のねじれ
政府ワーキングのモデル試算では、2020年時点の洋上風力の発電コストは30.3円/kWh(政策経費込み)。2030年にかけて低減を見込むものの、燃料火力や太陽光と比べれば依然高止まりする。第1回入札の落札価格が1桁台に迫る欧州の事例を意識していたとしても、日本の施工・系統・保守の制約を勘案すれば「価格だけで勝ち切る」戦略はきわめて脆い。
このねじれが、実行段階での資金調達・EPC・サプライチェーンの歪みとなって噴き出した格好だ。
サプライチェーンの座礁 機器・設計・保守の連鎖
第1回入札はGE Vernovaの大型機(Haliade-X 系)を前提に計画が描かれたが、世界的には24年以降、オフショア風力でコスト高・設計変更・部材不具合などの逆風が相次ぎ、金融条件の悪化も重なった。
また、計画では風力発電機の中核部品であるナセルの国内製造拠点整備も検討された。ナセルとは、風車の最上部に設置される“エンジン部分”にあたる箱型の構造物で、発電機や増速機、制御機器などを収める心臓部を指す。ブレード(羽根)で受けた風の力を電気に変える役割を担っており、この製造拠点整備は国内サプライチェーン形成の象徴とされていた。
日本市場でもナセル製造のローカル化計画は進んだ一方、実機供給・据付・運転開始までの一気通貫の“詰め”が難しくなった。結果として、設計や許認可、送変電ルート確保など前工程の費用が先行して膨らみ、事業性はさらに痩せた。
「罪深さ」の正体 安値総取りと国益・地域の機会損失
今回の撤退観測が強い反発を招くのは、単なる一民間プロジェクトの頓挫にとどまらないからだ。第1回入札は、他陣営が日本のコスト構造に合わせた現実的な見積もりで臨むなか、三菱商事連合が異例の低価格で3区域を押さえた。その後の外部環境の激変は事実としても、象徴案件での“総取り→白紙化”は、国の政策目標・価格シグナル・産業育成の順番を狂わせ、秋田・千葉の地元雇用や波及効果にまで空白を生む。
ちなみに三菱商事連合には、国内で発電事業を手掛ける同社子会社の三菱商事エナジーソリューションズと中部電力グループのシーテック、風力発電事業者のウェンティ・ジャパンが入っていると言われていた。
制度設計の甘さ(価格偏重)と、事業者の過度なリスク引受けの双方に「罪深さ」がある。政府が次ラウンド以降、「値段の安さ」だけで勝敗を決めないための評価項目(地元企業や地域とどれだけ協力するか、雇用をどのくらい生み出せるか、環境にどれだけ配慮しているかなど)の非価格要素の重み付けを強め、事業期間や施工条件を柔軟化しようとしてきた背景にも、この反省があるのではないか。
政策の岐路 「切り札」をどう立て直すか
政府は洋上風力を「再エネ主力化の切り札」と位置づけ、EEZへの展開や浮体式の本格化で量を確保する方針だが、今回の一件は“量より質”への転換を迫る。安値競争を避ける入札設計、長期のリスクを織り込める契約形態、送電・港湾の先行整備、施工船規制の明確化、系統費用の配賦設計、いずれも待ったなしだ。名門商社の撤退が事実なら、国内風力関連の投資心理は冷えかねない。
逆に言えば、ここで制度と案件の作り方を現実的なものに改めれば、日本の洋上風力は“持続可能な成長軌道”に戻りうる。