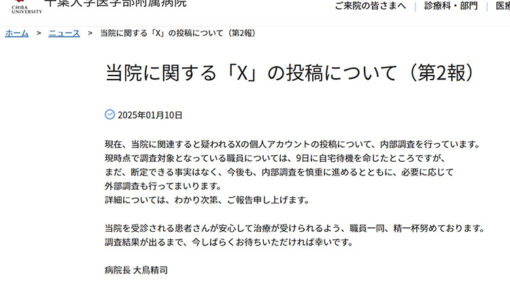4月28日、環境省は「日本企業による環境デュー・ディリジェンス対応促進に向けた懇談会 議論のまとめ」を公表した。3回にわたる有識者会合の成果を凝縮した本報告書は、サプライチェーン全体に潜む環境リスクを洗い出し、取締役会主導で対処する道筋を描く。
背景にはEUが域外企業も巻き込んで進める企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)の存在がある。
国際潮流が迫る理由
環境DDの原点は2011年に採択された国連「ビジネスと人権に関する指導原則」だ。企業は自らの活動が及ぼす負の影響を特定し、防止・軽減する責任を負う――この考え方が欧州で次々と法制化され、今夏にはCSDDDと企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が並走する予定だった。
しかし欧州委員会は2025年2月、企業負担を軽減する「オムニバス法案」を提示し、CSRDの第2・第3ウェーブを最大2年、CSDDDの初期適用を1年先送りする案を示した。欧州議会とEU理事会も3月以降「ストップ・ザ・クロック」措置を支持し、正式な延期が確定した。
延期は骨抜きか、それとも好機か
「猶予ができた」と安堵する声が日本企業から聞こえる一方で、報告書を丹念に読むと楽観は禁物だ。適用時期は28年頃に後ろ倒しされても、域外企業への拘束力や民事責任条項は維持される見通しで、供給網の管理という本質は変わらない。欧州委員会は対象企業を従業員1000人以上に絞る案を示したものの、直接取引先や子会社への管理義務は残り、対応済み企業と未対応企業の差が広がる可能性が高い。
報告書は「移行期間が延びた今こそ、リスク棚卸しと情報開示の質向上を先行させよ」と呼びかける。
報告書が描く七つの要諦を物語で読む
取締役会が環境DD方針を従業員と協議して策定し、調達慣行や製品設計を改訂する決断を下す場面から物語は始まる。衛星データと現地ヒアリングで森林破壊リスクを特定し、地域NGOや住民との対話で対策の優先度を決める。契約に改善義務を盛り込み、排水や土壌の測定値をKPIとしてサプライヤーと共有する。汚染が発覚すれば被害者補償と環境復元を同時に進め、その経過と成果を開示する。苦情窓口に寄せられた知見を次のサイクルに反映し、学習する組織へ昇華する――こうした循環を七つの要諦として織り込み、「単なる手順書」ではなく実務の追体験として読める構成だ。
トランプ政権復活と規制の綱引き
米国ではトランプ政権が復活し、SECの気候情報開示規則が棚上げになる可能性が囁かれる。EUの規制延期も産業界からの「競争力低下」批判や米国ムードへの配慮が背景にある。しかし欧州議会は民事責任条項を残し、段階適用という形で政策の軸足を維持した。規制のペースは揺れても、投資家は「透明なプロセスを示せる企業」を選別する傾向を強めるだけだ。
報告書は、日本企業が今のうちに環境DDを経営フレームに組み込めば、米欧規制の温度差を逆手に取り、市場での信頼を高められると指摘する。
読者が得る学び
第一に、環境DDは訴訟リスクを避ける防御策に留まらず、調達網のレジリエンスを高める攻めの経営手段になることを理解すべきだろう。第二に、開示とステークホルダーとの対話を早期に整えるほど資本市場での評価が高まるはずだ。第三に、延期は「抜け道」ではなく「キャッチアップの猶予」であり、この期間に取引慣行や苦情処理を磨いた企業こそ将来の競争優位を築けると考えるべきだろう。
行政支援と今後
環境省は手順書テンプレートや相談窓口を整備する方針を示し、本報告書を羅針盤として最大限活用するよう促す。準備に動くか様子見に回るか――3年後、数字でその差が表れることは避けられないだろう。