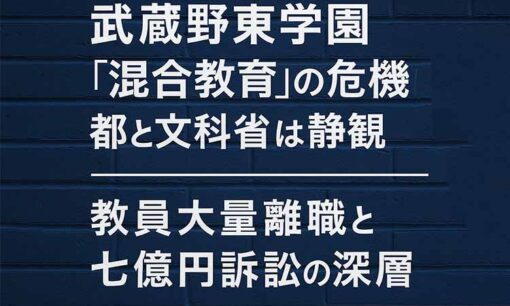日々のニュースを見渡せば、事件や事故、政治の混迷など、不安を煽る情報が溢れている。そんな現代において、「情に訴え心を揺るがす情報だけを届ける」という、極めてユニークな編集方針を貫く新聞がある。株式会社宮崎中央新聞社が発行する『日本講演新聞』だ。
政治・経済の時事ニュースは一切載せない。広告にも依存しない。それでも全国に約1万人の熱心な読者を抱え、週刊で発行され続けているこの新聞は、デジタルの波に揉まれるメディア業界において、独自の「サステナブルなメディアのあり方」を提示していると言えるだろう。
2025年7月、同社は新たなリーダーとして重春文香氏を代表取締役社長に迎えた。宮崎から東京へ拠点を移し、第二創業とも言える挑戦を始めた同社の全貌に迫る。
廃刊寸前から全国紙へ。「日本講演新聞」の独自モデル
『日本講演新聞』の前身は、昭和30年(1955年)に宮崎県で創刊された地域紙だ。転機が訪れたのは今から34年前の1990年頃。当時、廃刊寸前だった同紙を、重春氏の父である水谷もりひと氏(現・魂の編集長)が引き継いだ。
「一週間遅れのニュースを誰が読むのか」。そんな根本的な問いに対し、水谷氏が出した答えは、「人の心を明るくする情報の専門紙」への転換だった。その核となったのが「講演会」の記録である。
編集方針は誰かの「生き様」を一人語りで届けること
同紙の最大の特徴は、その記事作成プロセスにある。編集部や全国の読者・特派員が「面白い」「感動した」と感じた講演会情報を収集。実際に現地で取材を行い、講師の許可を得てその内容を記事化する。

掲載されるのは著名な経営者の話だけではない。「トイレ掃除を40年間続けてきた人」や「刑務所の管理栄養士」など、メディアのスポットライトが当たりにくい市井の人々の「生き様」や「本質的なメッセージ」も積極的に取り上げる。 文字数は1記事あたり5,000〜6,000字程度。講演者の熱量がそのまま伝わるよう、一人語りの口調で編集され、読者はまるでその場で講演を聴いているかのような追体験ができる。
広告に頼らず「ファン」に支えられる経営
新聞業界の多くが広告収入の減少に苦しむ中、同紙の収益構造は極めてシンプルだ。広告枠は極めて少なく、売上の大半は読者からの購読料で成り立っている。 発行は週1回(月4回)。現在の発行部数は約1万部。けしてマスに向けた大規模メディアではないが、その読者層は経営者、教師、主婦と幅広く、「記事を切り抜いてファイリングする」「ラインマーカーを引きながら読む」といった熱量の高いファンに支えられているのが強みだ。
かつては営業担当の母・松田くるみ氏が「1日100軒の飛び込み営業」を行い、15年かけて全国へと販路を広げた歴史を持つ。その地道な活動が実を結び、現在では記事をまとめた書籍が出版されるなど、宮崎発の全国メディアとしての地位を確立している。
そして2025年、同社は大きな変革期を迎えた。30代の若き新社長、重春文香氏への事業承継と、東京への本格進出である。
【Interview】「希望の種」を、もっと遠くへ。二代目社長の覚悟

後半では、2025年6月に代表取締役社長に就任した重春文香氏に、事業承継の経緯と、東京進出の狙い、そしてこれからのビジョンについて話を伺った。
継ぐつもりはなかった。それでもバトンを受け取った理由
――まずは、社長就任おめでとうございます。以前は全く異なる分野にいらっしゃったと伺いました。
重春: ありがとうございます。はい、私は元々理系の職場で働いており、メディアとは無縁の世界にいました。8年前に宮崎に戻り入社した当初は、まさか自分が社長になるとは思っていませんでしたし、最初の2年くらいは葛藤もありました。
――そこから心境が変化したきっかけは何だったのでしょうか。
重春: 一番大きかったのは、読者の方々との出会いです。全国で開催されるイベントや講演会に行くと、「毎週届くのを楽しみに待っているんです」「この記事に救われました」と、涙ながらに感謝を伝えてくださる方がたくさんいらっしゃいました。
母からは「無理して継がなくていいよ」と言われていましたが、読者さんの熱い想いに触れるうち、「この灯火を消してはいけない、私が次の世代へ繋いでいかなければ」という使命感が芽生えてきたのです。それで、30歳の時に「35歳になったら社長になる」と自分で決め、今年そのバトンを受け取りました。
東京進出の背景にある「危機感」と「使命感」
――事業承継と同時に、拠点を宮崎から東京へ移されました。この大きな決断の背景には何があったのですか?
重春: 一つは、物理的なアクセスの問題です。宮崎から全国へ行こうとすると、どうしても時間とコストがかかります。もっとフットワーク軽く、行きたい時にすぐに行ける環境に身を置きたかったというのが正直なところです。
もう一つ、より深刻な理由があります。それは「今の日本社会に対する危機感」です。 内閣府の世論調査などのデータを見たとき、10代から70代まで多くの世代が「将来に不安を感じている」と回答している事実にショックを受けました。私たちは「未来に希望が持てる情報」を発信しているつもりでしたが、一番届けたい不安の中にいる人たちには、まだまだ届いていないと痛感したのです。
――「いい情報」があるのに、届いていないもどかしさがあったのですね。
重春: そうです。宮崎で待っているだけでは限界があります。情報と人が集まる東京に私が自ら出ていき、この新聞の存在をもっと広く知ってもらわなければならない。それが、今の時代に私が果たすべき役割だと思いました。
アナログだからこそ伝わる「体温」のある情報
――デジタル全盛の時代に、あえて「紙の新聞」を週1回届けるというスタイルを維持されています。
重春: そこにはこだわりがあります。実際に読者の方を見ていると、紙で読むときの「情報の落とし込み方」はデジタルとは違うと実感します。記事に線を引いたり、余白に感想を書き込んだり。そうやって情報を「自分のもの」にしてくださっているんです。
また、この新聞は「捨てられない新聞」とも言われています。読み終わった後、自分の大切な友人に手渡したり、学校の先生がコピーして生徒に配ったりしてくださる。私たちはこれを「希望の種まき」と呼んでいますが、紙という「モノ」があるからこそ、手渡しで温もりのあるコミュニケーションが生まれるのだと信じています。
――最後に、今後のビジョンをお聞かせください。
重春: まずは私の代で、「日本講演新聞? ああ、知ってるよ」と誰もが言ってくれるような認知度を実現したいです。社会を見渡せば、物質的には豊かでも心の奥が疲れている人が多い。そんな今こそ、「世の中にはこんなに素敵な生き方をしている人がいるんだ」「捨てたもんじゃないな」と思える情報を届けたい。
父が掲げた「心を明るくする情報だけを届けたい」という志を守りながら、新しい時代のリーダーとして、日本中に「希望の種」を蒔き続けていきたいと思っています。
【企業情報】
株式会社 宮崎中央新聞社
代表取締役社長:重春 文香
事業内容:『日本講演新聞』の発行(週刊・月4回発行)、関連書籍の出版、講演会等のイベント開催。 「情報を新聞で読む」という文化を継承しつつ、講演録という独自のコンテンツで読者の心に寄り添うメディアを展開している。





![株式会社エッジコネクションが求めるゲーム感覚で仕事を楽しめる人材とは[対談]代表取締役社長大村康雄氏×取締役趙美紀氏](https://coki.jp/wp-content/uploads/2022/03/0c1689de3a0ec4303243c05e52d76699-1-510x306.jpg)