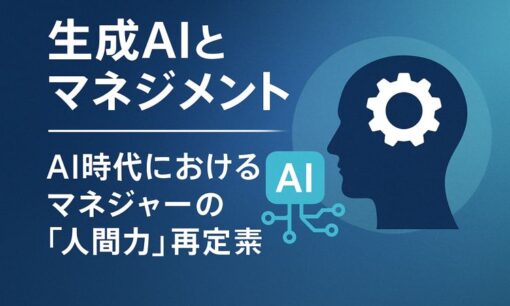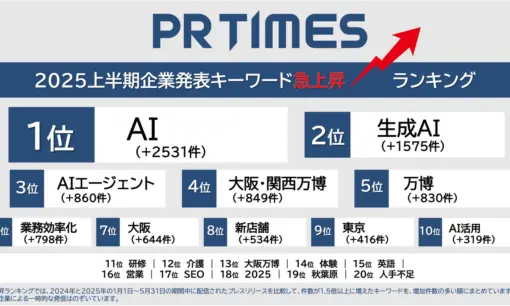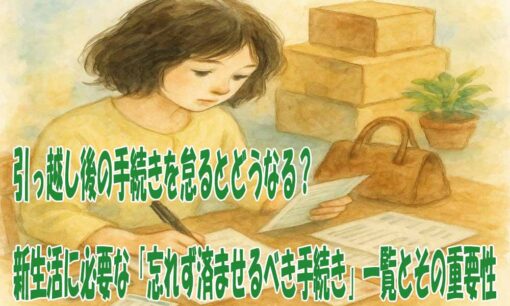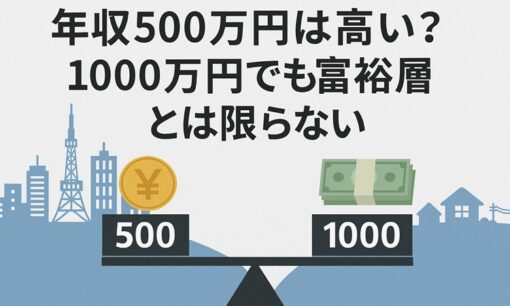生成AIの世界的な普及が加速する中、日本国内での利用は依然として限定的にとどまっている。総務省が7月8日に発表した2024年度「情報通信白書」によれば、日本で生成AIを使ったことがあると答えた人の割合は26.7%。前年の約9%からは3倍に増えたが、それでも米国の68.8%、中国の81.2%、ドイツの59.2%と比べて著しく低い水準にとどまっている。
年代別では20代の利用率が44.7%と最も高く、40代が29.6%、30代が23.8%と続いた。一方、50代以上では顕著に利用率が下がり、世代間の意識格差も明確に表れている。
企業においても生成AI活用の遅れは顕著だ。「積極的に活用する」「領域を限定して利用する」と回答した企業は合わせて49.7%にとどまり、米中の8割超と比較して控えめな姿勢が際立つ。特に中小企業では同様の回答が34.3%と、導入意欲の低さが課題となっている。
こうした現状について、総務省は「日本はAI技術の利活用において、世界の先進国に遅れを取っている」と明記。国際競争力を維持するには、社会生活における生成AIの実装や、企業活動への積極的な統合が不可欠だとしている。
なぜ出遅れたのか 構造的な要因
日本が生成AIで遅れを取る背景には、技術そのものへの理解や需要の問題だけでなく、制度的・構造的な要因も横たわる。教育分野では生成AIを授業に取り入れるためのガイドラインや教師向けリテラシー研修が整備されておらず、多くの教育現場では「禁止」「懸念」に留まっている。
また、経済産業省・総務省・文部科学省などがそれぞれ個別にAI関連施策を展開しており、縦割り行政による連携の不全が政策実行の足かせとなっている。民間側でも、法的リスクや炎上リスクを過度に恐れるあまり、AI活用は慎重に進めざるを得ないという現場の声も根強い。
「経営層が“使うな”と言っている以上、社員が自主的に試すこともできない。先に進めない理由は“無関心”ではなく“空気”だ」都内の中堅広告代理店に勤める30代社員はそう語る。
中小企業・若年層の“リアル”な声
中小企業の導入が進まない理由の一つとして、「導入コストへの不安」と「社内のスキル不足」が挙げられる。神奈川県内で製造業を営む企業の経営者は、「無料版のChatGPTを試してみたが、入力する情報の機密性や、正確性に不安があり、社内展開はしていない」と打ち明けた。生成AIの活用が「攻め」ではなく「守り」の文脈で語られる現実がある。
一方、若年層の中には積極的に使いこなす姿も見られる。大学生のひとりは「論文の要約やアイデア出しにChatGPTを日常的に使っている」と話すが、「教授によっては禁止されることもあり、グレーゾーンにいる感じがする」とも述べた。生成AIの活用は、世代内でも場面によって分断されている。
先進事例はどこにあるのか
国内でも一部では生成AIの積極活用に踏み出す動きが見られる。たとえば奈良先端科学技術大学院大学では、研究開発だけでなく、英語論文の草稿作成支援などにも生成AIが活用されている。また、N高等学校では、ChatGPTを使った作文トレーニングなど、授業に組み込む実践例も報告されている。
さらに自治体レベルでも、横須賀市がいち早くChatGPTを庁内業務に導入した事例が注目された。導入後の実証実験では、職員の資料作成時間が平均で30%削減されたといい、業務効率化への有効性が明確になっている。
こうした先進事例を横展開する仕組みづくりと、導入支援のための予算措置が、今後の喫緊の課題である。
文化的要因も影響 “空気”と“規範”の壁
日本における生成AI普及の遅れには、制度や教育に加えて、文化的な側面も影響していると指摘される。国民性として「リスク回避」や「集団調和」を重視する傾向が強く、ルールの明文化がない限り新技術に手を出しづらい土壌がある。
また、英語ベースで設計された多くの生成AIは、英語でのプロンプト入力が効果的であることから、英語アレルギーの強い日本人にとって心理的ハードルが高いという事情もある。生成AIが“非日常”として扱われる一方、米中ではすでに“日常”の一部になっているという感覚のギャップも大きい。
「職場でChatGPTを使っているのは“裏技”のような扱い。公然と使っていい空気がない」。こうした声が、生成AIの社会実装を遅らせている現実を映している。
必要なのは“使う力”と“許す社会”
白書は、生成AIを単なる技術革新として捉えるのではなく、「社会生活における活用」を推進すべきだと強調する。現場では着実に変化が始まっているが、制度の整備、教育現場での明確なガイドライン、そして企業が安心して利用できる環境づくりが急務である。
生成AIは、単なる「便利なツール」ではなく、社会全体の“知のあり方”を変える可能性を秘めている。その変革に日本が主体的に関わるためには、「使う力」と「許す社会」、そしてその両輪を動かす政策が必要だ。