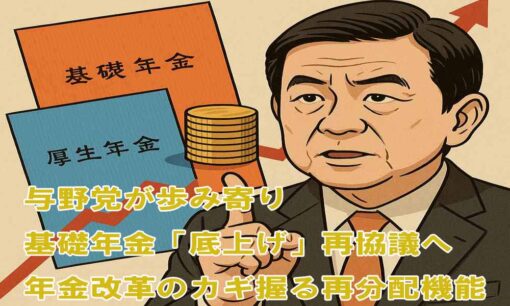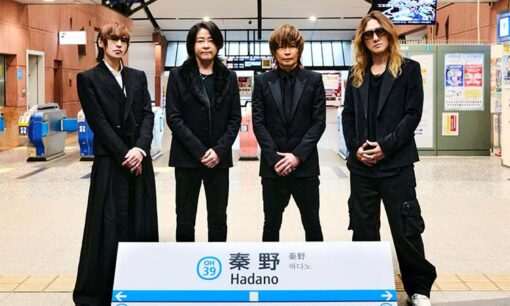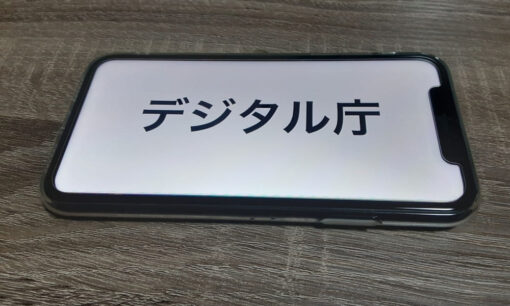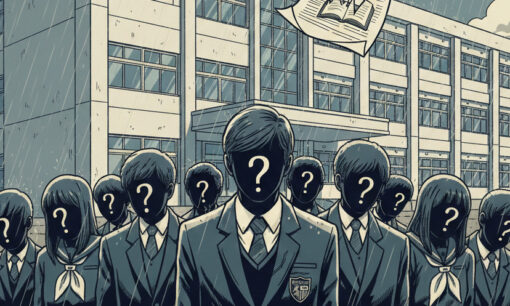2025年度の税制改正により、12月から所得税の基礎控除が大きく変わる。給与所得控除の引き上げ、扶養・配偶者控除の所得要件緩和、さらに「特定親族特別控除」の新設など、年末調整の実務にも直接影響する改正だ。面倒だと敬遠しがちな手続きだが、控除の申告を怠ると、最大で数十万円を取り戻す機会を逃しかねない。今年の年末調整は、まさに“やらなきゃ損”の制度になっている。
12月から変わる税制改正と、控除を活かすポイント
年末調整の季節がやってきた。面倒に感じがちな手続きだが、実態は「払いすぎた税金を正しく取り戻す」ための確認作業である。たった30分ほどの書類確認で還付が見込めることも多く、タイムパフォーマンスは高い。申請を怠れば本来反映されるはずの控除が抜け、“払いすぎ”が残るリスクがある。
年末調整をするメリットと、忘れた場合のデメリット
| 観点 | 年末調整をする場合(メリット) | しない・怠った場合(デメリット) |
|---|---|---|
| 税金 | 払いすぎた税金が戻る(還付あり) | 還付を受けられず、払いすぎたまま |
| 時間・手間 | 約30分~1時間の記入で完了 | 後日、自分で確定申告が必要になる場合 |
| 控除の適用 | 生命保険・扶養・地震保険などが反映 | 控除漏れで課税額が高止まり |
| 心理的安心感 | 年内に精算が完了しスッキリ | 「払いすぎていないか」の不安が残る |
| 金銭面の効果 | 数万円~ケースにより高額の還付も | “取り戻せたはずの額”を逃す可能性 |
2025年度税制改正 12月から基礎控除が段階制に
12月1日施行の改正により、所得税の基礎控除は合計所得金額に応じた段階制となる。令和7年(2025年)分から適用され、年末調整実務にも反映される。国税庁の特設ページによれば、合計所得金額655万円超2,350万円以下は58万円、655万円以下は加算措置により最大95万円(132万円以下の層)まで拡大、2,350万円超2,500万円以下は段階的縮小、2,500万円超は対象外となる(居住者対象の加算措置あり。令和9年分以後の取扱いも併記)。国税庁は改正概要と実務留意点を公表済みだ。
あわせて、給与所得控除の最低保障額は55万円→65万円に引き上げられる(年末調整・源泉徴収関連の各種表も更新)。
扶養・配偶者・大学生世代に関わる新基準
- 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件:48万円以下→58万円以下に引き上げ。勤労学生は75万円以下→85万円以下。
- 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下(給与のみなら概ね103万円超~201.6万円未満に相当)で適用。要件や控除額は本人と配偶者の所得水準により変動。
- 特定親族特別控除の新設:19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入ベースでおおむね123万超~188万円以下)の場合、最⾼63万円を所得から控除。年末調整で受けるには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要。
実務上の適用時期:令和7年12月に行う年末調整から新基準で計算。源泉徴収税額表の見直し等は令和8年支払分からの扱いもあるため、担当者は国税庁資料の該当箇所を確認したい。
見落としやすい主要控除(再確認)
- 扶養控除(大学生・高校生):新基準の下でも、該当すれば特定扶養控除63万円等が適用される。大学生世代で収入が一定額を超えても、新設の特定親族特別控除により段階的に控除が残るのが今回の大きな変化だ。
- 生命保険料控除・地震保険料控除:控除証明書の添付が前提。例年どおり、漏れがちな証明書の有無を確認。
- 社会保険料控除:子の国民年金を親が負担している場合などは親の控除対象。
実務の留意点(会社・従業員)
- 提出書類:今年は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の最新版を使用。提出期限の徹底と証明書類の回収が肝心。
- 年末調整の計算:改正後の基礎控除・給与所得控除で再計算する。源泉徴収税額表・速算表も最新版を参照。
2025年度税制改正対応:所得税・年末調整チェックリスト(最終版)
1. あなた自身の所得
- □ 年間の合計所得金額を把握している(源泉徴収票等で確認)。
- □ 合計所得金額2,350万円以下→基礎控除が原則58万円(655万円以下は加算で拡大、最大95万円は132万円以下)。2,350万超~2,500万以下は段階的縮小、2,500万超は対象外。
- □ 給与所得控除の最低保障額65万円の改正を確認。
2. 扶養家族・配偶者
- □ 扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額要件58万円以下を確認。
- □ 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額58万円超~133万円以下(給与のみなら約103万超~201.6万未満)か確認。
- □ 子が19~23歳で、合計所得58万超~123万円以下なら特定親族特別控除(最⾼63万円)の該当性を確認。申告書の提出が必要。
3. 保険料・年金・寄附
- □ 生命保険料控除の控除証明書を添付。
- □ 地震保険料控除の証明書を添付。
- □ 子の国民年金を親が負担→社会保険料控除で申告。
- □ 寄附金控除(ふるさと納税)の明細・受領証を確認。
4. 年末調整書類の準備・提出
- □ 扶養控除等申告書、特定親族特別控除申告書等を期限内提出。
- □ 保険料控除証明書の紛失時は再発行手続きを確認。
- □ 提出期限(多くは11月中旬~下旬)を厳守。
5. 手続き後の確認
- □ 12月給与明細で年調還付金の有無・金額を確認。
- □ 控除漏れに気づいたら確定申告(還付申告は5年以内)で補正。
- □ 翌年に所得・家族構成が変動する見込み→翌年申告書を更新。
まとめ
今年の年末調整は、基礎控除の段階制(最大95万円を含む加算措置)、給与所得控除の65万円化、扶養・配偶者基準の58万円化、そして特定親族特別控除の新設が同時に走る。制度が拡充・段階化されたことで、従来よりも「取り戻せる」余地が広がる一方、申告書の提出と基準値の正確な確認がこれまで以上に重要になる。年末調整は家計に直結する“実利のある手続き”。面倒でも、今年は特にやっておきたい。