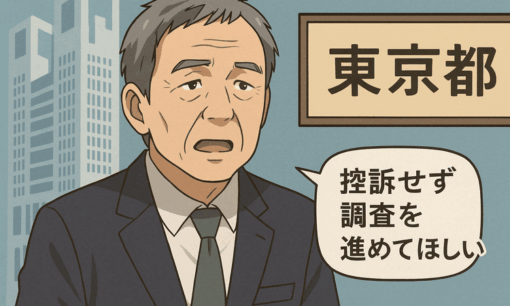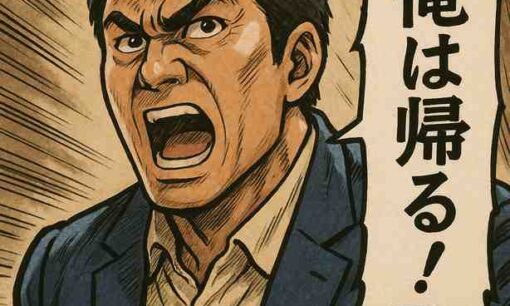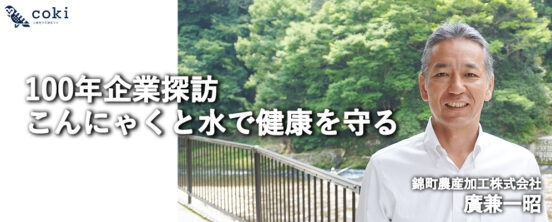1974年に始まったガソリン暫定税率が、ついに年内で廃止される。与野党6党が2025年12月末の完全撤廃で正式合意し、1Lあたり25円の値下げが現実味を帯びる。家計と財政に与える影響を追う。
与野党6党が合意 ガソリン暫定税率の廃止はいつ?
11月5日午前、国会内の会議室で与野党6党(自民、立憲民主、日本維新、国民民主、公明、共産)の税制担当者が静かに合意文書へ署名した。
政府はガソリン税に上乗せされてきた暫定税率(1Lあたり25.1円)を2025年12月31日に廃止する方針で、臨時国会で関連法案を成立させる。
補助金は11月13日から段階的に増額され、12月11日には暫定税率相当の額に達する見込み。補助金終了と同時に暫定税率が撤廃される計画である。
年間約1.5兆円の税収減が生じるが、政府は当面、歳出削減と税外収入で補う方針だ。
半世紀続いた「暫定」税率 制度の経緯と政治の影
ガソリン暫定税率は1974年、第一次石油危機を背景に“道路整備のための臨時措置”として導入された。
当初は2年間の時限措置だったが、景気変動と財政事情を理由に延長を重ね、気づけば50年が経過していた。
1980年代に道路特定財源が整備されると、暫定税率は事実上の恒久税となった。2008年、特定財源制度が廃止されてもなお存続し続けたのは、地方財源の確保と政治的妥協の結果だった。
「“暫定”という言葉が、政治にとって都合のいい“曖昧な逃げ道”になっていた」——元財務官僚はそう語る。
今回の決定は、長年続いた“先送り政治”への決別でもある。
海外では進む炭素課税 日本の燃料税制はなぜ遅れたのか
世界に目を向けると、燃料課税のあり方は大きく変化している。
英国では「燃料デューティ」を維持しつつ、炭素排出量に応じた環境課税が進む。
フランスは「エネルギー移行貢献税」を導入し、ガソリンからCO₂全体への課税へと転換した。
一方の日本は、暫定税率を「道路財源」から「一般財源」に転用した後も構造改革が遅れ、環境政策との整合性を欠いてきた。
結果として、燃料課税が“道路建設の遺産”として残り、国際的な税制潮流から取り残されていた。
暫定税率廃止は、ようやく時代の再設計に踏み出す一歩である。
だが同時に、炭素税や走行距離課税など“次の税”をどう設計するかが、新たな政治課題として浮上している。
ガソリン価格はどこまで下がる? 家計と企業への影響試算
暫定税率廃止によって、理論上ガソリン価格は1Lあたり25円下がる。
補助金(約10円/L)の終了を考慮すると、実際の値下げ幅は約15円前後とみられる。
月100L給油する家庭では年間約1万8,000円の節約効果。
一方で、運送業界や製造業では燃料費の低下が利益率を押し上げる可能性があり、物流コストの抑制が期待される。
ただし、地方財政や道路維持費の財源が縮小すれば、地域インフラの更新が遅れる懸念もある。
値下げの恩恵と財源の再設計、そのバランスをどう取るかが問われる。
SNSで広がる反応 「やっと終わる」「財源はどうするの?」
発表直後、SNSでは「ようやく決断した」「ドライブが楽しみ」と歓迎の声が広がった。
一方で「道路整備が止まるのでは」「また別の増税が来るのでは」といった冷ややかな意見も目立つ。
「25円の値下げはうれしい。でも1年後、別の形で回収される気がする」——そんな投稿が共感を呼んでいる。
国民は、政治の決断を歓迎しつつも、次の一手に警戒を強めている。
暫定税率廃止は終わりではない 日本の税制改革2025へ
半世紀続いた暫定税率の廃止は、単なる値下げではない。
それは「税を何に使うのか」という根本的な問いを突きつける転換点である。
1970年代に道路を支えた税は、21世紀のいま、環境と社会を支える税へと姿を変えようとしている。
炭素課税・環境投資・地方財政の再構築——。その先には、“持続可能な財源”を巡る長い議論が待っている。
年明け、ガソリンスタンドの電光掲示板に新しい価格が灯るとき、私たちは問われるだろう。
「この25円の意味を、どう未来につなげるのか」と。