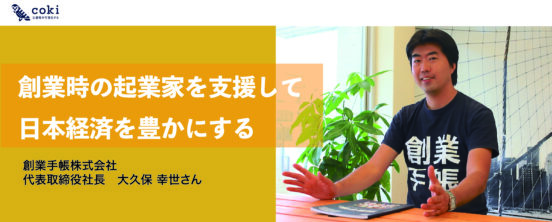猛暑や温暖化の影響で、日本各地で外来種や毒性の強い危険生物の出没が相次いでいる。海岸には猛毒を持つ「ブルードラゴン(アオミノウミウシ)」が漂着し、都市部では外来種の毒グモ「セアカゴケグモ」が繁殖。さらに、潰すと皮膚炎を引き起こす「やけど虫」も広く分布している。鮮やかな姿に惑わされ触れれば重大な被害につながりかねず、専門家は「やたらに触らず、発見したら通報を」と強く注意を呼びかけている。
危険生物が拡大してきた理由
以下のように、日本で危険生物が拡大してきた背景は多様な要因が絡んでいる。
| 生物名 | 主な要因 | 詳細 |
|---|---|---|
| ブルードラゴン(アオミノウミウシ) | 海水温上昇・漂流 | 温暖化による海流や水温の変化でクラゲ類と共に打ち上がりやすくなっている。外洋性で漂流しやすい。 |
| セアカゴケグモ | 温暖化・物流 | 猛暑や温暖化で活動期間が延長。自動車や貨物に付着し、都市部に侵入。人工環境に定着しやすい。 |
| やけど虫 | 温暖化・都市環境 | 高温多湿で繁殖拡大。草地や水辺だけでなく都市部の駐車場・側溝にも生息し、人との接触が増加。 |
海水浴場を脅かす「ブルードラゴン」
スペイン南東部の海岸で、強い毒を持つ「ブルードラゴン(アオミノウミウシ)」が発見され、現地当局が遊泳禁止措置を取った。鮮やかな青色と独特な姿から“竜”に例えられるこの生物は、カツオノエボシなどのクラゲを食べ、その毒針を体内に蓄えて自らの武器とする。新江ノ島水族館の笠川宏子氏は「海中で見つけるのは難しく、南風に流されて打ち上がるケースが多い。決して触らない方がいい」と警鐘を鳴らす。日本近海でも確認例があり、注意が必要だ。
お台場にも現れた「セアカゴケグモ」
猛暑の影響で生息域を広げているのが、オーストラリア原産の毒グモ「セアカゴケグモ」だ。東京・お台場のビル周辺では20匹以上が確認され、駆除作業が行われた。福岡では4歳児がかまれる被害も報告されている。国立科学博物館の奥村賢一研究主幹は「温暖化で成体が長期間活動できるようになった。自動車などに付着して拡散する可能性が高い」と指摘する。環境省は、発見しても素手で触らず、かまれた場合は速やかに医療機関を受診するよう呼びかけている。
小さな虫でも重い皮膚炎「やけど虫」
全国的に広く分布する「やけど虫」も夏場の脅威だ。赤と黒の小型昆虫で、潰すと体液に含まれる「ペデリン」という毒素が皮膚に付着し、まるで塩酸や硫酸をかけられたような激しい皮膚炎を引き起こす。被害を防ぐには、触れないことが第一であり、万一接触した場合はすぐに流水で洗い流し、症状が強い場合は医療機関に相談が必要だ。
広がる“危険生物リスク”への備え
これらの生物はいずれも「鮮やかな色」「目立つ模様」を持ち、人目を引く姿でありながら強い毒を有する。地球温暖化や国際的な物流の活発化が、生息域の拡大や国内侵入を後押ししている。専門家は「やたらに触らず、発見した場合は自治体や専門機関に連絡することが重要」と強調する。猛暑が続く今夏、海や屋外レジャーでは“予期せぬ危険生物”に遭遇するリスクが高まっており、市民への周知と警戒が求められている。
さらに、8月が過ぎて暑さが和らいでも油断はできない。セアカゴケグモのように秋でも活動を続ける外来種も確認されており、季節を問わず注意が必要だ。危険生物は人間の生活圏に入り込む可能性があるため、夏の終わり以降も継続的な警戒と情報共有が欠かせない。