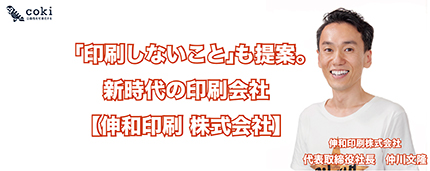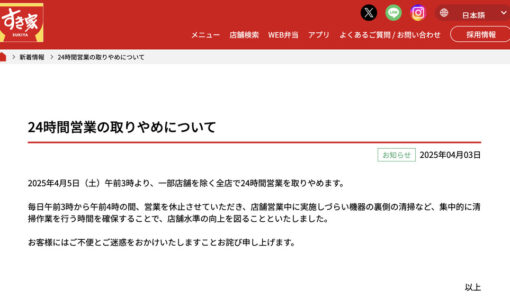「来年の新人、ゼロ」。9月2日に判明したJRA競馬学校の異常事態は、競馬界に小さくない波紋を広げた。要因は体重管理や校則違反とされるが、そもそも騎手になるには、どれほど過酷な条件とプロセスを乗り越える必要があるのか。JRAとNARの公式情報と報道を突き合わせ、現状と“なるための道”を整理する。
来春の新人騎手が「ゼロ」
読売新聞オンラインの報道によると、中央競馬の騎手を養成するJRA競馬学校(千葉・白井)で退学が相次ぎ、2026年春にデビューする新人騎手がいないことが9月2日に判明した。これは1982年の開校以来初という。報道によれば、2023年に入学した第42期(7人)は体重維持の失敗や通信機器ルール違反などで退学・留年が重なり、その期の卒業見込みがゼロになったという。
背景にある「体重管理」と校則:数字で見る厳しさ
JRA競馬学校では、入学時だけでなく在学中も毎朝の検量などで体重管理が求められる。体重上限は年齢区分ごとに細かく設定され、視力・聴力・健康状態なども基準がある。規律違反があれば退学対象になり得ることも、公式要項に明記されている。
地方競馬(NAR)の教養センターでも同様に、入所試験で体重超過はその時点で不合格となるなど、体格・体力面のハードルは高い。検査は閉眼片足立ちやシャトルラン、懸垂、1500m走など全身的能力を測る12項目に及ぶ。
騎手になるための道筋(JRAの場合)
- 受験資格を満たす
入学時の年齢は15歳以上20歳未満。体重上限は46~49キロ、視力や健康状態の基準も厳しい。 - 一次試験と二次試験に合格する
一次試験は身体検査、体力測定、学科試験、面接。二次試験は3泊4日の合宿形式で、運動機能や騎乗適性、本人と保護者の面接が行われる。合格率はわずか5〜10%程度と狭き門だ。 - 競馬学校で3年間学ぶ
基礎課程では乗馬技術や体力・メンタルを鍛え、後半はトレーニングセンターで実習。最後には模擬レースで実戦感覚を養う。 - 騎手免許試験に挑む
学力・技術に関する口頭試験、体重や視力などの身体検査、人物面の評価に合格することで免許が与えられる。学校を卒業できれば合格率は高いが、卒業までが最大の関門だ。
地方競馬(NAR)のルート
地方競馬の騎手を養成するのが「地方競馬教養センター」だ。入学試験は年1回で、体重や視力に加え、懸垂や1500メートル走など12項目の体力テストが課される。乗馬経験は必須ではない。
養成期間は2年間の全寮制。授業では騎乗技術だけでなく競馬法規や一般教養も学ぶ。最後は国家試験に合格する必要があり、体重50キロ未満、視力0.6以上などの条件を満たさなければならない。
過酷な日常生活
競馬学校の一日は早朝5時の検量から始まる。馬の世話、実技、学科をこなし、夜には再び馬の健康チェック。夏場は4時起床になる。食事は栄養士が管理し、体重コントロールの徹底が求められる。この生活を3年間続けられるかどうかが、卒業できるか否かを左右する。夢を抱いて入学しても、体重や視力の問題、精神的な負担で途中で辞めざるを得ない生徒も多い。
デビュー後に待ち受ける現実
騎手免許を得て厩舎に所属すれば、晴れて騎手人生がスタートする。しかしそこからも試練は続く。レースで騎乗するには調教師からの依頼が必要で、成績を残さなければチャンスは回ってこない。さらにレースごとに体重検査があり、基準を超えると出場停止や過怠金といった処分が下される。まさに一流アスリートと同じく、自己管理と結果がすべての世界だ。
専門学校という“予備校”的存在
JRA競馬学校の倍率は例年10%未満と極めて厳しい。そのため、受験対策を目的にした「馬の専門学校」も存在する。ここでは乗馬技術や体力強化に加え、面接や学科試験の指導も受けられる。一般の高校とは異なり数は限られるが、専門学校に通って力をつけ、複数回の受験に挑むケースも多い。小学生からトレーニングを受け入れる学校もあり、早期準備が有利になるのが現実だ。
今回の事態が示すもの
今回の「新人ゼロ」という出来事は、騎手という職業の厳しさを改めて浮き彫りにした。体重・体力・学力・規律、そのすべてを兼ね備えなければ夢は叶わない。しかし、その関門を突破した先には、競馬の華やかな舞台で馬と一体となって戦う喜びが待っている。厳しさと憧れが表裏一体の職業――それが騎手だといえるだろう。