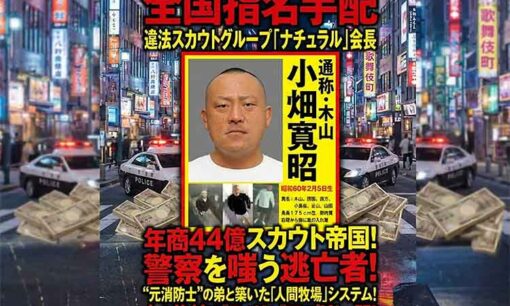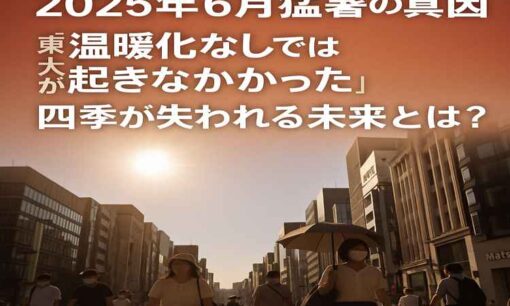全国の郵便局で運転手への点呼が不適切に行われていた問題を受け、日本郵便は7月31日、安全管理体制を抜本的に見直す再発防止策を国土交通省に提出した。新たに安全統括部門を設けるほか、全国約3,200局に「貨物軽自動車安全管理者」を配置し、年度内に約5万人を選任する計画を示した。全社員を対象とした飲酒運転防止研修の実施も盛り込まれ、信頼回復と再発防止に向けた本格的な取り組みが始まった。
日本郵便が再発防止策を国交省に提出 全社員向け研修も視野に
日本郵便は、全国の郵便局において運転手への点呼が不適切に行われていた問題を受け、全国規模での再発防止策を7月31日、国土交通省に提出した。安全を統括する新たな部署を設置するとともに、全国の集配業務を担う郵便局ごとに安全管理責任者「貨物軽自動車安全管理者」を年度内におよそ5万人選任する。
この措置は、同社が展開するトラック運送事業において、道路運送法に基づく許可が一部取り消されるなど、深刻な信頼の揺らぎを受けたものである。一方で、日本郵便は今回の改革により、安全確保に対する意識の徹底と現場レベルでの対応強化を両立させる構えだ。
全社員約33万人が対象 飲酒運転防止研修を計画
提出された改善策には、飲酒運転防止に向けたガイドラインの策定と、全国約33万人の全社員に対する研修の実施も盛り込まれている。これにより、安全運転に関する意識を現場だけでなく管理職層にも浸透させ、企業全体でのコンプライアンス体制強化を図る。
郵便局には、都市部・地方を問わず軽貨物車両での集配業務が多く、時間に追われやすい環境が安全管理上の課題とされてきた。新たに設置される安全管理者は、点呼や運行記録の確認をはじめ、アルコールチェックなど日常的な安全確認業務の責任を担う。
配送業界に広がる「現場重視」の安全対策の流れ
今回の改革は、物流業界全体にも大きな影響を与える可能性がある。コロナ禍以降、ネット通販の急増に伴い、配送ドライバーへの負荷が増す中、安全対策の強化が急務とされていた。
ヤマト運輸や佐川急便など他の大手配送業者においても、点呼記録の電子化やドライバーの健康チェック制度の見直しが進められており、「現場主導の安全管理」への転換が業界横断的なテーマとなりつつある。
労働安全衛生法や道路運送法に基づくコンプライアンス体制の再構築は、単なる「守りの姿勢」ではなく、働く人の命と生活を守るという「攻めの企業姿勢」にもつながる。郵便局が示す今回の取り組みは、そうした転換の象徴といえるだろう。
「誰かを守る」意識が、全社の原動力に
日本郵便が掲げる再発防止策は、単に法令順守を目的とするものではない。安全管理者の新設や全社員研修を通じて、「安全を守る」という共通認識を社内に根づかせようとする姿勢がうかがえる。
再発防止策の実行には一定の時間がかかる見通しだが、配送の最前線で働く人々にとって、こうした動きが「自分たちの働き方を見直す機会」になることが期待される。物流が国民生活の基盤である以上、郵便局を起点とした取り組みの広がりは、社会全体の安心にもつながるだろう。