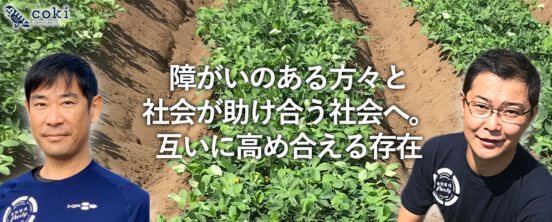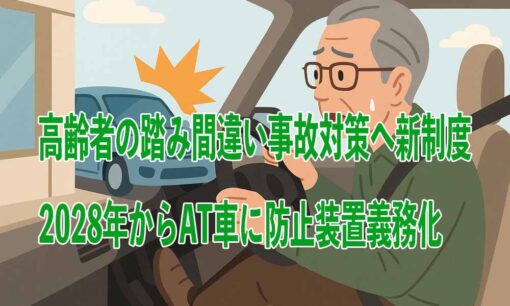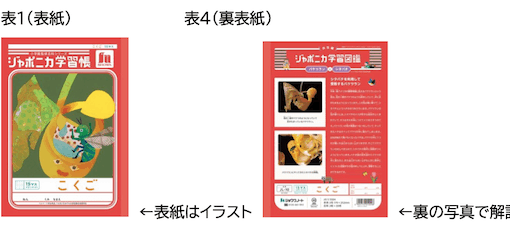国産半導体復権の切り札に公的資金、問われる勝算と実効性

政府は、先端半導体の国産量産を目指すラピダスに対し、1000億円を上限とする出資を行う方針を固めた。出資にあたっては、経営の重要事項に拒否権を持つ「黄金株(特別株)」の保有を条件とし、政府が経営判断に一定の関与を維持する構えである。経済産業省は2025年7月14日、出資に関する基本方針を示し、8月に施行される改正法にあわせて正式決定する見通しだ。
「黄金株」とは何か 国家戦略と企業統治のはざまで
今回政府が保有を求める「黄金株」は、株主構成にかかわらず、特定の経営判断に拒否権を発動できる特別な株式である。かつての郵政民営化や、INPEX(国際石油開発帝石)など戦略企業においても採用された仕組みであり、国益に関わる分野での過度な外資参入や経営逸脱を制御する手段とされてきた。
一方で、企業の自律的な経営判断を縛る可能性もあり、過剰な国家介入とのバランスが常に課題となる。今回のスキームも、国策企業と民間主導の中間的な立ち位置を制度的に構築する試みといえる。
EUVと人材、立ちはだかる現実の壁
ラピダスは、2022年の設立以来、IBMやimecと連携し、2ナノメートル世代の先端半導体の国産化を目指してきた。現在、北海道・千歳市で工場建設が進められており、2020年代後半の量産化が視野に入る。
しかし、その道のりは容易ではない。製造工程の要となるEUV(極端紫外線)露光装置は、オランダのASML社が独占的に供給しており、価格・納期・サポートのすべてで高いハードルが存在する。さらに、EUV運用に必要な専門技術人材の確保は、世界的にも競争が激化している。TSMCやインテルといった超大手と伍してリクルーティングを行うためには、国内の教育・研究体制の立て直しも不可欠だ。
出資による資金援助の枠組みは整いつつあるが、「金額的に十分なのか」という疑問も残る。1000億円は巨額に見えるが、TSMCが熊本工場に投じた金額はその数倍に上る。ラピダスにはこれとは別に民間資金を最大限調達することが政府の審査基準として課せられており、官民連携による総合力が問われることになる。
米中対立の最前線に置かれた「日本の半導体主権」
今回の出資スキームの背景には、米中の先端技術覇権争いがある。米国はCHIPS法に基づき国内半導体産業への巨額補助を展開する一方、対中投資や輸出に制限を課している。中国はこれに対抗する形で独自の技術獲得戦略を進めており、企業買収や人材獲得を強化している。
日本としても、戦略的技術を国内に囲い込む“経済安全保障”の視点が強く求められており、ラピダスはその象徴的存在とされている。黄金株は、こうした国際環境下における「制御可能な投資」の一手として位置づけられている。
問われるのは「復権」の現実味
政府による追加出資の判断には、一定の「勝算」があってのことと見る向きもある。ラピダスは、トヨタ、ソニー、NTT、ソフトバンクなど、日本の産業界を代表する企業の出資を受けている。国家戦略に則った基盤が整いつつあるなかで、日本の半導体産業が再び世界に存在感を示すことへの期待がにじむ。
とはいえ、支援に見合う成果が得られるかどうかは不透明だ。技術開発の実行力、商業化までの道筋、そして世界市場での競争力――そのすべてにおいて、政府と民間の“本気度”が問われるフェーズに入っている。