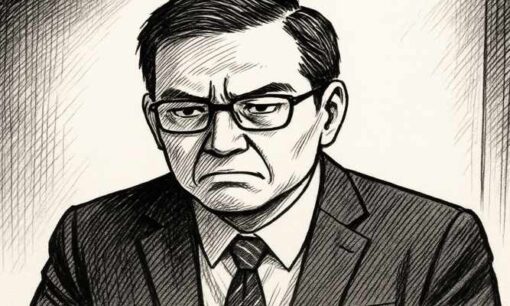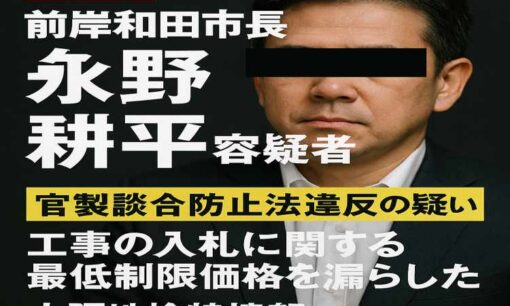年金制度改革法案をめぐり、注目されていた「基礎年金の底上げ」案について、自民党の田村憲久・元厚生労働大臣が「再び法案に盛り込むべきだ」との認識を示した。22日には与党と立憲民主党との間で修正協議が始まり、年金改革の今後を左右する焦点として、底上げの是非とその財源をめぐる議論が熱を帯びている。
所得再配分としての「底上げ」は有効と主張
田村元厚労相は、BS-TBSの報道番組「報道1930」に出演し、次のように述べた。
「(基礎年金の底上げによって)所得の再配分機能が厚生年金でもできるので、非常に良い制度だと思います。元々は(法案に)入っていたわけですから」
この発言は、与党内の慎重論に押されて法案から削除された底上げ案の意義を改めて訴えるものであり、制度の再設計に向けた姿勢を鮮明にした。
与野党が一致 “若者世代を守る”という視点
同じ番組に出演した立憲民主党の長妻昭・元厚労大臣も、基礎年金の底上げについて「田村氏と私の意見に齟齬はない」と語り、次のように強調した。
「若者や現役世代の将来の年金受給額が減ってしまうのを防ぐためにも、底上げは必要です」
現役世代の将来不安を軽減する観点で、与野党の枠を超えた共通認識が形成されつつある。
「基礎年金の底上げ」とは何か?
基礎年金は、国民年金制度に基づき20歳以上60歳未満の全ての国民が加入する仕組みで、保険料は一律ながら、所得にかかわらず原則同額の年金が支給される。
「底上げ」とは、この基礎年金の支給額そのものを引き上げることで、特に年金額が低くなりやすい非正規雇用者や自営業者、専業主婦らの生活保障を強化する意図がある。
所得再分配機能とは何か?――厚生年金から基礎年金へ
田村氏が言及した「所得再分配機能」とは、高所得層から低所得層へと経済的な支えを移すことで、格差を緩和し、社会全体の安定性を保つ制度的な仕組みを指す。
●今回の議論での所得再分配の仕組み
現在の年金制度では、厚生年金(会社員などが加入)は「保険料=収入比例」であり、高所得者は高い保険料を納める一方、高い年金を受け取る。一方、基礎年金は一律支給であるため、財源が同じであれば、低所得者にとってより大きな恩恵となる。
基礎年金の底上げに厚生年金の積立金を一部充てることで、以下のような再配分が機能する:
| 高所得の厚生年金加入者 | 保険料の一部が基礎年金の財源へ回る |
|---|---|
| 低所得の非正規・自営業等 | 底上げされた基礎年金で恩恵を受ける |
この仕組みによって、高所得者の負担を活かしながら、低所得者の老後の最低生活水準を引き上げることができるとされる。これが「所得再配分機能」の核心である。
財源の壁と与党内の慎重論
基礎年金底上げ案は一度、政府案として法案に盛り込まれていたが、自民党内から「厚生年金の積立金はあくまで保険料を払った人のものであり、流用すべきでない」との声が強まり、削除された。
厚労省内では代替案として、消費税財源の活用や他の税による一般財源投入も検討されたが、現時点では具体化されていない。今後の協議では、この**「財源の捻出」**が制度再導入の最大のハードルとなる。
今後の見通し
22日から始まった与党と立憲民主党の修正協議では、基礎年金の底上げの是非、そして財源のあり方が大きな争点となる。政府は6月に経済財政運営の指針「骨太の方針」を取りまとめる見通しであり、今回の協議は、将来の年金制度の公平性と持続可能性をどう設計するかを左右する重要な分岐点となる。