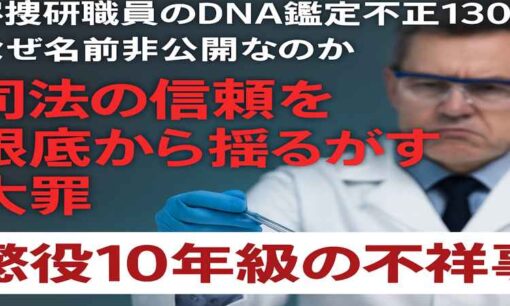野外での活動が増える春から秋にかけて、子どもたちがマダニにかまれる被害が全国で相次いでいる。放置すれば長期間吸血されるだけでなく、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)など命に関わる感染症を媒介することもある。特に乳幼児は被害に気づきにくく、予防と早期対応が重要だ。家庭や保育現場で今すぐ実践できる3つの対策と、刺された場合の正しい処置を専門家の知見をもとに解説する。
春から秋にかけて注意 マダニによる吸血被害が各地で報告
本格的なアウトドアシーズンを迎え、マダニによる被害が再び注目されている。気温の上昇に伴い、マダニの活動が活発化。2025年5月現在、各地の医療機関にはかまれた跡が化膿したり、発熱を訴える患者が散見されており、特に子どもを中心にした家庭や保育施設からの相談が相次いでいる。
マダニは、イエダニと異なり野山や草むらなどに生息し、人や動物の皮膚にかみついて吸血する。西日本では「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」という致死率の高い感染症を媒介することもあり、決して軽視できない存在だ。
乳幼児・子どもが狙われやすい理由
専門家の西海太介氏(セルズ環境教育デザイン研究所代表)によると、乳幼児や幼児は大人に比べて「視認しにくい部位をかまれやすい」傾向があるという。
「肛門周囲や耳の裏、脇の下、頭皮など、本人が不快をうまく伝えられない部位が特に危険です。さらに、子どもは地面に近い位置で行動するため、草むらとの接触頻度が高い。公園の植え込みや校外学習、ピクニックなどがきっかけになることもあります」
マダニが媒介する主な感染症とは
マダニにかまれることで感染する病気は複数あり、重症化するものも含まれる。とくに以下の感染症には十分な注意が必要だ。
| 感染症名 | 病原体 | 主な症状 | 潜伏期間 | 重症化・致死リスク |
|---|---|---|---|---|
| SFTS(重症熱性血小板減少症候群) | ウイルス(SFTSウイルス) | 発熱、嘔吐、下痢、リンパ節腫脹、出血、意識障害など | 約6日〜2週間 | 致死率10~30%と高い |
| 日本紅斑熱 | 細菌(Rickettsia japonica) | 発熱、発疹、頭痛、倦怠感、刺し口のかさぶた | 2~8日程度 | 早期治療で予後は良好 |
| ライム病 | 細菌(Borrelia burgdorferi) | 発熱、遊走性紅斑、関節痛、神経障害 | 数日~数週間 | 慢性化すると神経・関節障害あり |
| Q熱 | 細菌(Coxiella burnetii) | 高熱、頭痛、筋肉痛、肺炎、肝炎など | 約2〜3週間 | 慢性化すると心内膜炎に移行することも |
なかでもSFTSはウイルス性のため抗生物質が効かず、高齢者や免疫力の低い人にとっては致死的となる可能性がある。ウイルスは一部のチマダニ属・キララマダニ属に含まれることが確認されており、西日本を中心に報告例が増えている。
子どもを守るための3つの予防ポイント
家庭や保育現場でできる予防策は以下の通りだ。
(1)服装によるバリアを徹底
- 長袖・長ズボン、長めの靴下を基本とし、肌の露出を減らす。
- シャツはズボンに入れ、ズボンの裾は靴下に入れると効果的。
- 明るい単色の服(白やベージュ)を選ぶと、マダニの付着を発見しやすい。
(2)虫よけの活用
- DEETやイカリジンを含む虫よけスプレーを、ズボンや靴、リュックにも吹きかける。
- 衣類用タイプを選べば皮膚への刺激も軽減される。
(3)行動範囲に注意を払う
- 草むらや獣道、落ち葉が積もる場所は避ける。
- ピクニックシートを敷く場合は、周囲の草丈が低く、日当たりの良い場所を選ぶ。
- 帰宅後は着替えとシャワーを徹底し、親子でお互いの体を確認する。
かまれたかも?と思ったら…家庭での対処と医療機関の活用
子どもが不快を訴えたり、皮膚に黒い点のようなものが張りついていたら、マダニかもしれない。その際の対応は以下の通り。
- できるだけ早く皮膚科や外科を受診することが望ましい。
- 自宅で取り除く場合は、無理に引きはがさず、毛抜きで顎体基部をつまんで真っすぐ引き抜く。
- ワセリンで覆うと、窒息して自然脱落することもある。
重要なのは、かまれた後に発熱・下痢・倦怠感などが出た場合、「マダニにかまれたこと」を医師に伝えることだ。感染症の初期対応が命を左右する。
学校・保育施設も対策強化が急務に
文部科学省や自治体は、森林の近くに位置する保育園・幼稚園、小学校に対し、春以降の園外活動ではマダニ予防の注意喚起を促している。今後は教職員・保育士による衣服チェックや、保護者への予防啓発がより一層求められるだろう。
“子ども目線”の予防教育も大切
最後に、西海氏は「虫を怖がらせる教育だけでは限界がある」とも述べる。
「“自然の中にはルールがある”と伝えることが大切です。虫や生き物と上手につき合う術として、服装や行動を整える。その視点から教えれば、子どもたちは意外とすぐに理解し、自分で身を守る力を育みます」
アウトドアや野外学習が活発になる季節、マダニによるリスクは、自然とのふれあいを遠ざけるものではなく、「備えれば防げるもの」として、親子で向き合いたい。