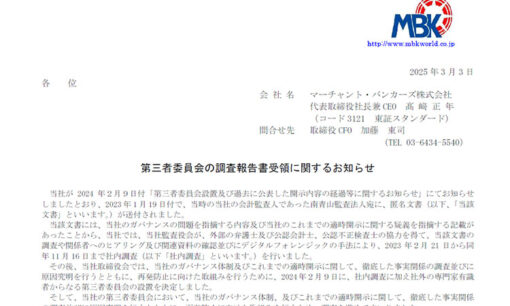近年、家庭やライフスタイルに合わせた柔軟な働き方として、パートタイマーの働き方を選ぶ人が増えている。主婦層だけでなく、定年後のシニアやダブルワーク希望の若者まで、幅広い層がパート就労を選択肢に入れている。一方で、パートで働くことには特有のメリットとデメリットが存在する。本稿では、労働者と企業の双方の視点から、パートタイム労働の利点と留意点を整理する。
労働者にとってのメリット:柔軟な勤務時間と生活の両立
パートタイマーの最大の魅力は、勤務時間を柔軟に設定できる点である。家庭の事情や体調に応じたシフト制が可能で、子育てや介護といった生活との両立がしやすい。また、短時間勤務によって心身の負担も軽減される傾向にあり、ライフステージに応じた働き方として選ばれやすい。
労働者にとってのデメリット:収入制限と待遇の差
パートタイマーには「年収の壁」が存在する。代表的なものとしては、所得税が非課税となる103万円の壁、社会保険の扶養範囲を超える130万円の壁(従業員51人以上の企業では106万円)などがある。これを超えると、社会保険料の負担が発生し、結果的に手取り額が減少する可能性がある。
また、正社員向けに整備された就業規則の適用範囲が曖昧な場合、パートタイマーに不利益が及ぶこともある。特に賞与や退職金、休職制度などは、パートに適用されないことが多く、待遇面での格差が課題とされている。
法律上は「労働者」に区別なし、有給休暇や休憩時間は同様に適用
労働基準法では、正社員とパートタイマーを区別しておらず、有給休暇や労働時間・休憩時間の規定は同じく適用される。たとえば、有給休暇の取得には「6か月間継続勤務し、8割以上出勤」という要件があり、付与日数は週の労働日数に応じて「比例付与」される。
休憩時間も、6時間を超えて8時間以下なら45分、8時間を超える場合は1時間と、正社員と同様のルールが適用される。
企業がパートタイマーを雇うメリット:コストと柔軟性
企業にとってパートタイマーを雇用する主なメリットは以下のとおりである。
- 人件費の抑制:パートは正社員より賃金が低く、賞与や退職金の対象外とされることが多い。社会保険の適用範囲も限定されており、総人件費の抑制が可能。
- 繁閑に応じた人員調整:シフト制により、忙しい時間帯や曜日だけの勤務を依頼しやすい。
- 地元人材の活用:地域に根ざした採用ができ、転勤の心配もなく安定した労働力を確保しやすい。
- 即戦力の導入:マニュアル化された定型業務には、経験者の即戦力化が期待できる。
企業がパートタイマーを雇うデメリット:待遇差と人材の流動性
一方、企業側には以下のようなデメリットも存在する。
- スキル蓄積が困難:短時間・短期間の勤務では人材育成が進みにくく、キャリア形成も難しい。
- 組織の一体感が弱まる可能性:正社員との待遇差により、モチベーションや帰属意識に差が出る。
- 法的リスクの増加:パートタイム労働法や同一労働同一賃金の原則により、待遇格差の合理性が求められる。
- 年収制限による稼働制限:パート側の希望により勤務日数や時間に上限が生まれ、フル活用が困難なこともある。
今後のカギは「待遇の明文化」と「均衡の確保」
パートタイマーの活用は、企業にとっても労働者にとっても重要な選択肢だが、その活用にはルールの明確化が不可欠である。企業はパートタイマー専用の就業規則や待遇方針を整備し、労働者との認識のすり合わせを行う必要がある。
また、2020年の法改正により、職務内容や責任の度合いに応じた「均衡待遇」が強く求められている。待遇差の合理性を説明できないままでは、労使トラブルの温床となりかねない。パートタイム労働者を組織にとっての戦力と位置付け、誠実に対応する姿勢が問われている。