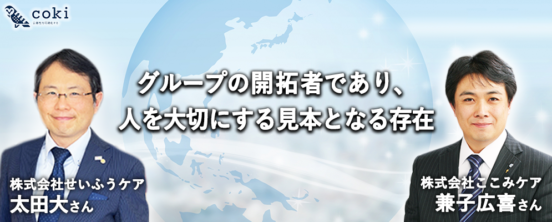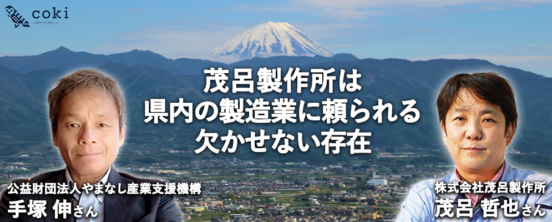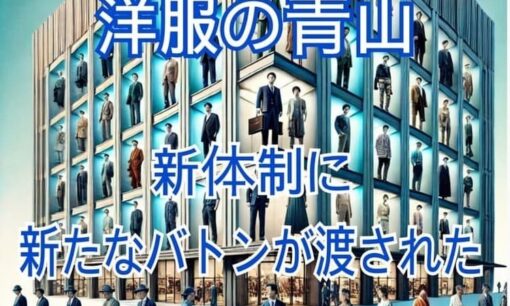季節外れの猛暑や寒波、極端な天候の急変など、近年の日本列島を取り巻く気象は、“異常”という言葉がもはや日常となりつつある。その影響は自然環境だけでなく、私たちの体調にも深刻なかたちで現れている。
今年3月下旬、東京都内では最高気温が25度を超えた翌日に雪が降るという、かつてない寒暖差が観測された。日内の気温差が20度を超えた地域もあり、気象庁は「春の天候としては極めて異例」とした。こうした気象の急変により、「倦怠感が抜けない」「頭痛が続く」「めまいで外出が怖い」といった声が相次いでいる。
自律神経が崩れると、生活そのものに影響が出る
寒暖差がもたらす体調不良は、「寒暖差疲労」とも呼ばれ、医学的には自律神経の乱れが原因とされる。私たちの体は、気温の変化に応じて体温や血圧を調整しているが、その調整役となるのが自律神経である。寒暖差が激しいほど、その働きに過剰な負担がかかり、頭痛や肩こり、不眠、冷え、不安感といった症状が現れる。
東京都世田谷区にある「せたがや内科・神経内科クリニック」では、「寒暖差疲労外来」を設けている。院長の久手堅司医師によれば、特に女性や更年期世代の患者が多く、「季節の変わり目になると、家事もままならないほど体が重い」と訴える人も珍しくないという。
「最近では、患者さん自身が“これは寒暖差疲労かもしれない”と自覚して来院するケースも増えています。気温差に加え、気圧の変動も関与しており、頭痛や古傷の痛み、気分の落ち込みといった症状を引き起こすことがあります」(久手堅医師)
気づかないうちに蓄積する“目に見えない負荷”
寒暖差がもたらす負担は、目に見えづらい。そのため、対処が遅れがちになるのが実情だ。だが、自律神経のバランスが崩れたまま放置すれば、やがて熱中症のリスクや慢性的な体調不良へとつながるおそれがある。
久手堅医師は、「特に一日の気温差が7度以上になると、症状が出やすくなる傾向にあります」と指摘する。さらに気圧の急降下が加わると、自律神経の負荷が倍加し、内耳が感知した気圧変化が“異常な揺れ”として脳に伝わり、めまいやふらつきにつながるという。
不調を防ぐ生活――“備え”が最大の防御に
では、こうした不調を防ぐには、日々どのような生活を心がければよいのか。
● 着脱しやすい服装で「体温調整力」を養う
日中と朝晩の気温差に備え、重ね着で調整しやすい服装を基本とする。ストールや薄手のアウターは、急な冷え込みに対応する心強い味方になる。
● 自律神経を整える基本の生活習慣
起床・就寝時間を一定に保ち、朝に太陽光を浴びて体内時計をリセット。バランスの良い食事と軽い運動、十分な睡眠が、自律神経の働きを整える礎となる。
● 室内と屋外の気温差にも注意
エアコンや暖房の効いた室内から外に出る際の気温差も、見逃せない負担要因。首・手首・足首の“三首”を冷やさないよう意識するだけでも予防効果は高い。
不調を感じたときの“セルフ回復術”
もし寒暖差の影響で不調を感じ始めたら、次のような対策を講じることで、早期の回復が期待できる。
● 耳と首のストレッチで自律神経の血流を促進
・耳たぶを横に引っ張ったり、ぐるぐる回す
・タオルを首にかけて、上下に軽く30秒ずつ引っ張る
→ いずれも1〜2分ででき、耳や首まわりの血流を改善して自律神経の安定を助ける。
● ぬるめの入浴で副交感神経を優位に
熱すぎない38〜40℃のお湯に15分浸かることで、緊張した神経がほどけ、リラックス効果が得られる。ヒートショック防止のため、脱衣所や浴室の温度調整も忘れずに。
● 甘い物やカフェインの過剰摂取を控える
不調時には甘い飲み物やコーヒーに手が伸びがちだが、急激な血糖値上昇や神経の刺激は逆効果になる場合もある。白湯やハーブティーで穏やかな回復を。
“体調は気象に左右される”という前提を持つ
異常気象のもとでは、体のほうが“天候に順応する力”を超えて疲弊してしまうことがある。だからこそ、「気象に体が反応してもおかしくない」と理解する姿勢が大切だ。
寒暖差に備え、自律神経を整える生活を日々意識すること。それが、これからの気候変動時代を健やかに生き抜くための“新しい生活防衛策”といえる。