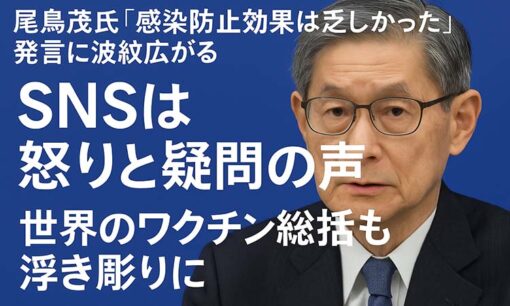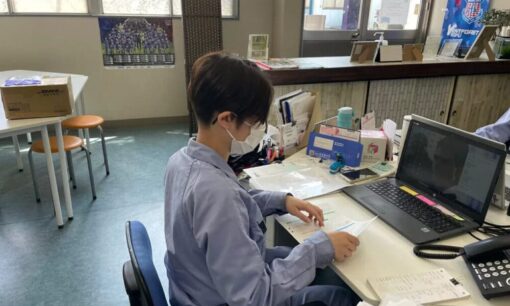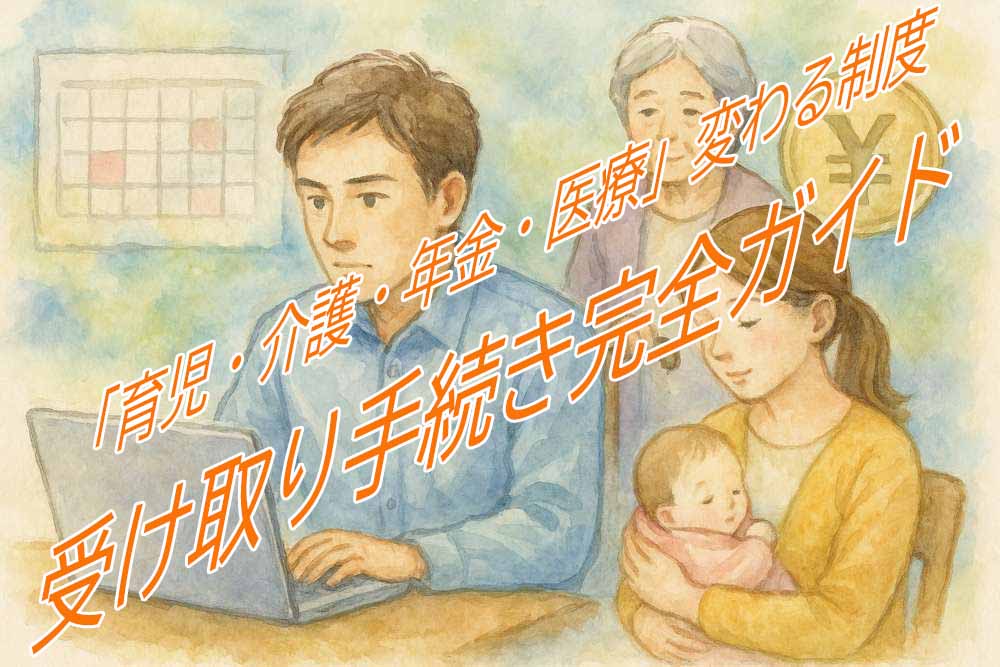
支援金・給付金・年金…新年度に変わる私たちの生活。見逃せない申請方法も徹底解説
2025年4月、新年度の始まりとともに、育児・介護・社会保障を中心とした国の制度改正が施行された。対象は多岐にわたり、少子化対策、労働と家庭の両立支援、高齢者の医療保険見直しなど、現代の生活課題に応じた措置が盛り込まれている。
制度を活かすためには、内容を正しく理解し、必要な手続きを確実に行うことが求められる。以下に主な制度の概要と、それぞれの利用に必要な申請方法を詳しく紹介する。
2025年4月施行 主な制度改正と背景
| 分野 | 主な改正内容 | 詳細・対象 | 目的・背景 |
|---|---|---|---|
| 育児制度 | 子の看護休暇の拡充 | 入園式・卒園式・感染症による学級閉鎖なども対象に、小学3年生修了まで拡大 | 育児期の柔軟な働き方の支援 |
| 出生後休業支援給付金 | 夫婦ともに育休14日以上取得で収入減を補填(最長28日) | 育児休業の取得促進、父親の育休取得推進 | |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を育てる短時間勤務者に賃金の10%相当を支給(要件あり) | 育児と就労の両立支援 | |
| 妊婦支援給付 | 妊婦1人につき5万円、妊娠報告で追加5万円(人数分) | 妊娠・出産期の経済支援強化 | |
| 介護制度 | 企業の義務強化 | 介護を申し出た従業員に個別意向確認・制度周知義務 | 介護離職の防止、早期支援介入 |
| テレワークの努力義務化 | 要介護者・3歳未満の子を育てる従業員に対して | 両立支援と柔軟な働き方の推進 | |
| 年金制度 | 年金支給額の引き上げ | 前年度比+1.9%(ただし実質的目減り) | 賃金上昇に連動、実質支給力維持が課題 |
| 医療制度 | 高齢者の保険料増 | 75歳以上の高所得者の負担増 | 医療費の持続可能性確保 |
| 雇用保険 | 自己都合退職時の給付制限短縮 | 給付制限期間を2か月→1か月に短縮 | 転職活動の迅速化、雇用流動化促進 |
利用するには? 各制度の手続き方法を詳しく解説
制度の多くは、勤務先を通じた申請や自治体での届け出が必要だ。以下に、利用のために求められる手続きを分かりやすくまとめた。
| 制度名 | 手続き内容 | 提出先・方法 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 子の看護休暇の拡充 | 書面または電子で「子の看護休暇届」を提出 | 勤務先(会社) | 入学式などの行事も対象。証明書類の提出を求める企業も |
| 出生後休業支援給付金 | 育児休業取得後、会社を通じてハローワークに申請 | 勤務先→ハローワーク | 夫婦ともに14日以上の育休取得が必要。収入確認書類も提出 |
| 育児時短就業給付金 | 短時間勤務開始後に申請 | 勤務先→ハローワーク | 賃金や労働時間の要件に留意 |
| 妊婦支援給付金 | 妊娠届・母子健康手帳交付後に申請 | 居住地の市区町村 | 本人確認書類とともに申請。給付は原則1回限り |
| 介護支援(企業義務) | 本人の申し出により、企業が制度を案内・意向確認 | 勤務先 | 利用には介護休業申出書等が必要な場合あり |
| テレワーク努力義務 | 社内制度を確認し申し出 | 勤務先 | 義務ではなく努力目標。企業ごとに対応に差 |
| 年金支給額改定 | 手続き不要 | 自動反映(日本年金機構) | 通知書で確認可能。6月の支給から反映 |
| 医療保険料変更 | 手続き不要 | 自動反映(市区町村) | 所得に基づき保険料が決定。年金からの天引きあり |
| 失業給付制限短縮 | 離職票等を持参し求職申込 | ハローワーク | 2025年4月1日以降の退職が対象。離職理由の確認あり |
少子化対策を財政面から後押し
今年度から始まる給付金制度は、単に制度を整えるだけでなく、経済的な支援をともなう点が大きな特徴である。妊婦への一律支給や、育児中の収入減への補填は、「経済的な理由で子どもを持てない」層への直接的な対策といえる。背景には、2024年に国会で成立した改正子ども・子育て支援法がある。
働く世代への介護支援が企業義務に
介護との両立支援は、かつては従業員の自己努力に依存する部分が大きかった。しかし今回の改正により、企業側の説明責任や意向確認が法的に義務化された点は、制度運用の転換点となる。特に介護に直面する40歳以降の従業員への情報提供が明記されたことで、予防的な支援も視野に入った。
実質減額の年金支給、「増えても負担感」の声も
年金額は名目では前年度より引き上げられたものの、物価上昇や賃金上昇との比較では実質的な目減りとみられている。「手取り感覚」としての生活防衛力をいかに維持するか、今後の焦点となる。
制度改革は、現場の運用で真価を問われる
今回の制度改正は、いずれも人口構造の変化に向き合いながら、個人の働き方やライフスタイルに配慮した内容が目立つ。企業、個人、そして国が三位一体で取り組む新年度の制度改革が、実効性ある支援につながるかどうかは、現場での運用次第である。