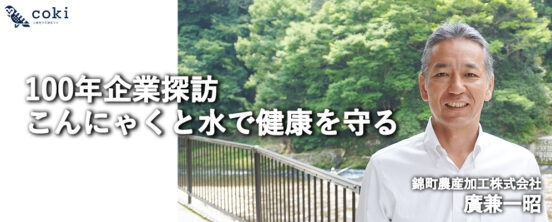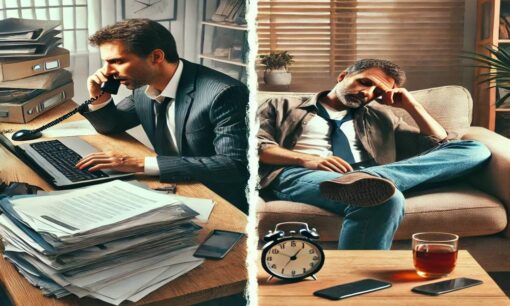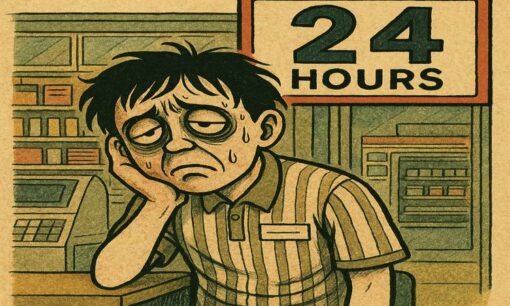新年度が始まったばかりの4月上旬、全国の企業では新入社員が入社式を終え、社会人としての第一歩を踏み出した。その一方で、都内の退職代行サービス事業者には、すでに複数の新入社員から退職依頼が寄せられている。背景にあるのは、職場との“ミスマッチ”と、個人のキャリア観の変化である。退職代行の利用拡大は、一部で“甘え”と批判されるが、企業側の説明責任や職場環境の課題をも照らし出している。新卒離職の現実と、求められる企業の対応を追った。
新年度早々、退職代行への依頼相次ぐ
新年度初日の4月1日、全国各地で入社式が行われ、数多くの新卒社員が社会人として第一歩を踏み出した。しかしその裏で、東京都内の退職代行サービス事業者には、新入社員からの“退職依頼”が早くも寄せられている。
退職代行サービスとは、本人に代わって勤務先に退職の意思を伝え、必要な手続きを代行する民間の有償サービスである。労働問題に詳しい弁護士が関与する「弁護士型」から、一般企業が実施する「民間型」まで形態はさまざまだが、特に精神的な負担が大きいとされる“退職の伝達”を第三者に委ねられる点が、若年層を中心に支持を集めている。
都内の退職代行事業者によれば、2025年3月末までの2か月間における「内定辞退」の代行依頼は35件を数えた。さらに、新年度初日から翌2日の午後5時までには、大学などを卒業したばかりの新社会人からの退職依頼がすでに8件寄せられたという。
22歳女性「理想と現実のギャップに耐えられなかった」
早期退職の背景には、「事前説明と実務の乖離」「職場環境への不安」など、いわゆる“ミスマッチ”があるとされる。
この春、大学を卒業して飲食店に就職した22歳の女性は、わずか5日で職場を離れた。理由について「接客業務と聞いていたのに、実際は裏方作業ばかりで失望した。土日勤務や長時間労働も知らされておらず、続ける自信がなかった」とNHKの取材に答えている。職場に女性社員がおらず、要望も出しにくかったことから、「このような仕事内容なら、最初から別の会社を選んでいた」と企業側の説明不足を悔やんだ。
退職代行会社の部長は「面接時の説明と現場の実態が異なるケースが多い。SNSなどで他社の情報が簡単に手に入る時代に、少しの不信感が離職の引き金になることもある」と話す。
退職代行サービスとは何か――背景と3つの形態
退職代行サービスが日本で注目され始めたのは、2018年前後のことである。先駆けとなったのは、2017年に創業したベンチャー企業「EXIT(イグジット)」が展開したサービスだ。以降、パワハラやブラック企業などを背景に「自分では言い出せないが辞めたい」という労働者の需要に応える形で急速に広がった。
その存在が広く知られるにつれ、弁護士や労働組合なども参入し、退職代行サービスは大きく三つのタイプに分類されるようになった。それぞれの特徴を以下の表にまとめる。
| サービス形態 | 実施主体 | 主な特徴 | 法的対応 | 主な対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 民間型 | 一般企業 | 本人に代わり退職意思を伝えるのみ。比較的低料金でスピード対応が可能。 | ×(交渉不可) | 転職・退職初心者 |
| 労働組合型 | ユニオン(労組) | 本人の委任を受け、勤務先との交渉(残業代・有給消化など)も可能。 | ○(労組として交渉可) | ブラック企業対応希望者 |
| 弁護士型 | 弁護士事務所 | 法律の専門家が対応。交渉・損害賠償請求・訴訟対応など法的サポートが可能。 | ◎(全面対応可) | 複雑な労働問題を抱える人 |
サービスの形態によって、どこまで企業側と交渉できるか、法的保護の範囲が異なる。特に「未払い残業代請求」や「損害賠償リスクがあるケース」では、弁護士による代行が推奨される。一方で、単に「会社に行きたくない」「退職の意志を伝えるのがつらい」といった心理的な負担が主な理由であれば、民間型でも対応可能とされている。
若年層においては、SNSやネット掲示板などで体験談が拡散されることで利用へのハードルが下がりつつあり、特に20代の利用が年々増加している傾向がある。
企業も“見極め”の工夫を進める
一方で、こうした早期退職を防ごうと企業側も対応を進めている。東京・港区の採用支援企業では、2023年から「バディ制度」を導入。内定者一人ひとりに先輩社員2人がつき、入社前から日常的な相談相手となる仕組みを整えた。バディ制度では、インターン終了後に15分間のフィードバックを必ず実施し、仕事内容や職場の雰囲気に対する違和感があれば早期に共有される。
入社したばかりのある女性は「バディの存在で入社前の不安が和らいだ。正直に相談できる相手がいるのは大きい」と話す。同社の社長も「従来は社員の“気づき”に頼っていたが、今は制度化することで個別対応が可能になった。新卒社員のモチベーション維持にもつながっている」と語る。
「キャリアの安全性」を重視する世代
新卒の離職動向に詳しい「インディードリクルートパートナーズ」リサーチセンターの栗田貴祥上席主任研究員は、現代の若者の就職観に次のように分析を加える。
「現在の学生は『キャリアの安全性』を重視している。待遇よりも、自らの成長を実感できるか、環境が変化しても自力で乗り越えられるかという感覚を大切にしている。企業は内定段階から、どのような支援や成長機会を提供できるのかを、より具体的に提示する必要がある」
また、初任給の引き上げについても「重要ではあるが、離職防止の決定打にはならない」と指摘する。給与では埋められない“意味のある仕事かどうか”の自覚を促すような組織づくりが今後の課題となる。
事業主側の反応と課題――退職代行は「鏡」でもある
退職代行サービスの利用増加に対し、企業側の受け止めはさまざまである。中小企業を中心に、退職者本人からの意思表示がないまま、突然、第三者から連絡が入ることに対して戸惑いや驚きの声が上がっている。
一部の経営者からは、「本来、最後はきちんと向き合って辞めてほしい」「礼を欠いている」といった批判的な意見も聞かれる。直接対話を重んじる企業文化においては、退職代行の手法は非常識だとする見方も根強い。
しかし一方で、従業員が退職の意思すら自ら伝えられない状況にまで追い込まれているとすれば、その背景には職場環境や人間関係、あるいは会社の受け皿としての体制に問題がある可能性がある。実際に、「退職代行の利用は企業にとっての“警鐘”だ」「従業員が本音を言いにくい職場になっていたのではないかと振り返る機会になった」と、サービスの登場をきっかけに社内制度やマネジメント手法を見直す企業もある(株式会社maimoの経営者コメントより)。
また、退職代行業者との対応には法的な注意も必要である。とくに、民間型サービスには「交渉権限」がなく、残業代の請求や離職票の即時発行などに関する要求に応じる法的義務は企業側にない。企業の労務管理を支援する専門家からは「退職代行業者がどの範囲まで正当な代理権を持つかを見極めつつ、冷静かつ法令に則った対応が求められる」との指摘も出ている(キテラボ「退職代行への企業側対応ガイド」より)。
退職代行は、単なる“逃げ”の手段としてではなく、職場に潜在する問題を可視化する“鏡”としての役割も果たしている。企業と働き手との間に横たわる“声にならないギャップ”をどう埋めていくか――その姿勢こそが、離職防止の第一歩になる。