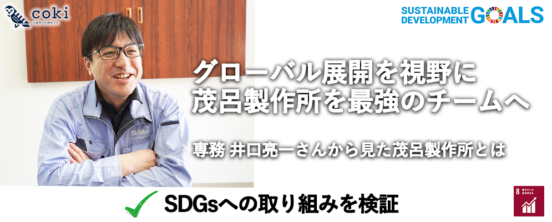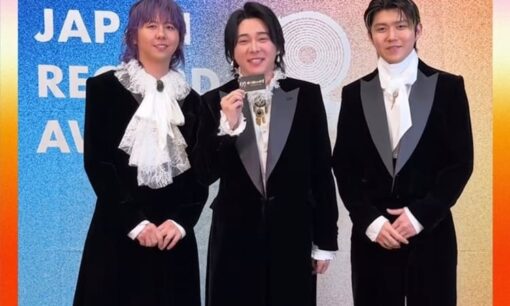正取引委員会からの是正勧告を受け、シャトレーゼが公式謝罪。20年続いた慣行「仕掛依頼」を廃止し、信頼回復へ向けて取引改革に踏み切る。
公正取引委員会の是正勧告 「甘いお菓子の裏で」静かに進んでいた違反行為
春の風が緩やかに吹く3月下旬、霞が関の一室で発表された一枚の文書が、全国に1045店舗を構える菓子メーカーの内部事情を白日のもとにさらした。公正取引委員会が27日に発表した内容は、シャトレーゼが下請法に違反し、取引先企業に対し商品を長期にわたり受領せず、保管費も支払っていなかったというものだった。
その金額は総額2383万円に及び、うち半数を超える約1300万円分の商品が、納品から1年以上もシャトレーゼに引き取られぬまま、下請けの倉庫に眠っていたという。
シャトレーゼは同日、自社ウェブサイトに謝罪文を掲載し、違反の事実を認めたうえで再発防止策を発表した。「法令に対する認識が不十分だった」との説明に、長年にわたり慣行として行われていた取引の闇がにじみ出た。
「仕掛依頼」という名の構造的負担 20年続いた慣習が違法とされた日
シャトレーゼが行っていたのは、「仕掛依頼」と呼ばれる発注方法だった。これは、製品の納期を明確に定めず下請けに製造を依頼し、実際に受け取る時期を明示せず、納品を棚上げにするという形式である。
表面上は発注が成立しているにもかかわらず、商品は下請けの倉庫に置かれたまま。その在庫管理コストや保管スペースの確保といった負担は、全て取引先が背負っていた。
この取引形態は、シャトレーゼにとって柔軟な在庫管理を可能にする“便利な方法”だったのかもしれない。しかし、公正取引委員会はこの方式を「受領拒否」と「不当な経済上の利益提供要請」に該当すると断じた。
そして明かされた事実には、もう一つの重さがあった。こうした仕掛依頼による商品未受領は、実に20年もの間、見直されることなく続けられていたのである。
「仕掛依頼」は本来違法なのか? 制度上のグレーゾーンと運用リスク
ここで疑問となるのが、「仕掛依頼」そのものは違法なのか、という点である。結論から言えば、「仕掛依頼」という取引方式自体は、下請法で明確に禁じられているわけではない。
実際、一定の業界や工程では、柔軟な納期調整や物流合理化の手段として活用されている。しかし問題はその“運用”にある。納入期限を過ぎても商品を受け取らず、しかもその保管料を支払わない、そうした状態が長期化すると、それは「受領拒否」や「不当な利益提供要請」として違反に該当する。
公正取引委員会も、こうした不均衡な取引の実態に対しては、形式上の発注があっても「実質的には支払いを回避している」と見なす姿勢を明確にしている。つまり、仕掛依頼という手法が問題なのではなく、それをどう使い、どこまで相手に負担を強いているかという“中身”こそが問われているのだ。
内部申告が突破口に 見えなかった負担が「違反」に変わった瞬間
今回の違反が明るみに出た背景には、行政の監視だけでなく、現場の声があった。取引先や社内関係者による申告がきっかけとなり、公正取引委員会の調査が入ったとみられている。
「もう保管場所が限界だった」「支払いもないまま1年以上商品を持ち続けていた」こうした声が積み重なり、静かに告発された事実が、ようやく是正に向けて動き出した。
企業が外からではなく“中から”問題に気づき、制度として是正の余地を持てること。それ自体は、現代のコンプライアンス体制が確かに機能している証左でもある。
シャトレーゼの公式対応 「納期明記型」への移行と信頼回復への道筋
是正勧告を受けたシャトレーゼは、「仕掛依頼」の廃止を明言。今後はすべての発注について、納期を明示した「発注依頼」形式に一本化すると発表した。
これにより、発注時点で納期を明確にし、納品と同時に商品を受領する体制が整えられる。保管料の不払い問題も解消され、下請け側の負担は軽減されることになる。
また、法務体制の強化、社員教育の再構築など、企業内部の再発防止策にも取り組む姿勢を見せており、信頼回復への一歩として一定の効果が期待されている。
他業界への警鐘と、ビジネスパーソンが学ぶべき教訓
今回の件は、シャトレーゼ一社の問題にとどまらない。業界に共通する「慣例」とされてきた手法に、違法性が問われたことで、多くの企業が自社の取引慣行を再点検するきっかけとなっている。
特に、製造・小売・飲食などの委託構造を持つ企業では、納期の扱いや在庫の責任範囲が曖昧になりがちだ。だからこそ、形式ではなく実態を重視し、契約の明文化と合意形成を重ねる姿勢が求められている。
ビジネスパーソン一人ひとりが、自社の「当たり前」に疑問を持つことで、不均衡な取引は初めて可視化される。
信頼を築く企業へ 「コンプライアンス」は社会との約束
甘くて親しみやすいケーキの向こう側に、20年続いた不均衡な構造があった。だからこそ今回の改革は、単なる制度対応では終わらせてはならない。
信頼は、危機のときにこそ鍛えられる。コンプライアンスとは、社会との無言の約束であり、ブランドを守る最前線でもある。シャトレーゼがこれからの取引の在り方をどう築いていくのか。その行方を、社会は静かに、だが確かに見つめている。