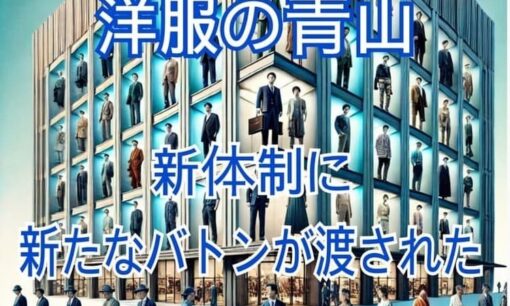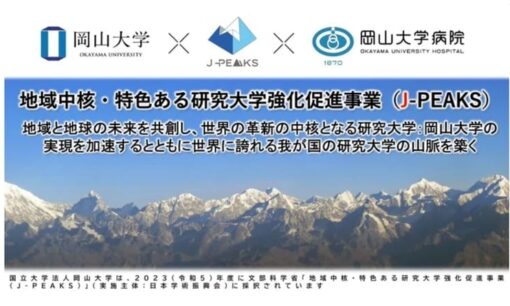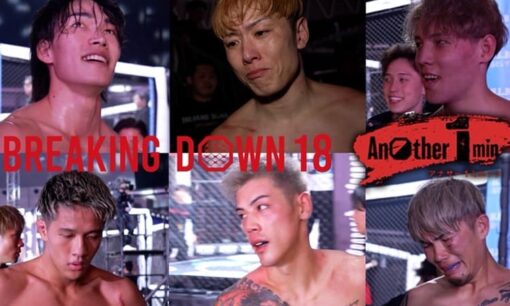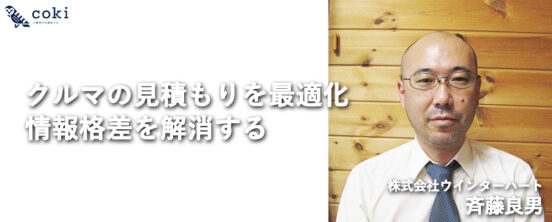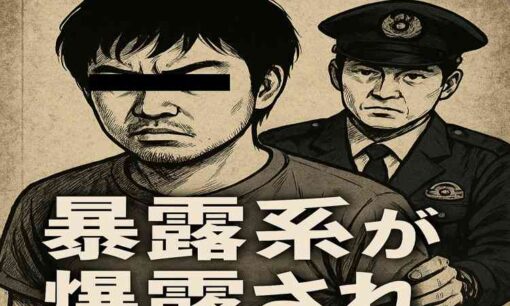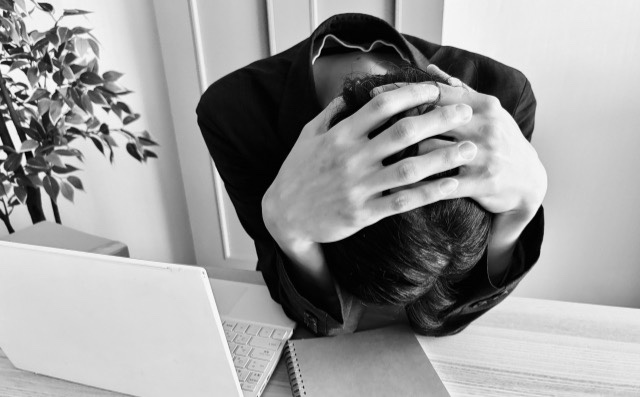
退職代行が日常語となり、社員が突然消えるように会社を去る時代になった。理由は語られず、残された職場には空白だけが積み重なる。その沈黙の裏に何が潜んでいるのか。
新宿のPR会社「おくりバント」が手がける退職引き止めサービス「イテクレヤ」は、辞めたい社員の声を第三者として拾い上げ、企業と社員のすれ違いを可視化する取り組みだ。
退職が当たり前になった今、離職連鎖を止めるための“見えない本音”が、この現場から浮かび上がる。
退職代行が広げた“突然の別れ”
平日の朝、まだ薄暗いオフィスに一通のメールが届く。
差出人は社員本人ではなく、退職代行サービスの名が記されている。
短い文面には「本日付で退職します」とだけ。
理由は書かれていない。
感情も、迷いも伝えられない。
ただ、一方的な終わりだけが突きつけられる。
退職代行の利用は急増し、いまや四社に一社が経験するとされる。
退職を告げた瞬間に巻き起こる詰問や引き留めへの恐れ、職場の人間関係の緊張。
そうした摩耗を避けるために外部に任せるという流れは珍しくなくなった。
突然の離職は、残された現場に大きな負荷をかける。
そこから次の退職予備軍が生まれ、組織は静かに崩れていく。
その連鎖を止められない企業は少なくない。
新宿の一室で始まる組織の聴診
こうした中で登場したのが、退職引き止めサービス「イテクレヤ」だ。
サービス名だけを見れば、社員を引き止める逆退職代行のように思えるかもしれない。
だが実際の現場はまったく違う。
新宿にある小さな会議室。
落ち着いた照明の下、経営者とスタッフが向かい合うが、視線は合わない。
空調の音だけが淡々と響く。
「離職が続いて困っている」
その声には、疲労と焦燥が入り混じっていた。
ここからイテクレヤの作業は始まる。
社員と経営側の双方から、第三者として静かに話を聞き取っていく。
匿名性が担保されることで、普段なら口にできない本音がようやく言葉になる。
まるで壊れかけた組織の鼓動を確かめる“聴診器”のように、細かなひずみを拾っていく作業だ。
経営者と社員の“断層” 語られない本音の層
経営側が推測する退職理由は、大きな構造の話が中心になる。
「成長の限界」「キャリアステップ」「業界の流動性」。
企業の未来を見据えた、抽象度の高い問題ばかりだ。
ところが、社員への匿名インタビューで表れるのは、驚くほど日常的で個人的な摩耗だ。
仕事に必要な書籍を経費で購入しようとした際の、ちょっとした嫌味。
会議で投げかけられた視線。
強い口調で語る上司の情熱が、別の角度から見れば威圧になること。
そのすべてが静かに積み重なり、気付けば出口のない不安になっている。
象徴的なのは「上司のガムを噛む音が不快」という声だった。
一見些細な不満だが、そこには深刻な関係性の亀裂が潜む。
ガムの音を指摘できないほど関係がこじれ、心理的安全性が崩れているのだ。
では、それを誰に言えばいいのか。
その言い出せなさこそが、退職の根底を形作っていく。
「おくりバント」がこの領域に踏み込んだ理由
イテクレヤを運営するのは、東京都新宿区に拠点を置くPR会社「おくりバント」だ。
広告企画、広報戦略、映像制作、デザインなど、企業の外側を整える仕事に強みを持つ同社は、これまで数多くの企業のブランディングに関わってきた。
しかし近年、同社に寄せられる相談が変化していった。
商品の露出や販促計画ではなく、
「人が定着しない」
「職場の雰囲気が悪い」
「本音を誰にも言ってくれない」
といった、企業の内側に関する悩みが増えていったのだ。
外向きのメッセージをどれだけ整えても、内側で人間関係が摩耗していれば、企業の価値は揺らぐ。
この違和感こそが、おくりバントが組織の本音に踏み込むきっかけになった。
PR会社は、組織の物語を読み解き、それを構造化し、適切な形で発信するプロだ。
その技術を外側だけでなく内側にも応用することで、職場に潜む沈黙や歪みを言葉として救い上げることができる。
その視点から誕生したのが、退職引き止めサービス「イテクレヤ」だった。
改善できる企業と、できない企業の分岐点
社員の声を企業へ返すとき、空気は大きく二つに割れる。
ひとつは、「誰がこんなことを言ったのか」と詮索が始まるケースだ。
この反応が出た瞬間、改善は止まる。
社員は二度と本音を語らず、退職予備軍は静かに広がっていく。
もう一つは、耳に痛い内容に沈黙しながらも、自分自身と組織の問題を受け止めるケースだ。
こうした企業では、昇給ルールの明文化、コミュニケーションの再設定、相談窓口の整備など、小さな改革が少しずつ始まる。
その変化は社員の表情に確かに現れ、「もう少しだけ続けてみよう」という気持ちが芽生える瞬間を生む。
退職を無理に引き留めることが目的ではなく、退職に至るまでの孤独や摩耗を見える化し、組織がそれを受け止められるかどうかが鍵になる。
退職は“終わり”ではなく、対話を失った結果
退職代行が当たり前になったいま、退職は個人の自由として尊重されるべきだ。
しかし問題は、退職を決意するまでのプロセスにある。
社員が「辞めたい」と言えない職場で、健全なコミュニケーションは生まれない。
恐怖や諦めが言葉を奪い、その沈黙が企業の内側を静かに蝕んでいく。
退職とは、組織の問題の出口にすぎない。
本当に見つめるべきなのは、出口に至るまでに積み重なった違和感と孤独だ。
イテクレヤは、その沈黙を言葉に変える役割を担い、企業に“鏡”を差し出している。
退職代行時代に求められるのは「関係の再構築」
退職代行が広がった今、企業と社員の関係は大きな転換点に立っている。
退職を防ぐことよりも、退職に至るまでのプロセスを健全化することこそが組織の課題だ。
イテクレヤが示しているのは、
「社員を残す」のではなく、「社員との関係を結び直す」という発想だ。
本音を言える場があり、注意すべきことを注意できる関係があり、不安や疑問を共有できる空気がある。
そうした土台が整ったとき、退職代行も退職引き止めも必要のない組織が生まれる。
退職が特別ではなくなった時代に、企業が向き合うべき本質は、まさにそこにある。