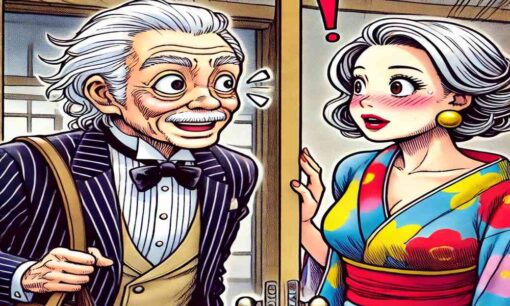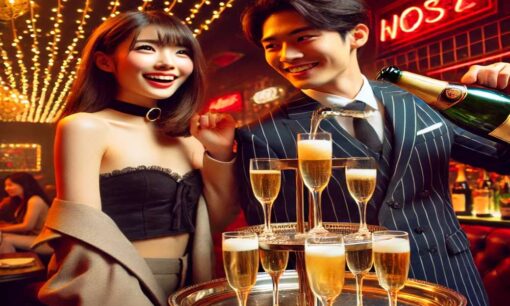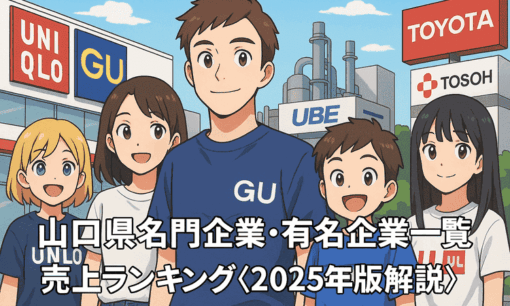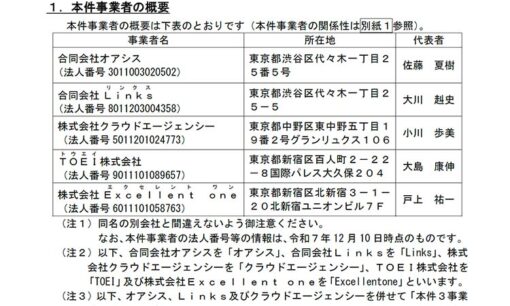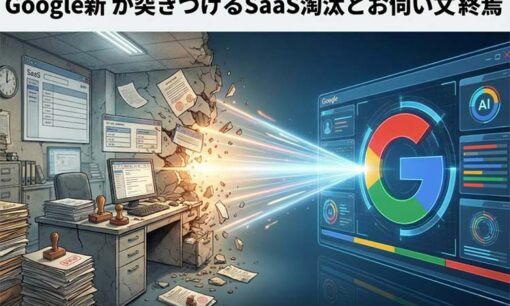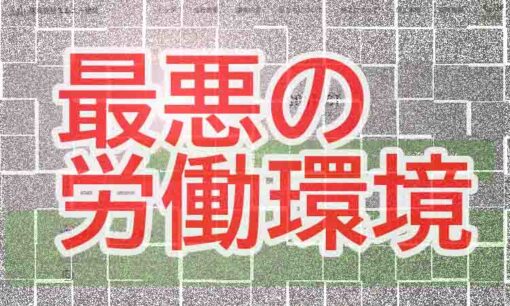11月19日、日中の関係が急速に冷え込むなか、Xを中心に、あるひとつの画像が拡散された。中国外務省の報道官とみられる人物が記者会見で登壇し、「これ以上日本が内政干渉を続けるなら、ハニートラップにかかった政治家やコメンテーターを公表する」と語った。そんな字幕が堂々と添えられている。
画像はよくできており、ホンモノの報道官の写真っぽい。背景の外務省紋章、報道官の無表情さまで本物らしく見える”だ。しかし、その発言についての公式記録は探してもなかなか見当たらない。それでもSNSでは爆発的に反応が広がり、コメント欄は騒然とした。
「本当ならぜひ名簿を出してほしい」
「テレビ局が半分消えるんじゃないか」
「わりと有名人の名前が並んでそう」
真偽よりも“面白さ”が先に走る、そんなネットの現象である。
一方で、冷静な反応も確実に存在した。「これは本当に言ったのか?」「報道官が自国に不利な発言をするとは思えない」。たしかに、ハニートラップを仕掛けていると自白するような発言を、国家の公式会見で行う政治的メリットはほぼない。火元もよく分からない。現段階で断定こそできないが、“フェイクの蓋然性が高い”という見方が妥当だろう(もし、本当に言及された話であるなら、それはそれで中国の怖さを感じるが……)。
だが、この怪しい画像が人々を惹きつけた理由は別にある。「ハニートラップ」という言葉への興味だ。
日本社会は、この古い陰影を帯びた言葉に妙に敏感で、そして弱い。
ハニートラップとは何か 語源と歴史的背景
ハニートラップ(Honey Trap)という言葉は、英語圏の隠語が語源だとされている。“Honey=甘い誘惑”“Trap=罠”を組み合わせた表現で、1950年代ごろから諜報活動の文脈で使われてきたと記録されている。
旧ソ連と西側諸国が激しく情報戦を展開していた冷戦期、とりわけ西ドイツ外交官が東側諜報機関の女性協力者に誘惑され、機密提供を迫られた事件は象徴的だ。これはドイツ連邦議会の印刷物(Bundestag Printed Paper, 1985)にも明確に記録されている。
また、米英の情報機関は、性的な関係や情緒的依存を利用して情報を引き出す行為を
「sexpionage(セクスピオナージ)」と定義し、現在もFBIやMI5が議会向けブリーフィングで警告を発している。
FBIの対諜報資料(U.S. FBI Counterintelligence Briefing, 2010)では、「恋愛・性的関係・情緒的依存を利用し、対象から情報提供・協力・沈黙を引き出す工作」
と説明されているとのこと。
つまり、ハニートラップとは、恋愛や浮気とは別の領域にある工作手法であり、目的は常に情報・弱み・影響力の拡大を狙ったものらしい。古典的な方法でありながら、現代でも頻繁に警戒対象となっている。
それはそうだろう。ネットを探せば、真贋こそわからないが、日本の大物政治家たちが、中国人美女と並び、鼻の下を伸ばしたツーショットでおさまる写真がいたるところに転がっているのだから。
SNSが騒ぐ中で思い出される“実際に起きた”ケース
今回の怪画像が“妙にリアルに感じられた”理由は、過去に明らかになった事例が世界各地に存在するからだ。欧州の外交官スキャンダル、アメリカ研究者の「偽装留学生事件」、英国MI5の「議員への接近警告」。
手口や規模の違いはあれど、“国家レベルの情報収集として起きた事案”がいくつも記録されている。
つまり、今回の画像は胡散臭くても、「ハニトラ自体は存在する」この前提があるため、ネット社会ではあっという間に火がついたわけだ。
永田町で語られた“夜の邂逅” 秘書が感じた不自然な空気
「最初はただ、気さくな女性だと思ったんです」
国会議員秘書の男性はそう語る。打ち合わせを終えた金曜の夜、永田町近くのバーで一人グラスを傾けていたとき、自然な流れで声をかけてきたのは、海外の記者を名乗る女性だった。
「日本の政治に興味がある」
「あなたの意見をもっと知りたい」
押しつけがましくもなく、距離の詰め方も巧みだった。翌週には女性から連絡が入り、二度、三度と食事を重ねていく。
しかし、会話の中身は徐々に“深いところ”へ入り込んでいく。
「その議員は、次の法案でどの方向に動くんですか?」
「まだ表に出ていない話、少しだけ聞かせてくれませんか?」
その時、秘書は背筋が冷えたという。
「彼女は情報の価値を理解していた。こちらが話しやすい空気を完璧に作る、あれは素人じゃない」
男性は連絡先を削除し、一切の接触を断ったという。
視察団に同行した“通訳” 距離感の異常さに気づくまで
別の元官僚は、海外視察団に同行した通訳の存在を振り返る。
「最初は優秀な通訳だと思いました。ところが、食事の席では急に距離を詰めてくる。“あなたの考え方に興味がある”“日本で働きたい”など、極めて個人的な話題が増えていくんです。」
官僚は違和感を覚え、帰国後に女性の所属先を確認すると、そこは現地政府系の組織だった。
「何も起きませんでしたが、今思うと政策の裏側を知りたがっていた。職務を超える関心だった」
通訳を名乗るその女性の意図は、結局最後まで分からなかった。
取材現場にも潜む“罠” 記者が語るヒヤリとした夜
新聞社の記者が語るケースも興味深い。
「特ダネ探しの飲み会で、隣の席の女性が“メディアで働いています”と声をかけてきた。政治家の癖や非公式懇談の内容に、異常なくらい詳しい質問をしてくる」
記者は酒の勢いで、つい未発表の話まで口にしてしまいそうになったという。
「今にして思えば、質問の一つひとつが“裏の情報”を測っていた。情報の値段を知っている人間のやり方です」
記者はそう静かに語った。
紹介した事例はすべて筆者が酒の席で当事者たちから聞いてきたものである。ただ、紹介した3つの事例は皆ハニトラにひっかかりそうになったが、回避したというもの。ようは、あわや嵌められそうになりながら、回避できたものだから、周囲に話せるネタと化しているのだ。
つまり、逆を考えれば、ハニトラを回避できた人だけではなく、嵌められた人もいるだろうことは想像に容易い。そして、嵌められてしまった人は、そのことを誰にも開示できるワケもなく、他国に便宜を図る堕落した存在へとなり下がってしまうのだろう。
フェイクか、現実か。問題は“信じてしまう社会の脆さ”にある
今回の画像は、火元が不明で、発言の合理性も低い。それでも多くの人が“あり得そうだ”と感じてしまった。
理由はシンプルだ。ハニートラップが歴史上、本当に存在してきたから。
そして、SNSが“確証より刺激”を優先する構造をもっているから。
フェイクは実害を伴わない形で社会に入り込み、やがて本物のように振る舞い始める。
今回の騒動は、「ハニートラップ」という古典的な手法と、「SNS社会の脆さ」という現代の問題が交差した象徴的な事件でもあった。