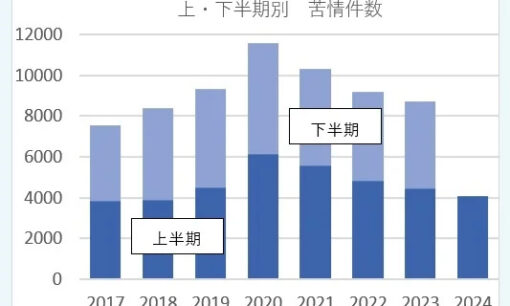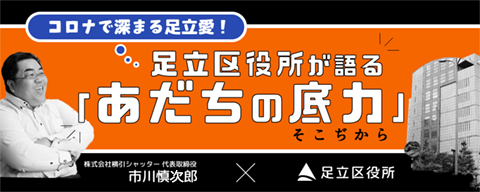店頭からコメが消えた。値札には「お一人様一袋まで」の文字。異常な暑さの夏、誰かが米を隠しているのではという憶測も広がった。
しかし、現場で起きていたのは別の現象だった。猛暑で収量と品質が落ち、国の統計との間に大きなずれが生じたのだ。
見えない不足は人々の不安を煽り、価格を押し上げた。気候と数字のズレが生んだ“令和のコメ騒動”の真相とは。
スーパーから消えたコメ
夏の終わり、スーパーの棚からコメが消えた。値札の横には「お一人様一袋まで」と書かれ、買い物客の足が止まる。
あたかもかつての米騒動が再現されたかのような光景だったが、今回の騒動の背景には、流通や農協ではなく、気候と統計の歪みが潜んでいた。
猛暑が奪った収量と品質
夏の記録的な高温は、田んぼを直撃した。
稲が登熟する時期に気温が上がりすぎると、粒の内部が白く濁る白未熟粒が増える。形が小さく不揃いになり、等級が下がる。
これまで十俵以上とれていた田んぼでも、収量は七俵ほどに落ち込んだ。冷たい水を絶やさぬようにと用水を流し続けても、炎天下の下で温度が上がり、稲の体力を奪っていった。
現場では努力が報われない夏だった。
ふるい目の違いが生んだ“見えない在庫”
減収の実感が広がる一方で、統計上の数字は大きく崩れなかった。
国の収穫量調査では、米を選別する際のふるいの網目を1.70ミリに統一している。だが現場では1.80〜1.90ミリのふるいが主流だ。わずか0.1ミリの差が、全国では数十万トン単位のずれを生む。
統計上は十分に取れているように見えても、実際に食卓に届く量は減っていた。誰かが隠しているわけではない。基準の違いが、存在しない幽霊在庫を生み出したのだ。
作況指数という羅針盤の狂い
さらに事態を複雑にしたのが、収穫量とは別に発表される作況指数だ。
これは平年を100とした豊凶の目安だが、猛暑の時代には実感とかけ離れていた。平年並みとされても、現場では明らかに不作。
こうしたズレを受け、政府は作況指数を段階的に廃止し、実際の収量変化に基づく指標への移行を進めている。
ようやく、国と現場の「ものさし」を合わせる動きが始まった。
変わる気候、変わらない品種
気候が激変する中で、従来の品種では限界が近づいている。
多くのコメは数十年前の気候条件をもとに開発されたもので、35度を超える日が続くと粒が充実せず、収量も品質も落ちる。
高温に強い新しい品種の開発や、AIと衛星データによる収量予測の研究が進むが、実用化には時間がかかる。気候と技術の競争は、もう待ったなしの段階にある。
買いだめと不安が価格を押し上げた
供給の不安は、人の心理にも影響した。
棚に並ぶ袋が減ると、次に買えるか分からないという不安が広がる。十分な備蓄があっても、人々が買い急げば市場はさらに品薄になる。
コメは単なる食材ではなく、安心の象徴でもある。だからこそ、不確かな情報が広がれば、価格の高止まりが起こるのも自然な流れだった。
家庭でできる“もう一つの備え”
この夏、備蓄米を長期間放置して虫が発生したという報告も相次いだ。
常温で二か月放置すれば、未開封でも虫が湧くことがある。農水省は十五度以下での保管を勧めており、冷蔵庫の野菜室が最も適している。
コメを守るのは、政策だけではない。私たち一人ひとりの保存方法もまた、食の安全を支える小さな対策だ。
数字と心をそろえるために
棚が空になったあの光景は、供給の危機であると同時に、情報の危機でもあった。
現場の声と統計の数字がずれていたことで、社会全体が不安に揺れた。必要なのは、正確なデータと冷静な判断、そして生活者の理解だ。
コメ騒動が教えてくれたのは、信頼できる情報がなければ、人は簡単に恐れに流されるということ。正しい数字と静かな行動、その二つが次の混乱を防ぐ唯一の鍵になる。