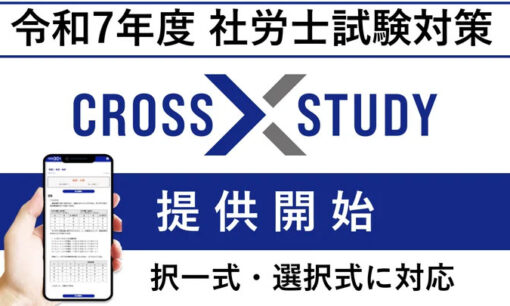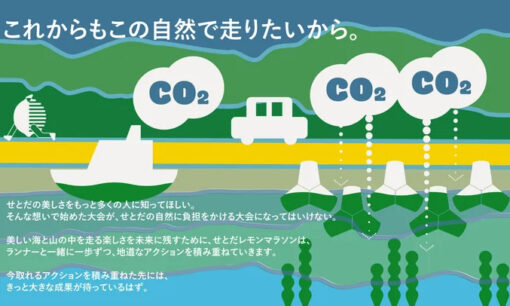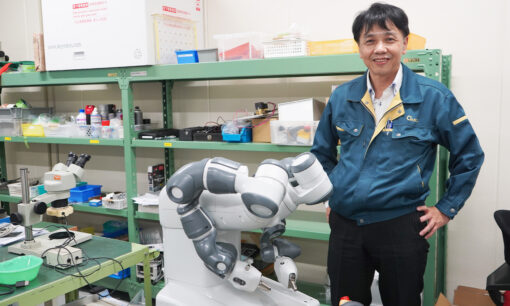静かな水辺で、稲の葉がわずかに揺れた。
その下を音もなく泳ぎ抜けたのは、南米原産の大型ネズミ「ヌートリア」。
本来、日本にはいなかったこの外来種が、いま全国で急速に増えている。
田畑を荒らし、稲やレンコン、野菜を食べ尽くす被害が広がる一方で、捕獲した個体を“ジビエ料理”や教材として再利用する動きも生まれている。
「食べて駆除する」という発想は、果たして持続可能な解決策になりうるのか。
浜松や愛知では、自治体や高校生が行動を起こし始めた。
ヌートリアをめぐる“人と自然のせめぎあい”は、いまや地域を越えて私たちの暮らしに静かに迫っている。
水辺に潜む“静かな侵略者”
夕暮れの田んぼを吹き抜ける風。稲の間に、なにかが音もなく動いた。
茶色い体、オレンジ色の前歯。南米原産の大型ネズミ「ヌートリア」だ。
明治期に毛皮を目的に日本へ持ち込まれた彼らは、野生化して西日本を中心に繁殖。
いまでは東海や関東でも目撃され、浜松市では年間600件を超える報告が寄せられている。
水辺近くに巣を作り、稲やレンコン、野菜などを食べ荒らすヌートリア。
稲が食べられた跡は、田んぼに残るしっぽの筋で分かる。
「苗の上半分だけをきれいに食べてしまう」。農家たちはため息をつく。
その被害は収穫量に直結し、青米(未成熟の米)が増える原因にもなる。
驚異の繁殖力 「増える一方」
ヌートリアは草食性だが、問題はその繁殖力にある。
栄養状態が良ければ年に2~3回、一度に5~6匹の子を産む。
「見つけた時には、もう手遅れになっていることもある」と、現場の声。
泳ぎが得意なため、水路を伝って住宅地にも侵入する。
農作業中に突然飛び出して人にかみついた例もあり、行政は捕獲用わなの貸出を進めている。
「攻撃性は低いが、油断は禁物」。専門家は注意を呼びかける。
「カピバラと間違えないで」生駒市の呼びかけ
近年は都市部にも出没し、奈良県生駒市では子どもがヌートリアに興味を示すようになった。
市は「かわいいカピバラと違います」と注意喚起のチラシを配布。
「絶対に触らないように」と強調している。
見た目の愛らしさとは裏腹に、感染症のリスクがあるためだ。
ヌートリアは肝炎などの原因となる寄生虫を保有している場合もあり、不用意に近づいたり、素手で触ったりすることは危険とされている。
“食べて駆除”という新たなアプローチ
一方、静岡県では、捕獲したヌートリアをジビエ料理として活用する動きも。
レストランではローストや煮込み料理として提供され、「鶏肉のように淡泊で柔らかい」と評判を呼んでいる。
食用以外にも、毛皮を座布団や教材用の標本として再利用する例が増加中。
「駆除した命を無駄にしない」という考えが、地域の新しい試みを支えている。
ただし、野生動物ゆえのリスクも存在する。
寄生虫や病原体の危険を考慮し、専門の処理や加熱調理が不可欠だ。
「安易な個人調理は避けるべき」と、専門家は警鐘を鳴らす。
高校生たちが挑む“畑の厄介者”との闘い
愛知県の農業高校では、ヌートリアによる野菜の食害をきっかけに調査が始まった。
生徒たちは捕獲した個体にGPSを取り付け、行動範囲を追跡。
「自分たちの手で被害を減らしたい」と、科学的なアプローチで挑んでいる。
夜間カメラには、レタスをムシャムシャと食べるヌートリアの姿。
被害額は県内で年間1500万円にのぼるという。
彼らの研究は、将来の被害防止策や環境教育にもつながっていくはずだ。
ヌートリアが堤防や土手に巣穴を掘ることで、地盤が脆くなり崩落を招く危険も指摘されている。
農業被害を超え、インフラ維持の課題としても注目されつつある。
人と自然の境界で問われる“共存”の形
ヌートリア問題は、「駆除」か「共存」かという単純な二択では語れない。
命を資源として再利用する動きもあれば、感染リスクや倫理的課題もある。
どの地域でも共通しているのは、「早期発見と地域の協力」が鍵だということ。
静かな水辺に潜むヌートリアの姿は、人と自然のバランスを問い直している。
人の生活圏と野生の世界。そのあいだにある“見えない境界線”を、どう描き直していくのか。
それは、私たちの暮らし方そのものを映す鏡かもしれない。