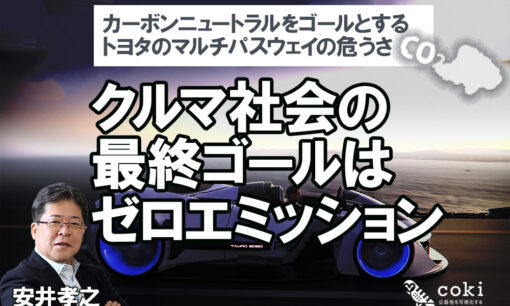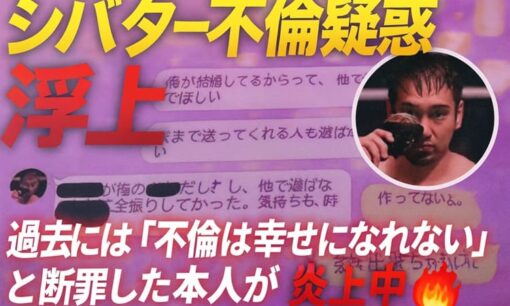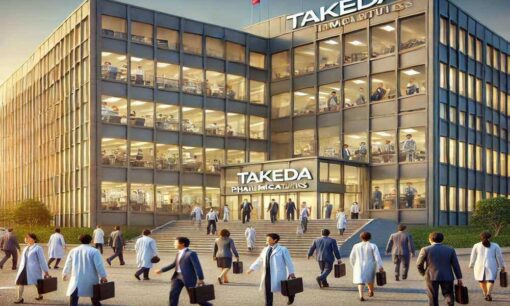物価高のいま、政治は何を最優先にすべきか。
減税か、企業献金の廃止か、それとも議員定数削減か。
自民党と日本維新の会が連立合意に向け最終調整を進めるなか、「高市政権」誕生を前に永田町の空気が急速に熱を帯びている。
永田町の廊下に残る熱気
10月17日夜、国会内の照明が落ちても、廊下にはまだ人の気配が残っていた。
会見を終えた記者たちのスマートフォンが一斉に光る。
「協議は大きく前進」。
自民党・高市早苗総裁と維新の藤田文武共同代表がそう語った瞬間、永田町の空気がわずかに変わった。
21日の首相指名選挙まで残りわずか。
野党間の連携は崩れ、票読みは過半数まで「あと2議席」。
政権交代ではなく“再編”の予感が漂う。
争点① 「食品ゼロ税率」はどこまで現実的か
維新が提案する「食品の消費税0%(2年間限定)」は、家計への即効性を重視した政策として注目を集める。
ただし、税収減をどう補うか、地方財政や社会保障への影響をどう抑えるか、設計は容易ではない。
立憲や国民民主からは「財源論が曖昧だ」との指摘もあり、自民側も慎重姿勢を崩していない。
それでもSNSでは「試験導入で効果を見てから恒久化すべき」と段階的導入を求める声が多い。
消費を喚起し税収を維持できれば、という“逆転の期待”もにじむ。
争点② 「企業・団体献金」廃止論の壁
政治とカネの問題は、公明党離脱の引き金にもなった。
維新は「企業・団体献金の禁止」を明確に掲げるが、自民は地方組織の存立を支える現実を理由に、「規制強化にとどめる」方針を崩していない。
自民幹部の一人は「全廃すれば地方支部が立ち行かなくなる」と語る。
献金禁止は理想として共感を集めるが、個人献金のインフラ整備や公開制度の強化など、代替ルートの設計がなければ実効性を欠く。
短期の政治改革よりも、透明性を高める中長期の制度設計こそが焦点となる。
争点③ 「議員定数1割削減」の象徴性
吉村洋文代表が「絶対条件」と強調するのが、国会議員定数の1割削減だ。
衆院465、参院248議席のうち、それぞれ約50、25の削減を想定する。
自民は方向性を受け入れたと報じられたが、実際には区割り調整や関連法改正などのハードルが高く、
臨時国会中での成立は「極めて困難」とみる声も多い。
それでも“身を切る改革”という言葉の力は強い。
物価高のなか、「政治家も痛みを分かち合え」という国民感情とシンクロしている。
ただし実際の財政効果は限定的で、歳費削減や政党助成金の見直しを併せて議論しなければ、象徴で終わる危うさをはらむ。
過半数まで「あと2議席」 票読みと駆け引き
自民の196議席に維新の35議席を加えても、過半数の233には2議席届かない。
高市総裁は参政党(3議席)や無所属議員で構成される「有志・改革の会」(7議席)に協力を要請。
参政党の神谷宗幣代表は「高市政権には期待している」と述べ、総理指名選挙での協力に含みを持たせた。
連立は制度上の恒常的枠組みだが、総理指名の投票協力は一回限りの政治判断。
双方の温度差を埋める詰めの交渉が続く。
「合意」はゴールではなくスタート
政策協議は、食品ゼロ税率・企業献金・定数削減の「三本柱」を軸に、文言と期限をめぐる最終調整段階に入った。
だが、合意文書が示される20日がゴールではない。
臨時国会の会期、法案化までの手順、次期衆院選の選挙区調整など、現実の政治は細部に宿る。
吉村代表が掲げる「副首都構想」など、大阪発の要求も残っており、地方自民との摩擦が予想される。
自民府連の一部からは「維新と組めば大阪自民が消滅する」との声も漏れる。
民意の割れ目 コメント欄が映す世論
SNSやニュースサイトのコメント欄では、「最優先は減税」「まず企業献金の廃止を」「定数削減こそ身を切る改革」と三者三様の意見が飛び交う。
中には「立憲の反対ありき姿勢より、違いを超えて合意を探す今の流れを評価したい」という声もある。
この多様な反応こそ、政治が再び“選ばれる側”へ戻りつつある兆しかもしれない。
短期と中長期の“二段ロケット”で
物価高の家計支援という短期の即効策と、政治資金の透明化・制度改革という中長期の信頼回復。
二つを二者択一ではなく“二段ロケット”として進められるかが、高市政権の初動を左右する。
21日の首相指名選挙、その一票が日本の政治の「優先順位」を決める瞬間となる。