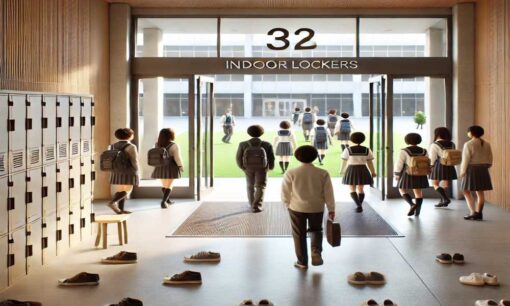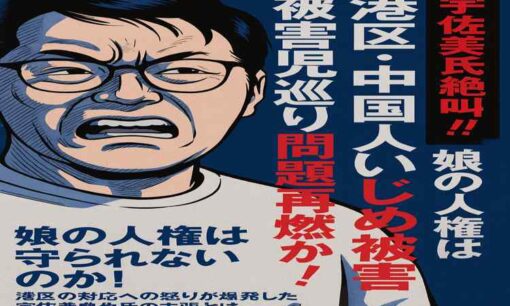東京で開催中の世界陸上で、男子20キロ競歩に出場した金メダル候補の山西利和(愛知製鋼)が、レッドカード3枚によるペナルティーで28位に終わった。勝負所でのスパート直後に科された判定は物議を醸し、SNSでは「AIで判定すべきだ」との声も相次いでいる。今大会では3000メートル障害や短距離種目でも不可解な裁定が相次いでおり、陸上競技の公平性と人気維持に深刻な影響を与えかねない状況となっている。
判定ルールと山西のレース展開
競歩のルールは二つに集約される。第一に「常にどちらかの足が地面に接地していること」。第二に「接地している足の膝が、地面と接触した瞬間から垂直になるまで伸びていなければならない」ことだ。違反と判定されるとレッドカードが提示され、累計3回でペナルティーゾーンに送られる。20キロの場合は2分間の待機となり、4回目は即失格だ。
今回のレースで山西は序盤から先頭集団で安定したペースを刻み、12キロ付近で最初のレッドカードを受けながらも冷静に対応した。しかし15キロ過ぎ、他選手が給水に入った隙をつき一気にスパートをかけて前に出ると、立て続けに2枚のレッドカードを受ける。フォームの乱れが審判の目に留まったとみられるが、微妙な判定であったことは映像からも指摘されている。16キロ地点で2分間の待機を余儀なくされた山西は、順位を大きく落とし28位でフィニッシュ。レース後には「慢心があった。ペースを上げた際の判断が甘かった」と悔しさをにじませた。
ただ、優勝したカイオ・ボンフィム(ブラジル)らのフォームも「走っているように見えた」とSNSで拡散され、警告を受けなかったことに不満が集中。判定基準の一貫性が問われる展開となった。
相次ぐ“疑惑の判定”
判定をめぐる不信は競歩に限らない。男子3000メートル障害決勝では、日本の三浦龍司が最終直線でケニアのセレムに背後から押され、さらに腕を引かれる形で大きくバランスを崩し、メダル圏内から8位に転落した。日本陸連は妨害として抗議・上訴したが、いずれも棄却され、セレムは銅メダルを獲得。ファンからは「明らかな妨害」との声が噴出し、大きな波紋を呼んだ。
また、男子110メートル障害予選では泉谷駿介がスタート時に隣の選手の動きに影響されて大きく出遅れ、予選敗退。フライングの可能性も指摘されたが判定は流れ、結局、審判の裁量に委ねられた。選手の努力や戦略ではなく、判定が結果を左右する場面が繰り返されることで、競技そのものへの信頼は大きく揺らいでいる。
技術導入の可能性と課題
こうした事態を受け、SNSや専門家からは「靴底にセンサーを付けて接地を判定すべき」「コース全体に高精度カメラを配置してAIで自動判定できるように」といった意見が相次いでいる。実際、陸上競技ではすでにフライング判定にスタートブロックのセンサーを導入し、ゴールの着順も写真判定で決している。競歩においても技術を導入する余地は十分にある。
一方で、AIによる厳密な判定を導入した場合、選手の多くが違反を取られる可能性があるとの懸念もある。費用や運用面での負担も小さくはなく、センサー不具合やシステム障害が発生した際の対応など課題も残る。完全に人間の裁量を排除するのではなく、AIを補助的に活用して透明性を高めるハイブリッドな仕組みが現実的だろう。
人気低下への懸念
判定をめぐる騒動が続く中で、ファンの間には「選手の努力が報われないなら誰も見なくなる」との声も広がっている。不可解な裁定で順位が変わる状況は、陸上競技が本来持つ魅力、人間の限界に挑む純粋なパフォーマンスをかき消しかねない。若い世代が陸上を志す意欲に影響を与える可能性すらある。
最高峰の舞台で判定ばかりが脚光を浴びる状況をどう改めるか。公平性の確保は、競技の人気を守る上でも避けて通れない課題だ。人の目と技術をどう融合させるかが、これからの世界陸上の未来を左右するといえる。