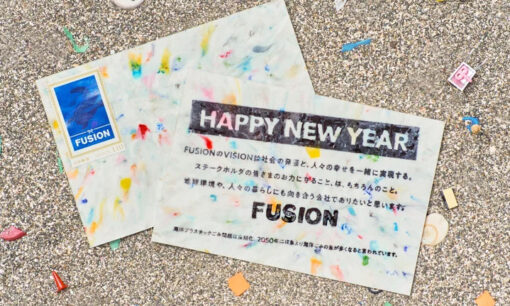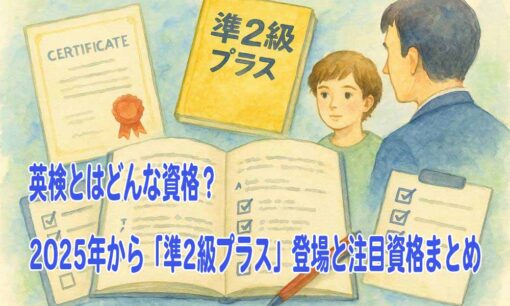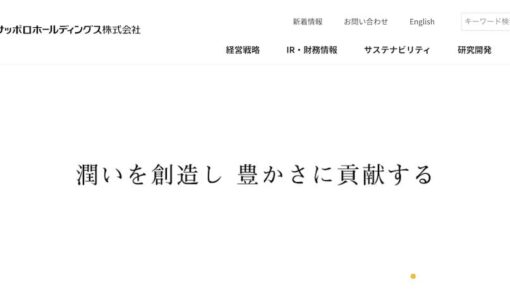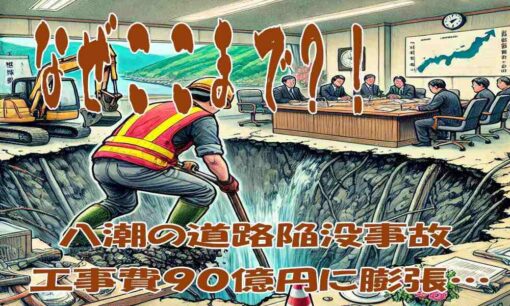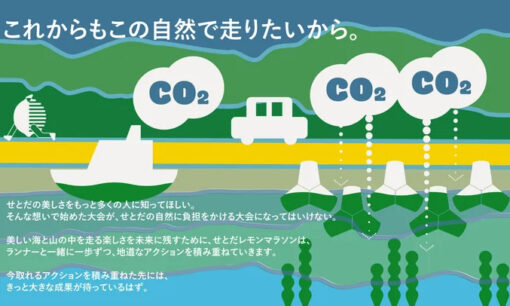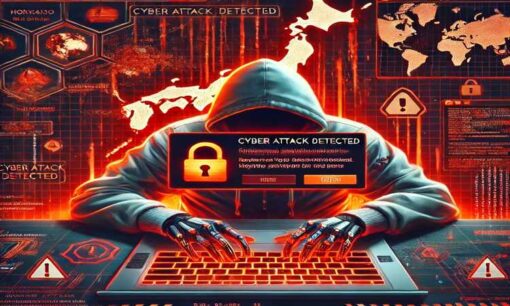対象:愛知・静岡・岐阜・三重・富山・石川・福井・新潟・長野・山梨
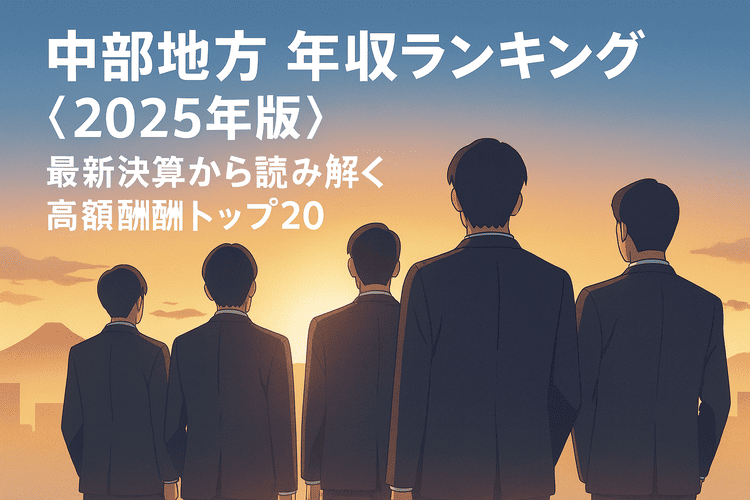
自動車産業を中心とした中部地方は、世界と直結した製造業の集積地だ。トヨタを筆頭に完成車から部品、素材、商社まで広がる産業クラスターが形成され、地域経済をけん引している。
本稿は決算短信・有価証券報告書など一次資料を突合し、2025年度に個人として1億円以上の報酬が開示された20人をランキング形式で紹介する。人物紹介を通じて、企業経営の現場を率いるトップの横顔に迫る。
20位 ブラザー工業(愛知)池田和史 1億円
人物紹介:1962年生まれ。神戸大学経済学部を卒業後、ブラザー工業に入社した。ドイツや米国の現地法人で経営トップを務め、欧米市場の販売戦略とマネジメントに深く携わった経験を持つ。経営企画や全社戦略を統括し、取締役副社長を経て現職に就いた。
プリンティング事業の収益基盤を再構築し、欧米市場でのシェア拡大を牽引。クラウド連携やセキュリティ機能を備えた新製品を投入し、法人向けソリューション事業の成長を加速させた。さらに、省エネルギー設計や資源循環対応など環境負荷低減を意識した製品開発を推進。
今後はIoTやAIを取り入れた次世代プリンティングソリューションを深化させ、オフィス、産業、家庭の多様なニーズに応える総合ソリューション企業としてブラザー工業を次の成長ステージへ導く役割が期待される。
19位 セイノーホールディングス(岐阜)田口義隆 1億300万円
人物紹介:1961年生まれ。獨協大学経済学部を卒業後、西濃運輸に入社した。米国子会社で経営を経験し、取締役総務部長、専務取締役、副社長を歴任。西濃運輸社長を経て持株会社体制への移行を主導し、グループ全体を統括する立場となった。
全国規模の幹線輸送網を再編し、共同配送ネットワークや積載効率向上策を導入。デジタル技術による運行管理やマッチングシステムの整備により、輸配送の効率化と環境負荷低減を両立させた。さらに、自動化設備や電動トラックを導入し、深刻化する労働力不足への対応にも力を入れる。地域経済団体の要職を務めるなど地元産業の振興にも積極的である。
今後はグローバルサプライチェーンの最適化と脱炭素戦略を加速し、物流業界全体の持続可能なモデルづくりを牽引する役割が期待される。
18位 リンナイ(愛知)内藤弘康 1億1,500万円
人物紹介:1955年生まれ。東京大学工学部を卒業後、日産自動車に入社。その後1983年にリンナイへ転じ、開発本部長や経営企画部長を歴任した。
製品開発と経営戦略の双方に携わった経験を生かし、2005年に社長に就任してからは、海外駐在経験を背景にグローバル展開を加速。給湯器や厨房機器を軸とした海外売上比率は3割を超え、主要市場でのシェア拡大を実現した。高効率ガス給湯器「エコジョーズ」やIoT対応の給湯・暖房機器を積極的に投入し、環境性能と利便性を兼ね備えた製品ラインを強化。近年は水素社会の到来を見据え、家庭用燃料電池「エネファーム」やゼロエミッション対応技術にも注力している。
今後はエネルギー転換と脱炭素の潮流に応じ、世界市場で持続的成長を遂げる牽引役として期待されている。
17位 マキタ(愛知)後藤宗利 1億2,400万円
人物紹介:1975年生まれ。慶應義塾大学理工学部を卒業後、マキタへ入社した。入社後は海外営業や企画部門を経て、2013年に取締役執行役員に就任。
グローバル事業を中心に販売網の整備を指揮し、主要市場でのシェア拡大に寄与してきた。社長としては、プロ向け電動工具の高付加価値化と、DIY市場への投入製品の多様化を両立させ、国内外の収益基盤を強化している。バッテリー技術を核とした製品開発にも注力し、園芸・清掃といった新カテゴリーへの展開を加速させていることが報じられる。さらに、各国の販売子会社との連携を深め、供給体制の安定化と需要変動への機動的対応を進める。
今後は、世界各地の市場ニーズに応じた製品戦略とデジタル販売チャネルの拡充を通じ、マキタをグローバル電動工具メーカーとして一段高い成長軌道へ導く役割が期待される。
16位 しずおかフィナンシャルグループ(静岡)柴田久 1億2,900万円
人物紹介:1956年生まれ。慶應義塾大学商学部を卒業後、静岡銀行に入行した。法人営業や経営企画を担当し、本店営業部課長や首都圏カンパニー長を歴任。
地域と首都圏の双方に通じる視野を持つ経営者として頭取を務め、持株会社制移行に伴い現職に就いた。現在は、静岡銀行と清水銀行を中核とするグループ経営を統括し、地域密着型金融の進化を目指している。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、モバイルバンキングやキャッシュレス決済の利用拡大で利便性を高めた。法人向けには事業承継や脱炭素支援のコンサルティング機能を整備し、地域企業の課題解決を後押ししている。
今後は、地域金融を超えたプラットフォーム型ビジネスの構築を進め、地元経済の持続的成長に貢献する役割が期待される。
15位 豊田自動織機(愛知)伊藤浩一 1億3,600万円
人物紹介:1963年生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、丸紅に入社し、海外事業や営業を経験した。その後、豊田自動織機に転じ、繊維機械事業の営業部門や経営企画を歴任。執行役員、常務役員、経営役員として主力事業の収益改善や新市場開拓に取り組んできた。
社長就任後は、フォークリフトやカーエアコン用コンプレッサーといった主力製品の競争力強化を進めるとともに、電動化・自動化分野への開発投資を拡大。CASEやカーボンニュートラルに対応した製品ポートフォリオを整備し、世界各地での生産体制の最適化を図っている。さらに、デジタル技術を活用した物流効率化や品質管理の高度化に注力し、持続的成長を目指す経営基盤を整えている。
今後は、グローバル市場でのシェア拡大と次世代モビリティ対応製品の開発を加速し、トヨタグループの中核企業として存在感を一層高めることが期待される。
14位 日本ガイシ(愛知)小林茂 1億4,000万円
人物紹介:1961年生まれ。慶應義塾大学法学部を卒業後、日本ガイシに入社。社内では海外営業を長く担い、電力事業本部やガイシ事業部長を歴任したとの経歴が伝わる。現在は経営全体を統括し、戦略会議や経営会議の議長を務めるとともに、サステナビリティやリスク管理といったガバナンス領域にもリーダーシップを発揮している。
技術系企業としての伝統を背景に、セラミックス事業のグローバル展開にも精力的に取り組む姿勢が注目され、最近では電気自動車(EV)向けの新製品開発に向けた情報も注目を集めている(聞き手に「GXは大きなチャンス」と語ったとされる)。統合報告書に示された中長期ビジョン「Road to 2050」では、ESG経営やカーボンニュートラルへの対応を経営の基軸に据え、新たな価値創造に取り組んでいることが明らかである。
今後は、強固な組織と技術力を礎に、EV向け素材やセラミックス技術の深化を通じた産業構造変革をリードし、「GX(グリーントランスフォーメーション)」を牽引する原動力としての役割が一層期待される。
13位 イビデン(岐阜)青木武志 1億5,600万円
人物紹介:1958年生まれ。関西大学工学部化学工学科を卒業後、イビデンに入社した。セラミック事業や電子事業の現場を経験し、製造部門と研究開発を横断的に統括。
取締役として電子事業本部を牽引し、プリント配線板と半導体パッケージ基板の増産体制を整えた。社長としては、世界的な半導体需要拡大に対応する設備投資を積極的に進め、国内外の生産拠点を増強。セラミック事業では、ディーゼル車用DPF(粒子状物質フィルター)の高性能化や環境規制対応製品を投入し、欧州や北米でシェアを確保している。ESG経営にも取り組み、カーボンニュートラルや資源循環に資する新技術の開発を加速。
今後は、次世代半導体パッケージ基板や水素関連部材など成長分野への投資を強化し、グローバル市場で競争力を高める牽引役としての役割が期待される。
12位 Niterra(旧日本特殊陶業)(愛知)川合尊 1億6,200万円
人物紹介:1962年生まれ。京都工芸繊維大学大学院を修了後、日本特殊陶業に入社し、セラミックスとセンサ技術を基盤にキャリアを積んだ。
社内ベンチャーとして立ち上がったセンサ事業を再建し、グローバル規模に育成した経験は、経営者としての原点とされる。社長就任後は、社名を日本特殊陶業からNiterraへ改め、脱エンジン依存を見据えた事業ポートフォリオを構築。次世代車載、医療、環境、エネルギーといった多様な分野を成長軸に据えた。統合報告書によれば、全事業とグローバル戦略、内部監査、ウェルビーイングを横断管掌し、現場と本社を結ぶ統治を強化している。
今後は、セラミックス応用領域と高機能センサを軸に、カーボンニュートラル社会に貢献する企業像を示すことが期待されている。
11位 セーレン(福井)川田達男 1億6,300万円
人物紹介:1940年生まれ。明治大学経営学部を卒業後、セーレンに入社。
若くして経営トップを任され、経営不振にあえいでいた同社の再建に取り組み、収益構造を立て直した。事業ポートフォリオを見直し、合成繊維から高機能素材へと重点を移し、自動車内装材や医療分野へ展開。さらに、自社開発のデジタル染色技術「ビスコテックス」を実用化し、環境負荷の低い生産方式を確立した。繊維業界の再編期には経営破綻したカネボウの繊維事業を買収し、再建を成功させたことでも知られる。現在は海外生産拠点の再編とグローバル販売網の拡充を進め、収益基盤を安定させている。旭日中綬章を受章するなど長年の功績は高く評価されている。
今後はカーボンニュートラルやサーキュラーエコノミー対応の素材開発を通じ、持続可能な産業モデルを牽引する役割が期待される。
10位 バローホールディングス(岐阜)田代正美 1億7,800万円
人物紹介:1947年生まれ。早稲田大学法学部を卒業後にバローへ入社した。店舗運営や商品部門を経て経営企画に携わり、現場と戦略の双方に精通した経営者として知られる。
社長就任後は食品スーパー事業を軸に事業領域を拡大し、物流網の再編や情報システムの刷新を進め、グループ全体の効率化と競争力強化を実現した。さらにドラッグストア、ホームセンター、スポーツクラブなど多業態を展開し、事業シナジーを創出して収益基盤を安定させた。持株会社体制への移行後は、グループ横断での商品開発や人材育成を推進し、地域社会と共生する企業像を明確にしている。近年はデジタルマーケティングやEC事業の拡充にも注力し、リアル店舗とオンラインを連動させた新しい購買体験を提供。
今後はデータ活用と人材戦略を通じて持続可能な流通モデルを構築し、地方都市における生活インフラとしての役割をさらに高めることが期待される。
9位 ファナック(山梨)山口賢治 1億8,200万円
人物紹介:1959年生まれ。東京大学大学院を卒業後にファナックへ入社。ロボット開発の現場からキャリアを積んだ。製造現場と研究開発を熟知する経営者として、FA、産業用ロボット、ロボマシンの三本柱を統合する「One FANUC」戦略を推進する。
自社開発のIoTプラットフォーム「FIELD system」を軸に、工場の視える化や自律運転化を進め、生産現場の効率化と安定供給の両立を図った。協働ロボットの導入や部品生産の集約にも取り組み、グローバル需要に応える生産体制を整備している。さらに「商品に誇りを持てる社員でなければよいものは作れない」と語り、現場力と人材育成を重視する姿勢を貫く。
今後は、国内外の拠点を活用して次世代FAとロボットの融合を深化させ、世界のものづくりを変革する原動力となることが期待されている。
8位 ヤマハ発動機(静岡)日高祥博 1億9,000万円
人物紹介:1963年生まれ。名古屋大学法学部卒業後にヤマハ発動機へ入社。二輪事業や企画・財務をはじめ幅広い業務を経験して指導力を養った。経営トップとしては、二輪車事業の立て直しと電動モビリティへの戦略的な移行に注力し、特にロボティクス事業の強化を通じて新たな収益の柱を育成した。しかし、社長を退任し現在は役員職などに就いていない(※最新人事により)。
日髙氏の経営スタイルは、従来のモーターサイクル中心から多彩なモビリティ領域へとビジネスを広げるスピリットにあふれていた。今後は、その精神と知見を活かし、新体制下でヤマハ発動機が電動化、ロボティクス、コネクテッド技術などの次世代領域でさらなる革新を生み出す原動力として存在感を発揮することが期待されている。
7位 オーエスジー(愛知)大沢伸朗 1億9,200万円
人物紹介:1968年生まれ。早稲田大学理工学部材料工学科を卒業後、オーエスジー販売(現オーエスジー)へ入社。欧州を中心に国際経験を積み、英国法人や欧州統括会社の代表取締役を歴任。南アジア統括や営業本部を担い、グローバル販売網の再構築と市場深耕を主導してきた。
社長就任後は、精密切削工具メーカーとしての技術優位を生かし、航空機やEV、半導体分野に対応した高付加価値工具の開発と供給体制強化を推進。欧州を含む主要市場で生産能力を増強し、海外売上比率を高水準に保っている。さらに、デジタル技術を活用したソリューション提案を展開し、顧客工場の生産性向上に貢献。
今後は、次世代モビリティや再生可能エネルギー分野の需要を取り込み、世界の切削工具市場で存在感をさらに高めることが期待される。
6位 アイシン(愛知)吉田守孝 2億4,100万円
人物紹介:1957年生まれ。名古屋大学工学部を卒業後、トヨタ自動車に入社。車両開発部門でキャリアを積み、常務役員・専務役員・副社長などを歴任した。豊田中央研究所会長として研究開発体制を統括した経験も持つ。
2021年6月、社長に就任し、同社が得意とするAT(自動変速機)事業を基盤に電動ユニットやeAxleの開発を加速。パワートレイン事業を統合し、モジュール戦略で原価低減と収益性向上を実現した。吉田氏は「環境対応と収益力強化の両立」を掲げ、CASE時代に対応した製品ポートフォリオの再構築を推進している。
今後は電動化、ソフトウェア連携、次世代モビリティへの投資を通じて、アイシンをグローバルサプライヤーとしてさらに進化させる役割が期待されている。
5位 ミネベアミツミ(長野)貝沼由久 2億4,778万円
人物紹介:1956年生まれ。慶應義塾高等学校から慶應義塾大学法学部法律学科へ進み、在学中にはハワイ州プナホウ・スクールに留学した経験を持つ。司法試験に合格後、ハーバード大学ロースクールでLL.M.を修了し、ニューヨーク州弁護士資格を取得。ニューヨークで弁護士として勤務した後、ミネベア(現ミネベアミツミ)に入社した。
国際法務や経営企画を経て経営トップとなり、積極的なM&Aで事業を多角化。ベアリングを中心とする精密部品事業を拡張し、モーター、センサー、半導体部品など幅広い分野を統合した。海外生産拠点の整備やグローバルサプライチェーン構築により海外売上比率を大幅に高め、世界市場での存在感を確立。現在はスマートシティ、EV、医療機器など新規市場への進出を加速している。
今後もグローバル経営の手腕と法務の知見を生かし、精密技術を核とした持続的成長をリードする役割が期待される。
4位 デンソー(愛知)有馬浩二 2億5,400万円
人物紹介:1958年生まれ。京都大学工学部を卒業後、日本電装(現デンソー)へ入社し、生産技術の現場でキャリアをスタートさせた。1989年にはデンソー・マニュファクチュアリング・テネシーへの出向で現地生産の立ち上げを牽引し、SCオルタネータの開発と量産体制を確立する革新的技術を主導した(世界初となる加工技術)。デンソー・イタリアの社長として事業の再建を成功させた後、常務、専務を経て取締役社長に就任。2023年には代表取締役会長へと昇格した。
有馬氏は「人づくり経営」を信条に掲げ、生産現場への足を絶やさないリーダーとして知られている。今後は会長として、デンソーが電動化・ソフトウェア・CASE分野における次世代技術を深化させ、グローバルモビリティの革新リーダーとしてさらなる飛躍を遂げる牽引役を果たすことが期待されている。
3位 豊田通商(愛知)貸谷伊知郎 2億8,900万円
人物紹介:1959年生まれ。同志社大学経済学部を卒業後に豊田通商へ入社。海外駐在や自動車企画部門を経て経営企画を統括した経験を持つ。取締役や専務執行役員を経て社長CEOとしてグループ全体を率い、収益基盤の多様化と事業ポートフォリオの再構築を進めた。
豊田通商は世界130カ国超にネットワークを持ち、資源、モビリティ、デジタルソリューションなど幅広い事業を展開する総合商社である。貸谷氏は現場感覚を持つ戦略家として、新興国市場の開拓や自動車サプライチェーンの最適化を推進し、グローバル成長を牽引した。副会長となった現在も、脱炭素社会に向けた再エネ・水素関連事業、デジタル分野の新ビジネス開発を指導。
今後は、国内外での協業や投資を通じて次世代モビリティと資源循環型社会を支える新たな成長エンジンを生み出す役割が期待される。
2位 スズキ(静岡)鈴木俊宏 2億9,300万円
人物紹介:1959年生まれ、東京理科大学大学院理工学研究科を修了後、日本電装(現デンソー)を経てスズキに入社した。米国ゼネラルモーターズへの駐在や商品企画部門での経験を重ね、開発と海外戦略の双方を熟知する経営者へと成長した。
取締役、専務、副社長を経て現職となり、四輪・二輪事業のグローバル展開を統括している。特にインド市場を成長の中核と位置づけ、現地生産能力の増強とEV生産体制整備に積極投資。輸出拠点化も進め、インド工場を世界最大級の生産拠点へ育てる計画を描いている。欧州や日本国内でも電動化やコネクテッド技術の導入を推進し、環境規制に適合した新モデルを投入。
今後は多様な市場のニーズに対応した製品開発とコスト競争力を武器に、次世代モビリティ時代におけるスズキの存在感をさらに押し上げる役割が期待される。
1位 トヨタ自動車(愛知)佐藤恒治 8億2,600万円
人物紹介: 1969年生まれ。早稲田大学理工学部を卒業後にトヨタ自動車入社。技術畑でキャリアを重ねた。
初代プリウスや北米カムリのサスペンション設計に携わり、レクサスブランドではGSやLCの開発主査として新プラットフォームを導入。プレミアムブランド戦略とモータースポーツの融合にも関わり、ブランド価値を高める取り組みを牽引した。経営層ではチーフ・ブランディング・オフィサーとして全社ブランド戦略を統括し、レクサス・インターナショナルやGAZOO Racing Companyのトップも務めた。社長就任後は「モビリティカンパニー」への変革を旗印に、EV、燃料電池、水素、ソフトウェア開発を柱とした新戦略を展開。グローバルでの生産・開発体制を刷新し、多様な地域ニーズに応える商品群を整備している。
今後はカーボンニュートラルやソフトウェア定義車(SDV)など次世代技術を核に、世界の移動体験を変革するリーダーとしての役割が期待される。
総評
今回のランキングは、トヨタ自動車を筆頭に、トヨタグループ各社、精密機器メーカー、地場金融、流通大手が顔をそろえる結果となった。
自動車産業の強さが際立つ一方で、ミネベアミツミやファナックといった精密・FAメーカーが上位に入り、産業構造の多様性も確認できる。経営者はいずれもグローバル市場での事業拡大や次世代技術への投資をリードする存在であり、その報酬水準は地域経済の国際競争力を象徴している。
今後はEV・ソフトウェア・再生可能エネルギー・サプライチェーン再編が経営課題の中心となり、報酬体系にも変化が現れるだろう。持続可能性と収益性を両立するトップの意思決定が、中部地方の未来を形づくる鍵となる。