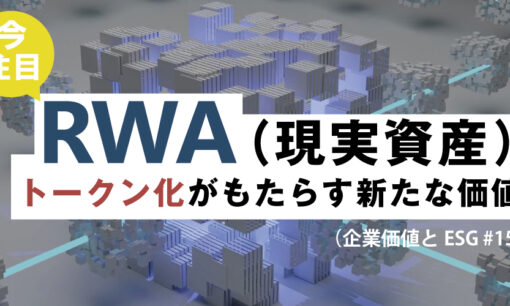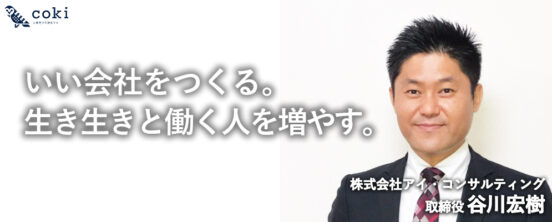2024年7月12日、北海道福島町。
新聞配達員の佐藤研樹さん(52)が、配達中にヒグマに襲われ、命を落とした。
その直後、町内でクマ1頭が駆除されると、今度は「クマを殺すな」と抗議の電話が役場に殺到する事態となった。命が失われた現場で、いったい何が起きていたのか。
「ナイフを持って行った方がいいかな」恐怖と責任のはざまで
佐藤さんは事件の数日前から、配達中に何度もクマを目撃していたという。
「また見かけた」「クマに見られてる気がする」
知人たちはそう語る。前日には母親にこう漏らしていた。
「ナイフを持って行った方がいいかな……」
それでも、新聞配達をやめることはなかった。
佐藤さんをよく知る商店主はこう振り返る。
「怖かったと思います。でもあの人は、途中で仕事を投げ出すような人じゃない」
その言葉の通り、佐藤さんは配達ルートを変えず、恐怖の中を走り続けていた。
駆除されたのは“別の個体”。繰り返される襲撃と、見逃された過去
事件の6日後、7月18日午前3時半。住宅街近くの藪にいたヒグマがハンターによって駆除された。
体長208cm、体重218kgの大きな個体だったが、DNA鑑定の結果、佐藤さんを襲ったクマとは別のものと見られている。
しかも、佐藤さんを襲ったクマは4年前にも77歳の女性を襲って死亡させていた個体だったことが判明した。
なぜ、そのとき駆除されなかったのか。
なぜ、再び命が奪われるまで見過ごされたのか。
町民の間には、やり場のない憤りと喪失感が残っている。
抗議電話が突きつけた「共生」という矛盾
駆除のニュースが報じられるやいなや、福島町役場には抗議の電話が相次いだ。
「クマを殺すな」「クマの土地に人間が住んでるんだろう」
電話の多くは、町外、さらには道外からだった。
役場の職員は語る。
「“お前も死ね”というような過激な言葉もありました。私たちは町民の安全のために動いているのに、非難ばかりが届くのはつらいです」
2023年、秋田県美郷町でも似た事例があった。
畳店にクマの親子が侵入し駆除された際、県外から抗議が殺到し、知事が「業務妨害」とまで言及した。
共生という言葉が、美しい理想だけを残し、現場の命や決断を責めるために使われていないか。いま改めて問われている。
ヒグマが人を襲う理由。生態と変化
ヒグマが人を襲うのは、決して狂暴だからではない。
主な要因には次のようなものがある。
- 子連れやエサ場を守る防衛本能
- 生ゴミや畑の野菜など、人の生活にひもづく食べ物への執着
- 一度人を襲って成功体験を得たクマが学習して行動を繰り返す
- 鹿の死体などを食べることで進む肉食化の傾向
特に今回のように、明け方や深夜の時間帯はクマの活動が活発で、新聞配達など静かな時間帯の生活者がターゲットになりやすい。
命を支えた日常と、残された空白
佐藤さんは母親と2人暮らし。毎朝4時前には家を出て、町中を無言で走り、新聞を届けていた。
「配達の音が聞こえると、なんとなく安心した」と語る近隣住民も多い。
玄関には、新聞を入れていたバッグが今もそっと置かれている。
その中に、誰にも知られず背負っていた恐怖と責任の重みが残されているようだった。
これからの問い。誰の命を、どう守るのか
命を落とした佐藤さん。
殺されたヒグマ。
その後に届いた非難の声。
自然と共に生きる社会とは何か。
私たちは誰の命を守るのか。
「殺すな」という言葉の先に、本当に「守られるべきもの」があるのか。
その問いを、安易な答えで閉じることなく、静かに考え続けたい。