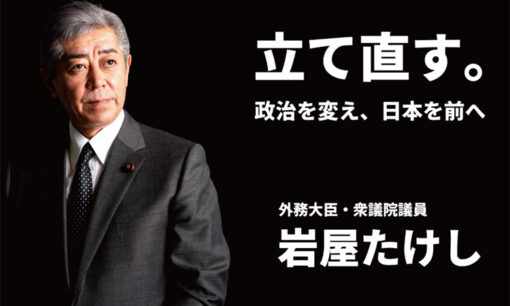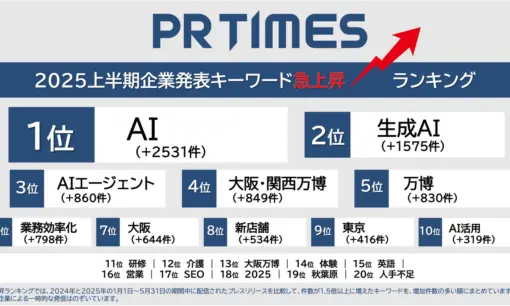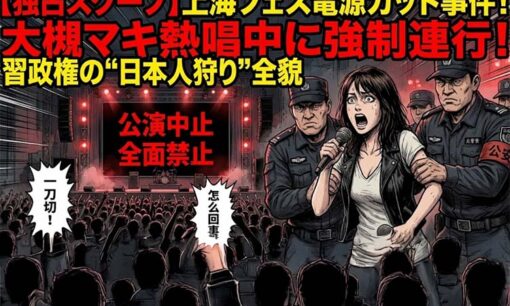「昼ごはんくらい、ちゃんと食べたい」
そんな当たり前の欲求が、物価高の波の中で揺らいでいる。
かつては500円台で選べた定食が800円を超え、ワンコインランチは姿を消しつつある。
企業の社員食堂がない職場では、毎日のランチ代は無視できない固定コストとなり、選択肢は徐々に「満足」よりも「妥協」へとシフトしている。
値上げラッシュの中で、“選ぶ”行為は試される
総務省の『家計調査』(2023年)によれば、単身勤労世帯の昼食費は平均約650円。
だが都市部で外食をする場合、800円以上を想定しなければ選択肢は限られる。
物価上昇のペースは、日替わり定食よりも速いのだ。
コンビニのパスタにサラダをつけると700円を超える。
牛丼チェーンも、以前の価格帯では収まらない。
一方で「冷凍食品+レンジ」「自作弁当+前夜の残り」など、工夫を凝らす人も増えている。
満腹感か、栄養か、スピードか。
そのすべてを叶えようとすると、コストが跳ね上がる。
どこを切り捨てるかが“個人の判断”として押し戻されている現状がある。
昼ごはんが「自己責任化」している
「お金をかけないなら、自分でつくればいい」
「時間がないなら、プロテインバーでも十分だ」
そんな言葉が、SNSにも、職場の会話にもあふれている。
だがその背後には、“食べることの価値を軽く見積もる空気”が漂っている。
本来、昼食は単なるエネルギー補給ではない。
午前と午後をつなぐ回復の時間であり、自律神経や血糖を整える行為でもある。
それをおろそかにすることは、集中力やメンタル、長期的には健康リスクにもつながる。
企業は昼ごはんから働き方を見直せるか
にもかかわらず、食事にコストをかけることが「甘え」や「意識高い系」と揶揄される場面さえある。
“ちゃんと食べたい”という欲求が、贅沢や怠慢として処理されかねない空気がある。
一部の企業では、こうした状況を改善しようという試みも始まっている。
たとえば、サブスクリプション型の弁当支援サービス「オフィスおかん」や「green」では、社内に冷蔵型の惣菜ステーションを設置し、1品100〜200円で手軽に食べられるようにしている。
導入企業の中には、昼食補助を“食べる権利への投資”と位置付けるところも出てきた。
一方、古くから社員食堂を持つ企業の中には、原材料費が上がっても価格を据え置いているケースもある。
コストを企業側が一部負担することで、「きちんと食べること」の選択肢を守っている。
しかしそれは、全体から見ればまだ例外だ。
多くの職場では、「昼ごはんは個人でどうにかするもの」として、見過ごされ続けている。
食べることは、“働くこと”の一部である
昼食の選択は、企業の制度や社会の設計とは無関係に見える。
だが実際には、その積み重ねが働く人のコンディションに影響を与え、パフォーマンスや離職率、満足度にまで波及していく。
たとえば、15分でパンをかじって終わる昼休みと、30分座って食べる定食の間には、“生産性の差”では測れないものがある。
それは、働く人の尊厳や安心につながる感覚だ。
物価高は止められない。だがその中で、「きちんと食べること」が贅沢扱いされていく社会は、本当に健全だろうか。
企業も、自治体も、働く人自身も。
“ちゃんと食べる”という行為を守るために、見直すべきものは少なくない。