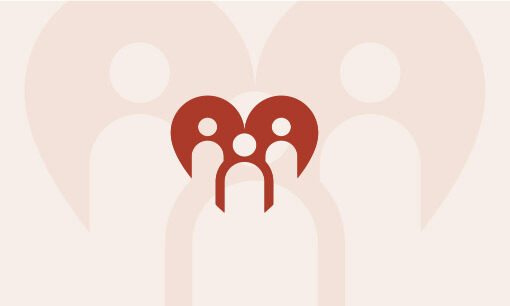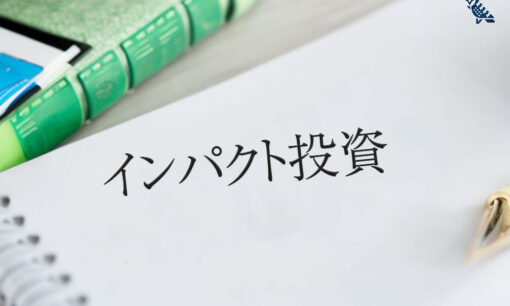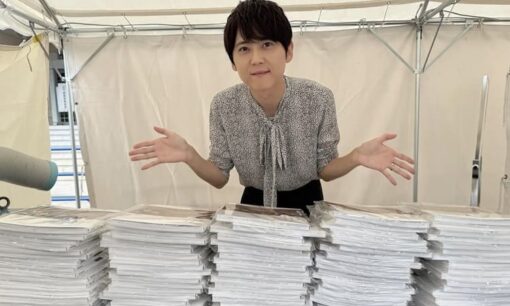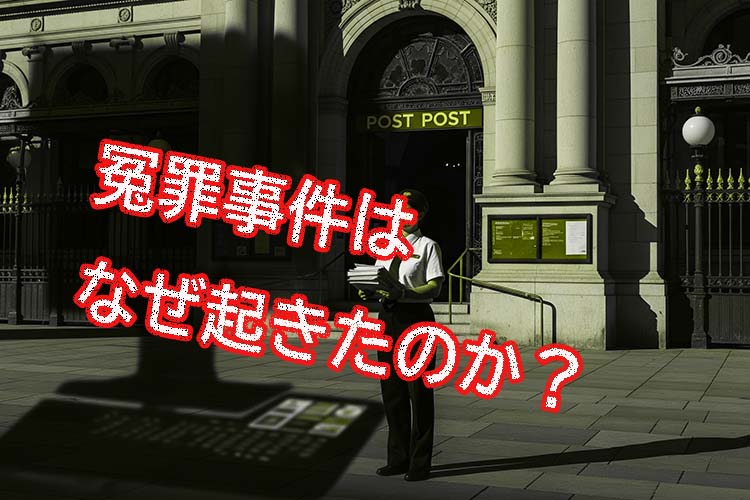
1999年、英国で始まったはずの“郵便局改革”は、気がつけば何百人もの人生を破壊し、13人以上の命を奪う未曾有の冤罪事件に姿を変えていた。しかもその背後には、我が国・日本を代表する大企業の名が浮かび上がっている。
事件の名は「Post Office Horizon scandal(郵便局事件)」──英国史上最悪の司法ミスとして歴史に刻まれたこの事件は、今や“英国内版・東電福島原発事件”とも呼ばれ、その波紋は司法界、政治、そして日本企業のガバナンスにまで及ぼうとしている。
英国でいま、歴史の針が巻き戻されている。1999年、国営から民営化の途上にあった英国の郵便局(Post Office)は、日本企業・富士通傘下の英国法人が提供する新型会計システム「Horizon」を導入した。全国規模で展開されたこのIT改革は、システム不具合による“会計エラー”を、局長個人の不正と誤認させる構造をはらんでいた。
結果、Horizonの記録を「唯一の証拠」として用いた司法が、全国で約952人を起訴。236人が実刑を受け、少なくとも13人が命を絶った。いまや英国史上最大の冤罪事件「Post Office scandal」として、国を挙げた補償と責任追及が始まっている。
しかも、その背後には、日本を代表するIT企業・富士通がM&Aを通じて手に入れた巨大システムがあった。
郵便局長を犯罪者に変えた「国策×IT」の罠
1990年代末、英国政府は郵便局改革の一環として、全国2万拠点以上に「Horizon」システムを導入。設計元は、英国の老舗IT企業ICL──1998年、富士通が完全買収し、2002年に富士通ブランドに統合された。
当初の想定では、Horizonは売上・預金・送金を統合管理することで、局長の業務を効率化する“夢の会計システム”だった。だが導入直後から、不自然な残高差異が頻発。数十ポンドから数千ポンドの差額が日常的に発生した。
これに対し、Post Office本部は「局長の横領」と判断し、自費補填を命令。補填不能な者は即刻刑事告発され、裁判ではHorizonのログが「唯一かつ決定的な証拠」とされた。
「自分は何も盗っていない」──そう叫ぶ局長たちの声は、法廷では一切斟酌されなかった。
Horizonという“ブラックボックス”技術が暴走した瞬間
HorizonはPOS端末とバックエンドサーバーが連動する閉鎖的なシステムで、外部検証が困難だった。BBCやThe Guardianの報道によれば、導入後すぐに富士通UK内部では1万件以上のエラーレポートが蓄積されていたにもかかわらず、その情報は裁判所にも被告にも一切共有されなかった。
さらに富士通は、システムに対してリモートでアクセスし、数値の書き換えが可能な“裏口”機能を保有していた。被告が否認する差額が、裏で書き換えられていた可能性も否定できない。
にもかかわらず、Post Officeと富士通は「Horizonに問題はない」と繰り返し主張し、英国議会に対しても「エラーはすべて操作ミス」と報告していた。
買収とデューデリジェンス富士通の“責任範囲”とは
問題の根は、富士通が1998年に買収したICLにある。ICLはHorizonを設計・提供していた企業であり、当時すでに不具合と官民癒着が指摘されていた。そのリスクをどう評価し、どこまで修正可能と判断してM&Aを成立させたのか。
ICLは買収当初、英国政府とHorizonプロジェクトの独占契約を締結しており、富士通はこれを「欧州展開の足掛かり」と捉えた。だが、瑕疵担保や法的責任については買収契約に明示されていなかった疑いもある。
さらに、富士通UKは2005年以降もPost Officeと数度にわたり契約を更新。Horizonの保守・運用業務で報酬を得続けており、技術的な欠陥の修正も進まないまま、冤罪だけが拡大していった。
英国のメディアでは「これはITの失敗輸出であり、富士通にとっては最悪の買い物だった」と指摘されている。
自殺、破産、離婚 IT冤罪”が奪った生活
被害者の多くは地域で信頼されていた局長や主婦だった。報告書によれば、少なくとも13人がHorizon事件を苦に自殺。数百人が精神疾患や経済的困窮、家庭崩壊を経験した。
ある女性局長は、わずか数百ポンドの差額を補填できず起訴され、解雇。冤罪により信用を失い、周囲の視線に耐えかねて命を絶った。
また別の男性は、有罪判決を受けて収監されたのちに釈放されたが、家族との関係は壊れ、社会復帰もままならずホームレス状態にまで転落した。
補償は進んでいるが道半ばだ。2025年6月時点で約7,900人に総額10億9,800万ポンド(約2,180億円)が支払われたが、補償対象者は約1万人。制度の煩雑さや申請期限の問題で、遺族への補償が行き届かないケースも多い。
富士通の責任は 無謬神話”の終わり
英国議会の調査委員会(ウィリアムズ・レビュー)は、富士通のHorizon運用と証拠隠蔽についても調査対象とし、メトロポリタン警察も現在、関係者を詐欺・偽証の容疑で捜査中である。
2024年には、富士通UKがPost Officeと「証拠ログのアーカイブ形式を変更」し、改ざん可能な状態にしていたとの内部告発も報じられている。
Post Office元CEOパウラ・ヴェネルズは現在、議会喚問を受けており、Horizonに関する“過失か故意か”の真相が問われている。
一方、富士通は「現時点では被害者に対する賠償義務はない」との立場を取っているが、すでに民事訴訟が複数進行中で、今後数十億円単位の損害賠償請求に発展する可能性が高い。
これは日本の問題でもある
富士通にとって、今回の事件は「M&Aの失敗」という教訓にとどまらない。司法の場で“技術が神になった”とき、企業はその責任から逃れられない。
ましてやそれが公共インフラであれば、その代償は国際的信用の喪失に直結する。
2025年秋以降、英国の大型公共案件において富士通が排除される動きもあり、銀行融資の制限やブランド価値の毀損はすでに表面化しつつある。
日本企業のM&A、IT監査、公共調達のあり方を問う警鐘として、この事件は“他人事”ではない。