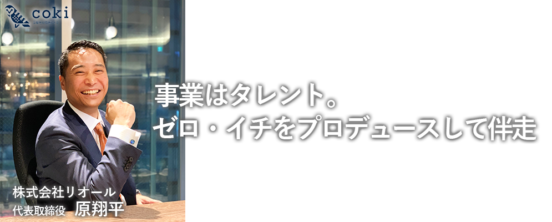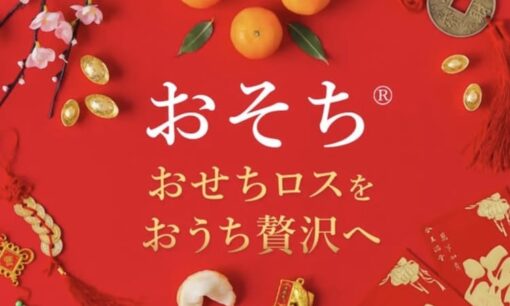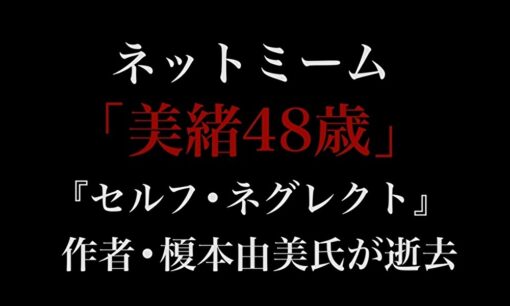大阪・関西万博で導入された「オールジェンダートイレ」が注目を集めている。性別を問わず利用できるこの新しい空間は、共生社会への一歩となるのか。それとも過性の試みに終わるのか。今、私たちに問われている。
万博に導入された「性別を分けないトイレ」
2025年の大阪・関西万博では、会場の一部で性別を問わず誰でも使える「オールジェンダートイレ」が導入されている。個室トイレの約1割にあたるスペースがこの形で整備され、LGBTQへの配慮や女性トイレの混雑緩和を目的としている。
トイレの設計は一方通行型で、通路の両側に個室が並び、共用の手洗い場やサニタリーボックスも設置。建築的にも心理的にも「誰でも使える」空間を目指した設計だ。
ただし、利用者の間では好意的な声と戸惑いが交錯しており、この取り組みが社会に定着するかどうかはまだ未知数だ。万博のような大規模イベントでの導入は、公共施設での普及に向けた試金石といえるだろう。
なぜ今、オールジェンダートイレなのか
オールジェンダートイレの導入が進んでいる背景には、いくつかの社会的な変化がある。まず、性の多様性に対する認識が広がったことが大きい。性自認が男性でも外見が女性的であったり、その逆であったりする人にとって、従来の男女別トイレでは不安や緊張を伴うケースがある。
また、共用トイレはトランスジェンダーやノンバイナリーといったLGBTQ当事者だけでなく、子連れの保護者や高齢者介助にも有効とされる。性別によらず付き添える空間としての利便性が評価されているのだ。
さらに、イベント会場や商業施設で起きがちな「女性トイレの行列」という構造的問題の解消にも寄与するとされ、都市設計の観点からも注目されている。
受け入れを阻む“心理的ハードル”
一方で、制度や設計が整ったとしても、すべての人が安心して利用できるわけではない。見知らぬ異性と同じ空間を共有することに抵抗を感じる人も少なくない。特にプライバシーや安全性に敏感な利用者にとっては、「安心感」が欠けると感じられる可能性がある。
こうした“心理的ハードル”をどう乗り越えるかが、社会実装に向けた重要な課題である。ハードウェアとしての整備と同時に、利用者への丁寧な説明や理解促進の仕組みも必要となるだろう。
海外や国内の事例に学ぶ
海外ではすでに多くの都市でオールジェンダートイレの導入が進んでいる。米国の一部大学や公共施設では、当たり前のように共用トイレが設置されており、大きな混乱も報告されていない。
一方、日本では2023年に東京都新宿区・歌舞伎町に設置された共用トイレが、防犯面の懸念からわずか1年で撤去されるという事例もあった。空間設計や運用ルールの工夫がなければ、社会からの信頼を得るのは難しいという現実を物語っているといえる。
誰もが「使いたい」と思える設計へ
オールジェンダートイレの本質は、「誰でも使える」ことだけではなく、「誰もが安心して使える」ことにある。そのためには、設備や導線の工夫だけでなく、社会全体が多様な価値観を尊重し合う文化を育てていく必要がある。
今回の万博のように、実際に使ってみてどう感じるかという「体験」は、社会の理解を深めるうえで極めて重要だ。特定の立場の人だけでなく、多様な利用者の声をすくい取りながら設計と運用を改善していくことが求められている。
トイレは社会の鏡である
公共トイレは単なる生活インフラではなく、社会の価値観や構造を映す“鏡”でもある。男女別という前提が揺らぎはじめた今、私たちはどのような空間を「当たり前」として選んでいくのか。
オールジェンダートイレの導入をめぐる議論は、インクルーシブな社会に向けた対話の始まりにすぎない。大阪・関西万博の現場で生まれる小さな違和感や納得の積み重ねが、未来の公共空間のかたちをつくっていく。