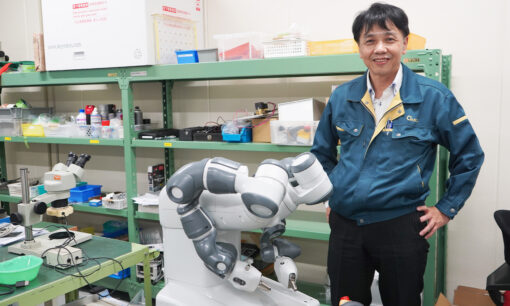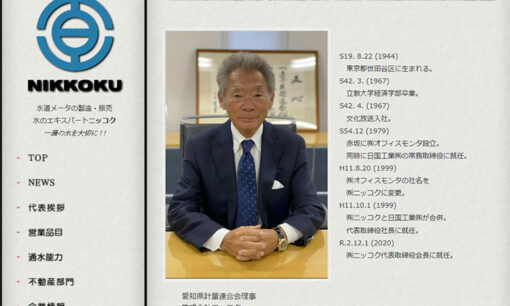「富士登山は3回目なんだ」。そう話していたというアメリカ人男性(67)は、2025年7月、富士山の静岡県側・富士宮口新七合目付近で体調不良を訴え、救助された。足元はサンダル。山開き前の入山、テント泊、単独行。さまざまなリスクが重なっていた。
登山者の「自由」と「自然への挑戦」は、富士山に限らず登山文化の根底にある。しかしいま、富士山では新たな価値観が求められている。2025年、富士山は“誰でも登れる山ではなくなった。それは、安全と環境、そして責任の再構築でもある。
サンダル姿での救助…見過ごせない装備と情報のギャップ
この男性は、6月下旬から富士山に入山し、山小屋がまだ営業していない新七合目付近で数日間を過ごしていた。7月4日、体調不良を訴えて他の登山者に助けを求め、119番通報を経て山小屋関係者が重機で五合目まで搬送。その後、救急搬送された。
警察によれば、男性は防寒着を着ていたが、サンダルを履いており、低体温症の症状が出ていたという。登山経験はあると自称していたが、気温5℃以下にもなる高地での装備としては致命的だ。
こうした“軽装”登山は、過去にも問題視されてきた。経験や国籍にかかわらず、「山の常識」が共有されていない状況が、命を危険にさらす大きな要因となっている。
外国人登山者の増加と情報の届かなさ
観光庁によると、近年は訪日外国人の増加にともない、富士山登山に挑戦する外国人が急増している。しかし、登山ルートの選び方、必要な装備、登山届の提出といった基本情報が十分に伝わっていないケースも多い。
案内板やウェブサイトは整備されつつあるものの、多言語での情報発信や文化背景の違いへの配慮は道半ばだ。今回のように「登山の危険性」が十分に理解されないまま入山し、救助に至るケースは今後も起こりうる。
加えて、外国人登山者の中には、山開きの時期や夜間登山のリスクについての認識が乏しい例も多く、登山者と受け入れ側の“情報の断絶”が事故を招いている。
救助費用は誰が払うのか?
今回の救助には、山小屋関係者の重機、消防、警察が出動している。こうした費用は原則として公費でまかなわれる場合が多いが、自治体によっては遭難者に費用を請求する制度もある。
しかし、外国人観光客の場合、制度周知が行き届いていないことや、支払い回収の現実的な困難さから、費用請求ができないこともある。登山保険の加入も任意で、加入率は依然として低い。
登山者の「自己責任」を前提としながらも、実際には“社会全体で支えるリスク”となっているのが現状だ。
富士山は「管理される山」へ。新制度が始まった
こうした問題に対応するため、2025年から富士山の入山制度が大きく変わった。
- 入山料:全ルート一律4,000円(従来の任意協力金から強制へ)
- 入山時間制限:14時〜翌3時は山小屋宿泊者以外の入山禁止
- 事前登録義務:アプリでのQRコード取得+eラーニング受講必須
- 人数制限:吉田ルートは1日4,000人に制限(山梨県側)
これにより、登山者は事前に富士登山に関する知識と心構えを学び、入山時間や装備、計画の管理が求められるようになった。
もはや「思いつきで」「軽装で」「夜中に登る」といった行動は許されない。“誰でも”という自由の裏側にあった安全リスクを抑えるための制度的変革だ。
富士山に問われるのは、自由ではなく責任
サンダル姿の登山者が救助された出来事は、象徴的な“警告”だったとも言える。富士山は美しく、神聖で、そして厳しい自然のまっただ中にある。観光地化が進む一方で、登山とは本来、リスクと向き合う営みである。
富士山が“誰でも登れる山”だった時代は終わった。これからは、誰もが「登る覚悟」を持たなければならない山になる。新制度はその第一歩だ。
安全、環境、観光、そして社会的コスト。すべてのバランスを取るには、「自由」の再定義が必要だ。