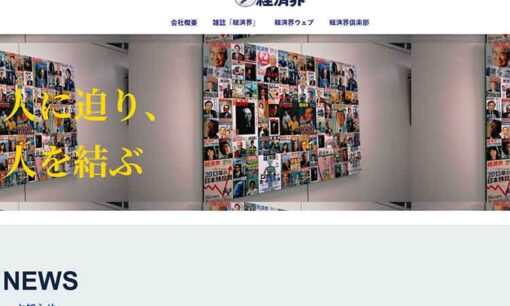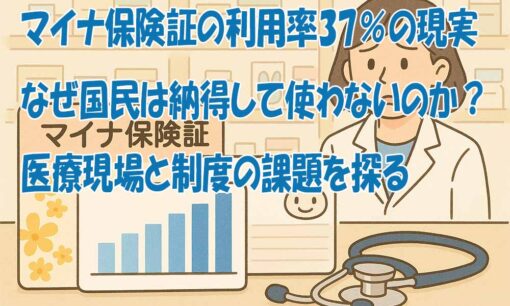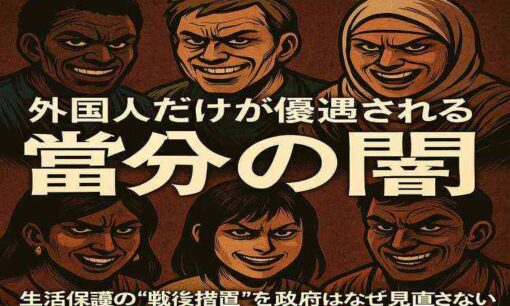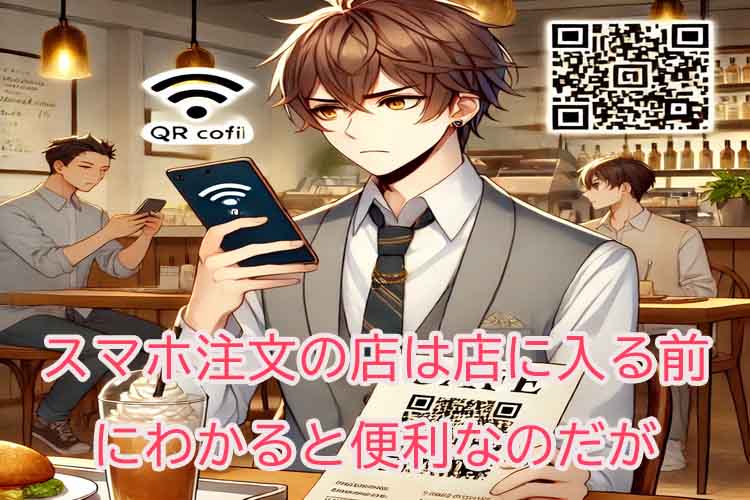
コロナ禍以降、飲食店での注文方法が大きく変わった。従来の紙メニューや口頭注文に代わり、QRコードを用いたスマホ注文が急速に普及している。人手不足の解消や業務効率の向上など、飲食店側にとっては大きなメリットがあるが、客側からは不満の声も少なくない。
スマホ注文の普及が止まらない!導入店舗が急増する理由とは?
リクルートの調査によれば、セルフオーダーの利用経験率は2021年の26.0%から2024年には57.1%に急増している。導入店舗は今後も増えていくことが予測されるようんだ。
スマホ注文の導入は、飲食店の経営効率化に寄与している。注文の手間が省かれることでスタッフの負担が軽減され、定着率の向上にもつながるという。さらに、注文データが可視化されることで、売れ筋メニューの把握が容易になり、食品ロスの削減にも貢献している。インバウンド対応の面でも、ブラウザの自動翻訳機能を活用すれば多言語での注文が可能となり、外国人観光客への利便性も向上する。
「俺のギガにタダ乗り」 スマホ注文に不満を感じる利用者たち
東京都内に住む会社員の男性(23)は「俺のギガにタダ乗りしやがって」とSNSに投稿した。飲食店でQRコードを渡され、スマホのカメラで読み取るとメニューが表示され、そのまま注文できるシステムが増えている。しかし、この方式には自分の通信料を使う必要があり、長時間の滞在ではバッテリー消費の問題も生じる。
こうした不満はSNS上でも度々議論の的となっている。「なぜ客が通信費を負担しなければならないのか」という声は根強く、アエラのアンケート調査では36人中11人が通信費の負担を問題視していた。そのため、Wi-Fiやコンセントを設置する店が増えているが、すべての飲食店に普及しているわけではない。
通信費の負担だけでなく、スマホ注文には他のデメリットもある。子育て中の女性(45)は「スマホを取り出すと子どもが触りたがり、騒ぎ出す」と話す。高齢者にとっては操作が難しいこともあり、スマホを使いたくないと感じる人も少なくない。食事中にスマホを触ることに抵抗を感じる人や、LINEの友達追加が必須となるシステムを煩わしく思う人もいる。
なぜ飲食店はスマホ注文を導入するのか?コスト削減と業務効率の裏側
飲食店がスマホ注文を導入する背景には、経営上の明確な理由がある。人件費の削減がその一つだ。従業員が注文を取る手間が省かれることで、スタッフの負担が減り、人手不足の解決策として機能している。また、厨房へ直接注文が伝わるため、調理や提供までの流れがスムーズになり、業務効率が向上する。
さらに、スマホ注文のデータを活用することで、売れ筋メニューの把握が可能となる。これにより、適切な仕入れを行うことで食品ロスの削減にもつながっている。また、インバウンド対応においても、スマホ注文は有効な手段とされる。自動翻訳機能を利用すれば、多言語での対応が可能となり、外国人観光客にとっても利便性が向上する。
スマホ注文のデメリットを解決!飲食店が取るべき対策とは?
ITジャーナリストの篠原修司氏は、「フリーWi-Fiやモバイルバッテリーの貸出、あるいは注文専用のタブレットを用意すれば、客側の負担は軽減される」とSNSで指摘する。しかし、問題は単にスマホで注文できるかどうかにとどまらない。特定のアプリやLINEの友達登録を強制する仕組みになっている場合、不要なメッセージが届くことを嫌い、店から足が遠のく客も多いという。
海外のスマホ注文事情を比較!中国・アメリカ・日本の違いとは?
海外では、日本よりも進んだスマホ注文システムが導入されている。中国では完全キャッシュレスのスマホ注文型レストランが普及しており、アメリカではAIを活用したセルフオーダーが進化し、客の嗜好を分析しておすすめメニューを提示する仕組みが導入されている。日本ではスマホ注文の普及が進んでいるが、従来の接客サービスとのバランスを求める声も根強い。
人の温かみ×デジタルの融合がカギ!これからの飲食業界のスマホ注文戦略
スマホ注文の普及は避けられない流れであり、飲食店側の業務効率化や人手不足対策には有効な手段であることは間違いない。しかし、通信費負担やスマホ操作の煩わしさなど、客側の不満も無視できない。客にとっての利便性を考慮し、Wi-Fi環境の整備やタブレット注文の導入、さらにはアプリ登録不要のシステム設計など、より快適な注文体験を提供することが求められる。
デジタル化が進むなか、人の温かみを感じられるサービスを残しつつ、テクノロジーとの融合を図ることが、今後の飲食業界の鍵となるだろう。