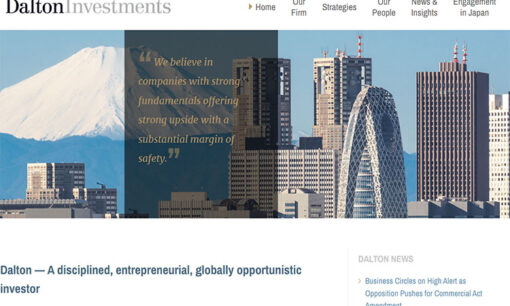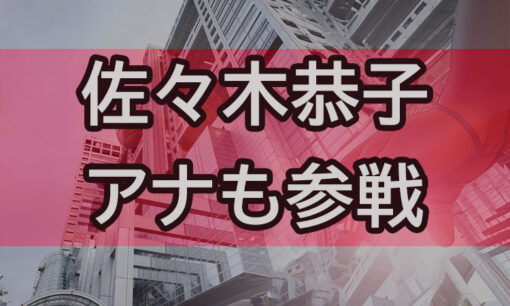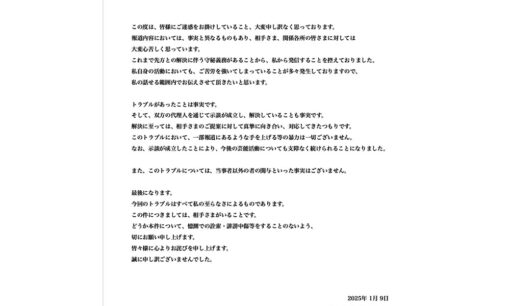フジテレビを巡る経営構造が再び注目を集めているが、その複雑さは他の上場企業と一線を画すものだ。株式会社フジ・メディア・ホールディングス(以下、フジメディアHD)は東京証券取引所に上場しているものの、同社の上に実質的な支配機構として「フジサンケイグループ」が存在している。
この構造の中で、フジサンケイグループ代表でありフジメディアHDの取締役相談役を務める日枝久氏(87)が、長年にわたり実質的な権力を握り続けていることが問題視されている。
フジの「特殊な構造」とその弊害
一般的な上場企業であれば、株主総会を通じた株主統治が経営の中核を担う。しかしフジテレビの場合、株主が選任する取締役会による統治は、フジメディアHDの枠内にとどまる。さらにその上には、株式会社産業経済新聞社(産経新聞)、株式会社ニッポン放送などを含むフジサンケイグループが存在し、この全体を統括する「グループ代表」という形式的な役職に過ぎない日枝氏が、実質的な最高権力者として君臨している。
この体制は、「グループ全体を見渡すための効率的な統治構造」として正当化されてきた。しかし、同時にこうした権力の集中が、株主や視聴者への説明責任を後回しにし、経営の硬直化を招いているとの批判が絶えない。特に日枝氏が37年間にわたり支配力を保持している現状について、「ガバナンス機能が著しく形骸化している」との指摘が専門家や市場関係者から上がっている。
「院政」批判と現場への影響
2017年にフジメディアHDとフジテレビジョンの会長職を退いた日枝氏だが、取締役相談役およびフジサンケイグループ代表として、依然として影響力を保持している。経営陣や現場の意思決定において、日枝氏の存在が常に意識されているとされ、その結果、現場の柔軟性やチャレンジ精神が損なわれているとの声も少なくない。
「社長をはじめ幹部が視聴者ではなく、日枝氏の意向を優先する構造が続いている。その結果、視聴率低迷や企画力の欠如が顕著になっている」とフジテレビ関係者は語る。
株主統治の不全と外圧の可能性
株主統治が十分に機能していないことも、フジメディアHDの構造的課題として浮上している。特に株主総会では、経営改革を求める声が上がるものの、日枝氏が築いた既得権益により実現は難しいとの指摘がある。
一部の専門家は「日本のメディア企業特有の閉鎖的な経営文化が、フジテレビの低迷を助長している」と語る。また、「外資系投資家の圧力によってしか変革が起こらないのではないか」との意見もある。
日枝久氏の権力掌握までの軌跡
フジテレビの特殊な構造が注目される中、日枝久氏がどのようにしてその権力を得たのかを辿ると、そこには波乱に満ちた物語が見えてくる。
以下では、彼がいかにしてフジテレビの絶対的な支配者となったのか、その軌跡を振り返る。
フジテレビと日枝久氏――権力者の誕生とその変遷
フジテレビの黄金期を築き上げ、その後も長きにわたり絶大な影響力を誇ってきた日枝久氏(87)。彼の名を語るとき、切り離せないのが、経営者としていかにして権力を得たかというその道のりである。ここでは日枝氏が辿った軌跡を、時代背景と共に掘り下げる。
出世コースから外れた青年時代
日枝氏がフジテレビに入社したのは1961年、同局の創業期だった。早稲田大学教育学部を卒業した日枝氏は当初教員を志していたが、ある日、大学構内でたまたま出会った教授に「新しいテレビ局に挑戦してみてはどうか」と誘われ、フジテレビへの入社を決めた。
しかし、入社後の日枝氏の道は平坦ではなかった。労働組合の結成に奔走した彼は、当時の経営陣と激しく対立。組合書記長として社員の待遇改善に尽力したものの、「反体制派」とみなされ、出世コースから完全に外れた。
「腐らずに意欲的に働き続ける」という日枝氏の姿勢が転機を迎えたのは、1980年、鹿内春雄氏がフジテレビ副社長に就任したときだった。春雄氏は「軽チャー路線」という若者向けの大胆な編成方針を打ち出し、フジテレビの革新を進める。日枝氏は42歳で編成局長に抜擢され、この挑戦的な路線を春雄氏と二人三脚で牽引することになる。
黄金期への道――「軽チャー路線」と視聴率三冠王
日枝氏が手掛けた「楽しくなければテレビじゃない」という編成戦略は、当時の保守的な放送業界に新風を吹き込んだ。若者に支持されるバラエティ番組やドラマが次々に生み出され、フジテレビは1982年に視聴率三冠王を達成。この成功は、以後12年にわたる黄金期の礎となった。
1988年、さらなる転機が訪れる。当時、フジサンケイグループの象徴的存在であり、日枝氏の後ろ盾でもあった鹿内春雄氏が、わずか43歳で急逝する。その後、グループ議長の座には父・鹿内信隆氏が復帰し、日枝氏はフジテレビの社長に昇進する。しかし、これが次なる権力闘争の幕開けだった。
「クーデター」としての支配権掌握
1990年代初頭、鹿内信隆氏が亡くなると、グループ議長には春雄氏の義理の弟である鹿内宏明氏が就任。宏明氏はグループ内での全権を握るが、ワンマン経営が周囲との軋轢を生む。1992年、フジサンケイグループ内でクーデターが勃発。日枝氏は反宏明派の中心人物として、この内紛を制し、グループ内での実権を握る。
この勝利により、フジテレビだけでなく、グループ全体を掌握する道が開かれた。1997年にはフジテレビの東証一部上場を実現し、「パブリック・カンパニー」としての地位を確立。一方で、グループ内での権力基盤をさらに強固にするため、持株会社体制への移行を推進し、2008年にはフジメディアHDを設立した。この新体制において、日枝氏はグループ全体の支配を完成させた。
ライブドア事件と「日枝体制」の完成
2005年、堀江貴文氏率いるライブドアがニッポン放送の株を買収し、フジテレビの支配を狙った事件が起きる。この危機に際し、日枝氏は先頭に立ってライブドアと対峙。結果的に堀江氏との和解に成功し、グループの安定を取り戻した。この事件をきっかけに、フジサンケイグループの資本構造の見直しを進めた日枝氏は、持株会社体制を確立し、自らの影響力を盤石なものとした。
長期支配と「院政」批判
2017年、日枝氏は会長職を退き、取締役相談役としてグループに残留。だが、その影響力は依然として強く、「院政を敷いている」との批判が続いている。実際、幹部人事や経営方針において、日枝氏の意向が色濃く反映されているとされる。
「視聴者ではなく、幹部が日枝氏を重視する姿勢が、フジテレビの低迷を招いている」とする声も多い。黄金期を築いた成功体験が、逆に現在の硬直化を生む一因となっているのは否定できない。
未来への問い
日枝氏の長期支配は日本の企業統治の問題点を象徴している。一部の専門家は「フジテレビが再生するためには、外部の視点を取り入れ、ガバナンスの透明性を高める必要がある」と指摘する。
日枝氏の軌跡は、個人の努力と戦略が企業をいかに変えるかを示す一方で、長期支配がもたらす歪みと課題も浮き彫りにしている。
誰が引導をわたすのか 再建への課題
日枝氏の影響力が依然として残る中、フジテレビが本格的に再建を果たすには、経営の透明性を高め、視聴者目線に立った番組作りを復活させる必要がある。次世代のリーダーがどのようにこの遺産を引き継ぎ、変革を進めていくのかが問われている。
かつて日枝氏は、1970年代、フジテレビがオーナー一族のワンマン経営で混乱を極め、マイナーなテレビ局と揶揄されていた時代に、経営に抵抗する労働組合の活動家として立ち上がった。組合のリーダーとして会社と対立しながらも、1980年代には編成局長として人気番組を次々と生み出し、フジテレビの存在感を劇的に高めた。
そして迎えた1988年、オーナー一族に対してクーデターを仕掛け、グループの実権を握ることに成功。以降、フジテレビを押し上げた立役者として評価される一方で、40年近くもの長期支配の中で「最初の王を倒した革命家」が「さらに強固な王」に変貌していった。
「歴史は繰り返す」と言われるが、フジテレビが真に再生を果たすには、日枝しの影響力を払拭する必要があるだろう。
そう遠くないうちに日枝氏が舞台を退く日は訪れるに違いない。しかし、それを待つだけでは、復活への道は遠い。社内から新たなリーダーが立ち上がり、引導を渡す覚悟を持たなければ、フジテレビの未来は描けない。
再び「楽しくなければテレビじゃない」の精神を取り戻せるか――その答えは、現場と次世代の挑戦にかかっている。
【フジテレビのその他の報道はこちら】
上から新着順