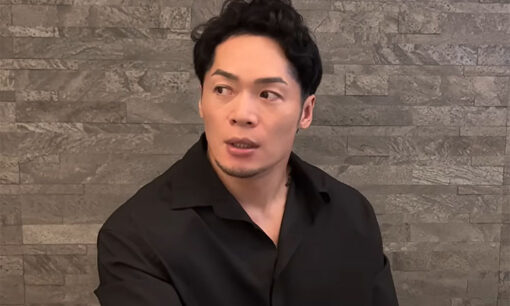最近の経済現象をゆる~やかに切り、「通説」をナナメに読み説く連載の第13回!イマドキのビジネスはだいたいそんなかんじだ‼
時短はSDGsの死角か? はたまた仕事の禁忌なのか?
「いやー8時間か。考えもしなかったなー」
イマドキの「サステナブルな取り組み」をしている大手メーカーの取材のとき出た発言だった。
そのメーカーは上場している化学系の大会社で、世界的にも有名サステナブル系審査機関とかファンドとか、NGOとかからいろいろな賞をもらっている、その界隈では有名どころである。
イマドキの大企業はSDGsの17の項目のすべてを掲げて、169のターゲットというより仔細な目標について、「2番目ではこんなことに取り組んでいる」「5番についてはこんなこととあんなことをやってます」ということをHPで訴求するのが習わしとなっている。
で、イマドキだと「それってあなたの感想ですよね?」みたいなことを言われたりするから、詳細なデータを掲載するだけでなく、そのデータが世界何十箇所に拠点を置くような審査機関のお墨付きをもらってますよ〜〜と言うのが当たり前になっている。
とは言っても、いかに大企業でも17のゴールと169のターゲットなんて網羅できるわけがないだろうから、得意なところから潰していく。
で、そうやって得意なところから手を広げていくと投入する人も金も手間も増えていくから、どんなに大企業とて湯水のごとく割けないだろうと思う。ましてお上が口を極めて「働き方改革を実現せよ」と言っておる時だ。残業なんてもってのほか。じゃ人を雇おうとなっても、世の中は空前の人手不足なのだ。
人件費はどんどん高騰しているから、ちょっと前に想定した人数は雇えない。そこはきっとDXとかGXとか、リモートワークなどを駆使して業務全体の生産性を上げていくしかないのではないか。
「なんか、劇的な時短方法とかなにかあるのではないかと…」
「時短、ですか?」
「いまリモートワークが導入されてますが、技術自体は前からあったわけです。でもなかなか普及しなかった。それがパンデミックとなり、急に使われるようになった。在宅でいろんなことができるようなったから通勤時間も減りました。出張も行きにくくなりましたが、オンラインツールを使えば移動時間も移動費もなくなった。
さまざまな業務ツールを使うといろいろ時短しやすい時代になったのかなーと。やり方によっては残業ゼロどころか、8時間も働かなくてもよくなっているんじゃないでしょうか? 御社くらい優秀な人が集まっていれば7時間とか6時間労働でもいけるんじゃないか、と…」
「そんなことはないですよー」
「でもできるんじゃないでしょうか。いろんな技術、ツールが揃ってきてますから。そこに御社のノウハウが合わさって…。そもそもなんで労働時間が8時間なんでしょうか。御社に聞くことではないかもしれませんが…。8時間労働が決まってから100年以上経ってるのに、コンピュータのチップの集積度が週単位で上がってるのに、なぜ8時間なんでしょう」
「なんで8時間なんだろう。知ってる、◯◯君?」
インタビュイーの紳士は、同席していた広報担当者に目配せした。この「なんで8時間」はことのほか紳士に刺さったようで、インタビューが終わってエレベーターホールまで送ってくれたときもしきりに繰り返していたのだった。
8時間労働のコンセプトを200年前に打ち出したロバート・オウエン
8時間労働の起こりは諸説ある。明確に記されているのは、500年前にイギリスの国王が発した「王令」である。日の出から夕刻までの労働で、休憩を除いて8時間を働くこととするようにとしたことがはじめとされるが、制度として法制化されたのは旧ソビエト連邦で、1917年のことだった。すでに100年以上も経っている。
そもそも8時間労働が明確なコンセプトとして打ち出されたのは、そこからさらに100年遡る。1817年にイギリスの実業家のロバート・オウエンが提唱した「仕事に8時間を、休憩に8時間を、やりたいことに8時間を」というスローガンからである。
26時間以上働かされ続けて過労死した女性
当時は産業革命の真っ只中で、10歳に満たない子どもたちが、暗く埃の舞う劣悪な環境の工場で16時間、多いところでは18時間も働かされた。しかも産業が発展するにつれてどんどん労働時間は延び、労働者も若年化し、女性もどんどん雇用された。
カール・マルクスの「資本論」のなかでは人気のドレスをつくる裁縫工場では平均で16時間半、ビーク時は26時間半も働かされて、女性が過労死したこともあったという。現代の資本主義はこの産業革命から始まったとされるが、資本家は人間を単に労働力とみなして、とりわけ子供、女性という弱者を奴隷として搾取していたのである。
最初から安価な労働力としてみなされた女性や子どもたちは、使われ放題だった。こうした人たちの夫や父親は、貴族や新興資産家、あるいは啓蒙思想家たちによってコモンズと呼ばれる農地を囲い込まれて、都市に流れ込んだ人たちだった。彼らは安い賃金で仕事を渇望するよう貧困状態に留め置かれた。
当時は日を追って技術革新が起こっていたから、それまでの職人の仕事も奪われていった。製品の需要以上に労働力の需要が上回っていたから、賃金は低いままどころか下がっていた、意図的に。哲学者のデイヴィッド・ヒューム先生は、「欠乏が何年も続き、それが極端でないばあい、貧民はより勤勉になり、よりよく生きるようになる」とその代表的著書「政治論集」で述べているほどだ。
よりよく生きるための思想はいま、ウエルビーイングと呼ばれてさまざまな組織で実践されつつあるが、そのルーツを探るとどうやら真反対の理論だったようだ。
囲い込みで行き場を失った農民や職を奪われた職人が都市のスラムに流れ込んだ

技術革新に伴い、資本家たちは生産性について言及しはじめていたが、当時「生産性が高い」ということは「労働力✕労働時間」で測っていたため、必然的に生産性の高い工場は長時間労働を強いることになったのだ。
当時のマンチェスターなどの工業都市は全国から集まった元農民や職を奪われた職人たちで溢れ、街はスラム化した。労働者は「どこからでも誘いさえすれば手早く掻き集められてきた人びとであって、その大多数が怠惰で・のんだくれで・嘘つきで・誠がなく、しかも偽信心家」と見られていた。
こうした惨状を嫌ほど見ていたオウエンは思ったのである。
「これらの悪状態を、よき状態に変じなくてはならぬ。かくして、自然の然るべき秩序において、その不変な法則に従って、かの劣悪な状態によって造られた劣悪な性格は、健康な状態によって、つくられるべき優良な性格に置き換えられなければならぬ。そして、これこそ、今や万人の幸福のために、あまねく実地に採用されるべき方法なのだ」と。
その理念を実践したのが、スコットランドのニュー・ラナーク工場だった。
オウエンは学歴こそは小学校卒だったようだが、経営者の才能が素晴らしく、19歳で小さな製糸工の工場主となってバリバリ経営して売上を伸ばし、21歳でひとかどの経営者となり、最終的には2000人を雇うまでの紡績王となった。
オウエンはいまでいう在庫管理や品質、生産技術の向上、新商品開発、販路開拓、財務力の向上など、経営者としていまではごく当たり前となっていることを人一倍熱心に取り組んだ。オウエンが他の経営者と優れて違っていたのは、工場の従業員を共同生活者として位置づけ、その生活環境の改善をサステナブルに行い続けて、今で言うQOL、ウエルビーイングの向上を図っていたところにある。
たまたま取引でおとずれたスコットランドのある女性と恋に落ちたオウエンは、彼女の父が工場を売りたがっていると聞き、「それじゃ」と買い取ったのががニュー・ラナーク工場だった。
オウエンは工場経営を通じ、生産性を高めることが高い利益につながると理解しており、生産性を高めるにはよりよい労働環境が必要だと考えていた。
当然生産性が高まれば労働時間が短縮できると見込んでいた。オウエンは当初10時間労働で稼働させたが、さらに短くできると考え、8時間を掲げたのである。実際にオウエンが8時間労働を実現させたかは不明だが、それに向けた取り組みはサステナブルに続けていたはずだった。
世界初の企業内育児施設
オウエンは当時工場経営者が考える理想をことごとく実現していった。たとえば、世界初の企業内育児施設である。オウエンは世界初の幼稚園を創設し、従業員の子どもたちを預かった。第1組と第2組があり、前者は3歳まで、後者は6歳までで、制服は無償で提供された。
独自の小学校もつくり、就労してからも教育を受けられるようにした。いわゆる夜間学校である。
従業員には高水準の給与を与え、生活水準の向上のために協同組合をつくり、共同で生活物資を安く購入し、従業員が安く購入できるようにした。
オウエンはまた「サイレントモニター」という、現在でいうところの人事評価制度も確立し、仕事のインセンティブを高めている。
オウエンの時代には2500人がニュー・ラナークに住んでいたが、その多くはグラスゴーやエディンバラの救護院(ワークハウス)の出身者ばかりだったのだ。救護院は当時、自立して生活することが困難な高齢者や病人、失業者などを救済するために作られた施設であった。
オウエンの工場はスコットランドやイングランドから注目を集めるようになり、オウエン自身も積極的に工場環境改革のための法律改正に動く。その結果、1918年に9歳未満の労働禁止、16歳以下の労働時間を12時間以内とする紡績工場法が制定された。
この内容にはオウエンは不服だったが、それでも従来の地獄のような労働環境からすれば、全然マシだった。
オウエンがニュー・ラナークで実践した取り組みは海を超えて世界中に広がり、工場衛生、教育、ガバナンス(企業統治)、協同組合、労働運動、労働法、工場法などさまざまな影響を与えていった。
ケインズは100年後には労働時間は1日3時間、週15時間になると予言した
労働時間については1886年にアメリカのシカゴやオーストラリアなどで、世界各地で8時間を求めるデモが起こったが、なかなか実施されなかった。成立したのはいわゆる西側ではなく、共産主義革命で誕生したソ連だった。
ILOが8時間労働の条約を制定したのは2年後の1919年だから、ソ連が誕生しなかったら、労働時間はいまだ10時間のままだったかもしれない。
いろいろあっても、何かをきっかけにコトが一気に進むことがある。労働時間もそうである。何せオウエンと同じイギリスの近代経済学の祖の1人でもある、ジョン・メイナード・ケインズ大先生が1928年に「100年以内に経済的な問題は解決する」と母校ケンブリッジ大学で一席ぶっているからだ。
曰く「全世界の人が生きていく上での最低限の富が満たされ、その際には多くても1日3時間、週15時間働けば、経済的な問題はなくなる」と。
まもなくその100年になるがその気配はない。
スウェーデンで1日6時間企業が増える
と思っていたら、挑戦的な試みをしている企業も出ているようだ。
スウェーデンでは、国が進めた社会的実験の影響もあって、いくつかの企業が6時間制を定着させているという。その1つが日本企業のトヨタだった。工場ではなくサービスセンターというのがミソだが、調査によるとクレームが大幅に減り、利益率が25%もアップしたという。いいじゃないか!
またある介護施設の例では、看護師の健康状態が改善され、「ずっと温厚になって注意力も増している」という。6時間勤務を18カ月続けた看護師のうち77%が健康状態は良好と回答。対して比較対象とした8時間労働の看護師は49%にとどまった。病欠も6時間勤務の看護師の方がはるかに少なかったという。
日本でもじわじわ時短の動きはあるようだ。大手食品メーカーの味の素は、2017年から就業時間を20分短縮し、8時15分から16時30分、8時45分から17時20分の時間帯を設定した。
いいじゃないか!
このまま6時間労働が広がり、ゆくゆくは3時間が可能なのか。
だが現実はそうもいかない模様だ。
ある化粧品のOEMを手掛ける経営者は「労働時間の短縮はおもしろそうだが、取引先が一緒にその時間にあわせてくれないと難しい」とこぼす。時間が短縮された場合、その分給料が減るという懸念もある。スタートトゥデイがうまくいっているのは、発注側でかつ給料を8時間労働を前提にしているからというのもある。
先のスウェーデンの例では実験が終わると8時間に戻した企業も多かった。時短にするとその分の人を雇う必要があり、人的コストが増えることや、実験期間は6時間でも8時間分の給料が出たが、実際導入となると6時間分しか出ないとなったためだ。
オウエンができたことを、なぜ現代の優れた経営者ができないのか
労働環境や社会福祉では先進と思われるスウェーデンでもこうした意識なのだと思うといかに世界中で8時間労働の縛りが強固なのかが伺い知れる。逆に言えば、いかにオウエンがやったことが凄かったかということだ。
ある労働経済の研究者はその凄さを「オウエンは彗星のように現れ、彗星のように消えていった」と評している。
オウエンは、社会思想史界隈では「ユートピア社会主義者」「空想社会主義者」に列せられているが、これは誤解を与える表現だと強く思う。理想を掲げ地道に検証と改善を重ね、実践を繰り返したオウエンは、さらなる理想を求め、ニュー・ラナークを売却し、その資金をもとにアメリカに渡って農業を取り込んだ新しいエコシステム「ニューハーモニー村」を建設している。
この画期的な村は、いくつかのシステム的な問題と関係者の誤解や無理解などから破綻しているが、手順をしっかり踏んでいれば、現在につながる田園都市が生まれていたと、ワタシは思う。
少なくとも自らを「科学的」と評したカール・マルクスより、ずっと科学的で実証的だった。
労働時間の短縮改革はさまざまなしがらみがあって実現は難しいのかもしれない。だが200年前オウエンがたった1人でできた時短が、なぜ現代の優秀な経営者たちにできないのか。
言っていけない、触れてはいけない禁忌なのか。ワタシは不思議で不思議でならない。
イマドキのビジネスはだいたいそんな感じだ。