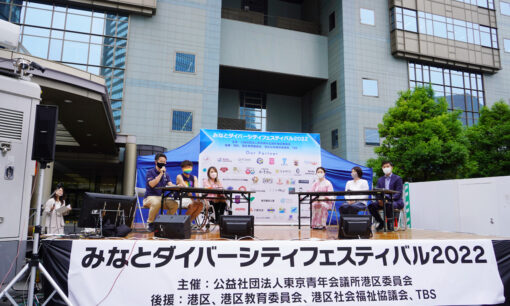第1回)変わる「優良企業」の条件~企業が環境対応をせざるをえないワケ
地球温暖化の問題が深刻さを増す中で、「優良企業」の条件が変わろうとしている。かつては「資本効率」や「株主還元」などお金に関連する項目だけが重要とされたが、「環境対応」「持続可能性(サステナビリティ)」という新たな条件が加わりつつある。大きなきっかけとなったのが、東京証券取引所が2021年6月に改訂した「コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)」だ。上場企業は報告書で、気候変動など環境問題への対応内容を開示するか、対応していない場合は理由を説明しなければならなくなった。23年3月期の有価証券報告書からは、サステナビリティ情報の開示が義務になる。企業への環境対応への要求は今後さらに厳しくなる方向だ。国連が17の目標から成るSDGs(持続可能な開発目標)を採択して8年。さまざまな課題や矛盾も抱えながら、多くの日本企業は「環境力」の強化に乗り出している。
(ジャーナリスト、元日本経済新聞記者 日高広太郎)
■ 拡大するESG投資、環境力の弱い企業に「売られるリスク」
「年金基金などの機関投資家がESG(環境・社会・企業統治)の観点を重視するようになり、企業は対応をせざるをえなくなった」。東京証券取引所上場部でコーポレートガバナンス・コードの改訂を担当した信田裕介調査役は、企業の「環境力」強化の重要性を強調する。各国の運用会社などで構成する世界持続的投資連合(GSIA)によると、2020年の世界のESG投資は35.3兆ドルと16年からの4年間で1.5倍に膨らんだ。
気候変動が進み、台風や洪水による災害が頻発すれば、例えば「工場の生産停止期間が長期化する」「気候災害関連の訴訟が増える」などのリスクが出てくる。将来的に「炭素税」が導入されれば、二酸化炭素(CO2)排出量が多い企業により多くの税金がかかるという問題もある。大和総研の藤野大輝研究員は「環境対応に消極的な企業は将来のリスクが高いとみなされ、投資家にそっぽを向かれかねない」と話す。
■ 内閣府令も改正、対応できなければ信用失墜も

コーポレートガバナンス・コードは、金融庁と東証が15年に導入した「上場企業の企業価値向上のための行動指針」のこと。守れない場合、企業はその理由を東証に説明しなければならない。十分に説明できない場合は、「理由の説明義務に違反した」として名前を公表される場合があり、企業側も対応に必死だ。社会的な信用が失墜し、業績や株価に悪影響を及ぼす可能性が高いからだ。
21年の同コードの改定では、「サステナビリティを巡る取り組みについての基本的方針の策定」などの項目が盛り込まれた。さらに、気候変動などの環境問題への配慮などについて積極的な対応も求めており、企業は具体的な情報を開示する必要がある。
企業にとってもう1つの圧力となりそうなのが、内閣府令の改正だ。事業年度ごとに企業情報を開示する有価証券報告書に、サステナビリティ情報を記載しなければならなくなったためだ。具体的には、環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防止、贈収賄防止、ガバナンス、サイバーセキュリティなどの情報を掲載する必要がある。一部の企業は気候変動への対応についての情報開示を迫られそうだ。
■ セイコーエプソンは「カーボンマイナス」
政府や東証の動きを受けて、企業は相次ぎ環境関連の施策を打ち出している。政府は温暖化ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を50年に実現することを宣言しているが、日本経済新聞社の22年の「SDGs経営調査」では、カーボンニュートラルを宣言している企業は53.3%に達したという。
例えば、トヨタ自動車は2050年までにハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車などを拡充・普及させ、新車の走行時のCO2排出量を10年比で9割減らすことを目指している。味の素は30年までに「50%の環境負荷を削減する」との目標を設定。フードロスやプラスチック廃棄物の削減などを進める。セイコーエプソンは50年に温暖化ガスの排出量を上回る削減効果を実現する「カーボンマイナス」という目標を掲げている。 ESGへの取り組みを役員報酬に連動させる取り組みも増えている。世界的にESG投資が急増していることに加え、欧米諸国でESG関連の株主提案が急速に増えていることも背景にある。花王はESGへの取り組みを一般社員のボーナスを含めた賃金に反映する制度を導入している。
■ グリーンウォッシュ、過激な抗議活動・・・課題や矛盾もあらわに
SDGsなど環境問題への対応を巡っては課題も多い。その1つが、実態を伴っていない企業の環境活動だ。例えば、「100%リサイクル可能とする紙製ストローへと切り替えたが、実際には分厚すぎてリサイクルができていなかった」「温暖化ガス排出量が実質ゼロの資源開発プロジェクトを立ち上げたと発表したが、それに応じた投資をしていなかった」といった事例だ。「グリーンウォッシュ」ともいわれる、こうした事例は相次いで発見されている。
一方で一部の環境活動家らの過激な行動も目立つ。昨年は英国の美術館にあるゴッホの「ひまわり」にトマトスープとみられる液体を投げつける事件が起こった。気候変動対策を求める自分たちの主張に注意を引く意図があるようだが、こうした過激な活動は批判を招きこそすれ、共感は得られそうもない。
■ 環境対応への圧力はさらに厳しく、実効性がカギ
とはいえ、このまま環境破壊を放置しても良いと考える人はまれだろう。コーポレートガバナンス・コードの改訂や内閣府令の改正をみれば、企業の環境力強化への社会の圧力が強まっているのは明らかだ。気候変動が進んで自然災害がさらに増えれば、経済への悪影響や社会不安が拡大し、企業が求められる環境対応の水準はさらに厳しくなりそうだ。
東証の信田氏は、企業に求める環境対応の見通しについて「今後は実効性を高めることが課題となる。前進はしても後退することはない」と話す。大和総研の藤野氏は「国際的には企業の環境対応について、さらに厳格な開示の検討が進められている。いずれ日本にも影響が及ぶだろう」と指摘する。経済社会や国際情勢が大きく変容する中、多様化し、厳格化していく「優良企業の条件」。それを満たすための挑戦は、多くの企業にとってまだ始まったばかりだ。