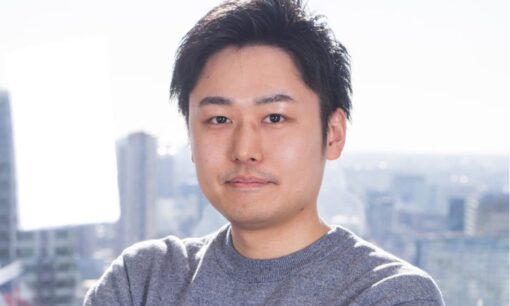100万本ヒットの裏にあった、作り手と使い手の物語

「魔法瓶」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。 高性能なスペック? 朝入れたコーヒーが夕方まで温かい機能性? もちろん、それらは重要だ。
しかし、大阪に本社を置く創業75年の老舗・ピーコック魔法瓶工業が本当に作りたかったのは、単なる保温容器ではなかったのかもしれない。
彼らが作りたかったのは、生活の“余白”を楽しむ時間だ。昭和の時代、家族団らんの中心にあった「花柄のポット」。 令和の今、猛暑に立ち向かう人々を救った「アイスパック」。 そして、夜な夜なゲームに没頭する若者の喉を潤す「ゲーミングボトル」。

一見バラバラに見えるこれらの商品には、一つの共通点がある。
それは、ちょっとお節介で、人間臭いということだ。これは、技術一辺倒だった老舗メーカーが、生活者という“先生”に出会い、モノづくりの本当の意味を再発見するまでの、挫折と再生の物語である。
完璧な計算から生まれた「失敗作」
時計の針を少し戻そう。 2021年、ピーコック魔法瓶は社運をかけた新商品を世に送り出した。「アイスパック」シリーズである。
開発のきっかけは、4代目社長・山中千佳の、あまりにも個人的な悩みだった。

山中千佳さん
「真夏のゴルフ、氷嚢を持っていくけれど、すぐに氷が溶けてしまう。これじゃあ意味がない」
ここまではよくある開発秘話だ。しかし、ここからがピーコックらしい。
彼らは、創業以来培ってきた魔法瓶の真空断熱技術を、飲み物の温度ではなく氷嚢の冷たさを守るために使うことにしたのだ。
魔法瓶で「冷たさをキープするホルダーを作れば、一日中冷たいまま体を冷やせる」
理論上は完璧だった。技術的にも申し分ない。「これは売れる」 開発チームは確信していた。
しかし、市場の反応は残酷だった。
全く、売れなかったのだ。
発売から2年間、その商品は倉庫の棚で静かに眠り続けた。
スポーツ用品店のバイヤーからは「水筒売り場に置くには形が変だ」「そもそも何に使うのか伝わらない」と敬遠され、消費者からは見向きもされない。本来なら、ここで「終売」のハンコが押されるはずだった。 しかし、彼らは諦めなかった。
「いや、絶対に必要としている人がいるはずだ」 それは意地だったのか、それとも確信だったのか。広報の木村剛治氏は当時を振り返り、苦笑いする。

広報・木村剛治さん
「正直、社内でも『なんでまだやるの?』という空気はありました。でも、作り手としてのエゴかもしれないけれど、この技術が誰かの役に立つということを、僕ら自身が一番信じていたんです」
この「往生際の悪さ」こそが、後の奇跡を呼び込むことになる。
顧客が教えてくれた「本当の価値」
転機は、開発室の会議机の上ではなく、SNSという広大な海の中で起きた。 2023年の夏、記録的な猛暑が日本列島を襲っていた頃、北海道のあるユーザーが投稿した一つのつぶやきが、運命を変えた。
「子供に持たせたネックリング。溶けたらピーコック魔法瓶のアイスパックと一緒にしておけば、復活する!」
その投稿は、瞬く間に拡散された。 当時、首元を冷やす「ネッククーラー(PCM素材のリング)」は大流行していたが、一度溶けてしまうと再冷凍する場所がないのが最大の弱点だった。
ユーザーは、ピーコックが「氷嚢用」として作った商品を、「持ち運べる冷凍庫」としてハッキング(読み替え)したのだ。
この発見に、一番驚いたのはピーコックの社員たちだった。
「僕たちは『ゴルフ』や『スポーツ』という用途に縛られていた。でも、お客様はもっと自由に、もっと切実な生活の悩み解決に、この商品を使ってくれたんです」(木村さん)
そこからは早かった。「そういう使い方があったのか!」「これなら部活の子供に持たせられる」「コミケの熱中症対策に最高だ」 SNS上には、感謝と驚きの声が溢れた。
売れない在庫の山だった「アイスパック」は、一夜にして「どこにも売っていない幻の神アイテム」へと変わった。2025年にはシリーズ累計100万本を突破する大ヒット商品となったのだ。

これは単なる「SNSバズ」の話ではない。メーカーが一方的に「こう使え」と押し付けるのではなく、「作り手が込めた技術(種)」を「使い手が育てて(花)、完成させる」という、新しいモノづくりのサイクルが生まれた瞬間だった。
「回転底」から受け継がれる、お節介なDNA
なぜ、ピーコック魔法瓶は、こうした柔軟な変化を受け入れられたのか。 そのルーツを探ると、創業期のある発明に行き着く。
昭和の時代、どこの家庭にもあったガラス製の魔法瓶ポット。水を入れると重くなるポットを、お年寄りや子供でも楽に扱えるようにしたい。そんな想いから創業者が発明したのが、ポットの底にベアリングを入れ、指一本でくるりと向きを変えられる「回転底」だった。

「技術を見せびらかすのではなく、使う人の『ちょっとした不便』に寄り添いたい」
そのDNAは、今の尖った商品群にも脈々と受け継がれている。
例えば、「ゲーミングボトル」。eスポーツ市場が盛り上がる中、彼らはゲーマーの行動を徹底的に観察した。ヘッドセットをしているから普通の水筒は飲みづらい。ゲーム中はモニターから目を離したくない。そこで、飲み口に角度をつけ、視線を外さずに飲めるボトルを開発した。さらに、炭酸飲料対応にして、エナジードリンクも入れられるようにした。
また、「おうち居酒屋」シリーズ。 コロナ禍で外食ができないお父さんのために、家で瓶ビールをいつまでも冷たく飲めるタンブラーを作った。氷水を用意する手間すら省けるように設計した。

これらは全て、マーケティングデータから弾き出された正解ではない。「こんな時に困っている人がいるんじゃないか?」「こうしたらもっと楽しいんじゃないか?」という、作り手たちの「お節介な想像力」から生まれたものだ。
「孔雀」は、誰よりも生活者の近くにいる
大手メーカーが席巻する魔法瓶業界において、ピーコック魔法瓶のような存在は稀有だ。彼らは、巨大な資本や圧倒的な広告量で勝負はしない。 その代わり、彼らには愛嬌がある。
売れなかった商品を2年も抱え続ける不器用さ。ユーザーの裏技を公式採用して喜んでしまう素直さ。 そして、社員90名という規模だからこそできる、社長直轄の「おもろいやん」で動くスピード感。
木村さんは語る。
「私たちは、魔法瓶という“ハード”を作っていますが、本当にお届けしたいのは“ソフト”、つまり生活の中にある『心地よい時間』なんです。 氷嚢ホルダーがヒットした時、一番嬉しかったのは売上数字ではありません。お客様が『ピーコックさん、ありがとう!これで夏が乗り切れるよ』と、まるで友達のように話しかけてくれたことなんです」
完璧なブランドである必要はない。時には失敗もし、時にはお客様に教えられる。そんな隙のある老舗だからこそ、人々は親しみを感じ、応援したくなるのかもしれない。
企業理念は「食に感動を」。 75年前、大阪の町工場から始まった「孔雀(ピーコック)」の旅。 かつて海を渡り、東南アジアの人々の喉を潤したその技術は今、SNSという新しい風に乗って、現代人の渇いた心をも潤している。
次に彼らがどんなお節介を焼いてくれるのか。 私たちは、一人のファンとして、その新作を楽しみに待っていればいい。