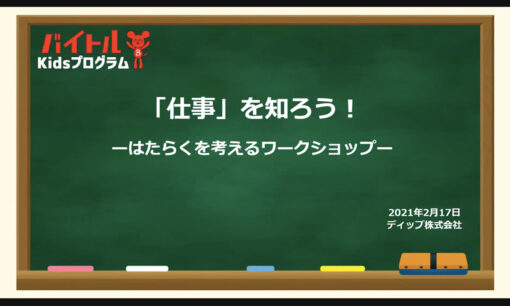かつて江戸前で重宝されたクロダイが、現代では「海の厄介者」として扱われている。この矛盾に光を当て、未利用魚の価値を再定義するスタートアップ、ベンナーズの挑戦が東京駅の真ん中で静かに幕を開ける。
東京駅に現れた「江戸前の真実」を喰らう場所
人流が交差する東京駅の「JAPAN RAIL CAFE TOKYO」にて、ある試みが注目を集めている。福岡に拠点を置く水産加工スタートアップ、株式会社ベンナーズが、JR東日本クロスステーションとタッグを組んで放つSDGsイベント「ツナグステーション」だ。
主役は、かつて高級魚として名を馳せた「クロダイ」である。しかし現代において、この魚は複雑な立場に置かれている。
市場での評価が安定しない一方で、東京湾のノリ養殖を食い荒らす「食害」の元凶として、漁業者からは疎まれる存在となっているのだ。ベンナーズは今回、このクロダイを「未利用魚」という枠組みから救い出し、洗練された海鮮丼として都市の消費者に提示した。
「規格外」を「極上品」へ昇華させる独自の目利き
ベンナーズの取り組みが既存の鮮魚流通と一線を画すのは、単なる「余り物の有効活用」に留まらない点にある。彼らが展開するサービス「フィシュル!」の根底にあるのは、未利用魚が持つポテンシャルの徹底的な引き出しだ。
今回のイベントで提供されるメニューを見れば、そのこだわりが理解できる。クロダイは、大分県産の高級梅干しを使用した特製の梅生姜ダレに漬け込まれ、瀬戸内海の牡蠣殻を肥料にした「里海米」の上に乗る。
さらに、茶業の製造過程で出る「はしっこ茶」を添えることで、最後の一口まで物語を完結させている。他社が「安価な代用魚」として扱う未利用魚を、彼らは「その背景ごと味わうべき希少品」へと見事にプロデュースしてみせた。
「美味しくなければ、文化は続かない」という信念
なぜ、これほどまでに手間をかけるのか。その答えは、代表の井口剛志氏が抱く水産業への危機感と哲学にある。日本の水産現場では、味に問題がなくとも、サイズが不揃いだったり、調理に手間がかかったりするという理由だけで、多くの魚が廃棄されてきた。
「魚食文化を守るためには、消費者に我慢や義務感を強いてはいけない」という考えが、彼らの行動原理だ。SDGsという言葉が踊る昨今、正論だけで人は動かない。
ベンナーズが追求するのは、あくまで「圧倒的な美味しさ」という実体験を通じた行動変容である。未利用魚を日常の食卓に載せる仕組みを作ることは、漁師の所得向上に直結し、結果として持続可能な海洋資源の維持へと繋がっていく。
一皿の海鮮丼が突きつける、現代ビジネスへの教訓
ベンナーズの歩みから、我々ビジネスパーソンが学ぶべきは「負の資産を資産へ転換する視点」だろう。社会課題として忌避されていた「海の厄介者」を、独自の加工技術とストーリーテリングで「特別な体験」へと変貌させた。
「この魚、本当に美味しいですね」と驚く客に対し、スタッフが「実はこれ、ノリを食べてしまう困りものだったんですよ」と微笑む。そんな会話のなかに、社会貢献とビジネスが幸福に両立するヒントが隠されている。
東京駅でのこの体験は、単なる食事ではない。捨てられていた価値に再び命を吹き込む、静かなる革命の目撃なのである。