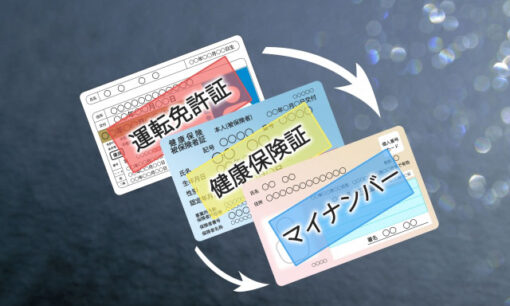スペイン産生ハムの輸入停止は、日本の食市場が抱えてきた「輸入依存」という前提を静かに揺さぶった。供給不安のなかで浮上したのは、国産生ハムという、これまで脇役にとどまってきた存在である。量では代替にならなくとも、国内で生産し、熟成し、評価する仕組みを育てる契機となり得るのか。輸入停止を一過性の混乱で終わらせないための課題と可能性を追う。
輸入停止が露呈させた「脆弱な前提」
スペイン産生ハムを含む豚肉関連品の輸入停止は、単なる一商品の供給不安にとどまらない問題を浮かび上がらせた。日本の生ハム市場が、特定地域の生産と国際物流に過度に依存してきたという構造そのものだ。
飲食店や流通現場では代替品の確保に追われているが、今回の事態は「いつ元に戻るか」を待つ局面ではない。むしろ、輸入が止まった瞬間に市場全体が動揺した事実こそが、これまで見過ごされてきた前提の脆さを示している。
輸入措置の現状は「固定」ではない
輸入停止の背景には、アフリカ豚熱への警戒がある。日本は2025年11月下旬、スペインからの豚肉等の輸入を一時停止する措置を取った。
一方で、国際的な防疫対応は状況に応じて見直される性質を持つ。一定の条件を満たす製品については、例外的な取り扱いが検討される可能性もあり、供給環境は依然として不確実性をはらんでいる。重要なのは、措置が長期化するかどうかを断定することではなく、市場が常に変動リスクを抱えている現実だ。
代替では埋まらない空白
現実問題として、国産生ハムが欧州産の供給量を肩代わりすることは難しい。国内生産は小規模が中心で、長期熟成を前提とするため、短期間での増産には限界がある。
しかし、問題の本質は量の不足そのものではない。輸入が滞った際に、「国内に選択肢がほとんど存在しない」状態が可視化された点にある。今回の輸入停止は、その空白を多くの事業者に強く意識させる契機となった。
危機のなかで可視化された国内の挑戦
国内では、以前から生ハムづくりに挑んできた事業者が存在する。長野県の株式会社SATOKAは、国産豚を用いた長期熟成生ハムの製造を続けてきた。山形県の東北ハムも、庄内地方の豚肉を使った生ハムを手がけ、地域資源を生かしたものづくりを行っている。
また、北海道や北関東、中部など各地に、少量生産ながら独自の熟成技術を磨くクラフト系工房が点在する。こうした動きは輸入停止以前から存在していたが、市場全体の関心を集める機会は限られてきた。
「つくれる」ことと「続く」ことの間
輸入停止をきっかけに、国産生ハムは注目を集め始めた。しかし、注目がそのまま定着につながるとは限らない。長期熟成に必要な設備投資、衛生管理、安定した原料供給、そして分かりやすい基準づくり──いずれも個々の生産者だけで解決できる課題ではない。
生産者のネットワーク形成や基準整備を担う団体の役割も重要になる。危機が去れば再び輸入依存に戻るのか、それとも国内基盤の整備に踏み出すのか。分岐点はここにある。
文化として根付くために必要な視点
国産生ハムを「非常時の代替品」と位置づけてしまえば、輸入環境が落ち着いたときに存在感は薄れる。一方で、地域性やトレーサビリティ、日本の気候風土を生かした熟成という価値を、食文化として提示できれば状況は変わる。
量で競うのではなく、「どこで、誰が、どう育て、どう熟成させたか」を語れる商品として育てられるか。そのためには、生産者だけでなく、飲食店、流通、小売、そして消費者側の理解と選択が欠かせない。
危機を一過性で終わらせないために
今回の輸入停止は、日本の食市場が抱えてきた依存構造を可視化した。その構造を「元に戻す」だけで終わらせるのか、それとも国内で生産し、育て、評価する文化を積み重ねるのか。
国産生ハムが市場の主流になる可能性は高くない。それでも、確かな選択肢として存在し続けることはできる。輸入停止という「危機」を、国産生ハム文化を育てる転機とできるかどうか。その成否は、いまの関心を持続的な取り組みに変えられるかにかかっている。