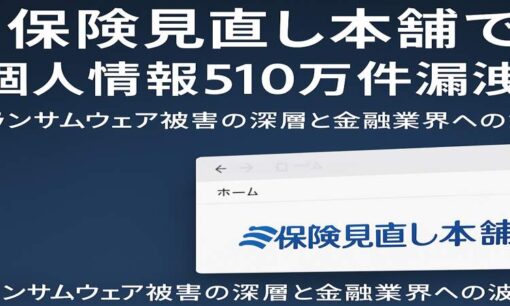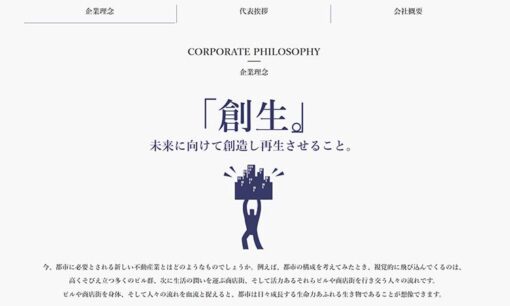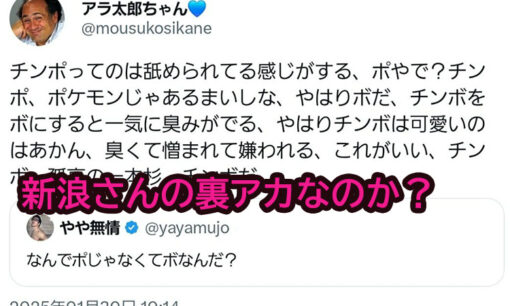細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』が、公開直後から予想外の苦戦を強いられている。日テレが過去作の連続放送を含めて万全の宣伝態勢を敷いたにもかかわらず、興行収入は伸び悩み、SNSには鑑賞者の厳しい声が相次いだ。
同じ週末、実写映画『国宝』が22年ぶりに邦画歴代興収記録を更新し、『鬼滅の刃』『チェンソーマン』などアニメ作品の熱量も衰えない。映画界の力学が大きく変わったことを示す象徴的な三連休となった。
初動の低迷が映すもの 細田守作品では異例の数字とSNSに広がる厳しい声
公開3日間の興収は2億7000万円。一般的な邦画なら上々と言えるが、『竜とそばかすの姫』が同期間で8億9000万円、最終で66億円に到達した“細田ブランド”の強さを考えれば、今回の初動はあまりに物足りない。関係者の間でも「細田監督の新作がここまで初動でつまずくとは想定外」という声が出ている。
主演はスカーレット役の芦田愛菜、旅の相棒となる看護師・聖役の岡田将生。宿敵クローディアスを役所広司が演じ、市村正親、吉田鋼太郎、斉藤由貴、松重豊、山路和弘、柄本時生、青木崇高、染谷将太らが脇を固めるという、いわば“豪華布陣”だ。それでも数字が動かなかった点は象徴的だ。
SNSで寄せられた反応をたどると、その理由の一端が見えてくる。
「映像は美しいが物語の芯が弱い」
「キャラクターの動機が薄く、感情移入できない」
「テーマが散漫で焦点がぼやける」
といった声が目立ち、批判の矛先はキャストではなく作品の構造そのものに向かっていた。
こうした感想は“傾向としてみられたタイプ”のものであり、特定の投稿の引用ではないが、評価の重心が肯定より否定に傾いていたのは確かだ。
通常、細田監督の新作公開時には、熱心なファンが絶賛を連投し、その熱量が初動の勢いを押し上げる。だが今回は、そうした“ポジティブなうねり”が生じなかった。興行の低調とSNSの厳評が互いに作用し、「数字が伸びない → ネガティブな空気が濃くなる → さらに観客が動かない」という循環が、ごく短期間に出来上がってしまった。
ブランドだけで観客を動かせた時代は、静かに終わりつつある。
今回の初動は、その現実を細田作品が真正面から突きつけられた出来事でもある。
アニメ勢は依然として強い 『鬼滅』『チェンソーマン』の熱狂
『果てしなきスカーレット』が伸び悩む一方で、アニメ作品、とりわけ『鬼滅の刃』と『チェンソーマン』の存在感は依然として圧倒的だった。同じタイミングで公開・解禁された映像や情報がSNSで瞬時に拡散され、ユーザーの反応速度と熱量は、もはや「映画宣伝の常識」を超えた段階にある。
『鬼滅の刃』は作品単体の人気にとどまらず、シリーズを横断する共同体的ファンダムという特性を持つ。新PVや最新情報が出るたび、SNSでは数十万件規模の投稿が一気に流れ、YouTube上では関連動画が数百万再生を短期間で積み上げる。この“常時接続型の熱狂”は、テレビ放送や劇場公開といった区切りを前提とした旧来型の視聴行動とはまったく異なる。
一方、『チェンソーマン』は全く別の文脈で強い。原作・アニメ・音楽カルチャーが混じり合う“領域横断型コンテンツ”で、ファン層が極端にネットネイティブ寄りだ。新作情報の一片だけでSNS全体が反応し、ファンアート、考察、MAD動画など二次創作が連鎖的に増殖する。テレビ宣伝では発生し得ない“自走型プロモーション”が自然に立ち上がる構造だ。
ここには、映画興行を左右する決定的な違いがある。
アニメ勢は、作品そのものが常にSNSの中心に存在し続け、観客が自ら宣伝装置になるのに対し、テレビ局が後押しする実写作品や劇場アニメは、どうしても“公開期間に宣伝を集中させる”モデルから抜け出せない。
つまり、『鬼滅』『チェンソーマン』が強いのは単に人気があるからではない。
作品とファンがオンライン上で常に接続し続け、情報が滞留せず循環し続ける構造そのものが強いのだ。
対照的に、『果てしなきスカーレット』には、その“循環”がまったく生まれなかった。
細田作品のファンは幅広いが、ネット上で常に議論や二次創作が生まれる類の作品特性ではない。公開前の熱量を維持する仕組みも弱く、SNSでの情報の流れが細く、話題が広がる速度も遅い。
さらに、アニメ勢は音楽コンテンツとも強く結びついている。
人気アーティストの主題歌が出ればそれだけで数千万再生規模の露出が生まれ、作品の熱量を底上げする。
これも“テレビ宣伝中心”の作品では手が届きにくい領域だ。
『鬼滅』や『チェンソーマン』の熱狂は、単なる一作品の成功ではなく、
ファンコミュニティが作品の寿命を自ら延命し、興行タイミングを超えて市場を支配する新しい成功モデルそのものだ。
この構造の違いを前に、『果てしなきスカーレット』が弱い初動のまま推移したのは、もはや偶然ではない。
観客の熱量がどこに流れ、どんな仕組みで強化されていくのか――作品同士の“構造的競争”の結果がそのまま数字に出たと言える。
テレビ局の総力戦が効かない時代へ
今回の日テレは、かつての成功パターンを踏襲し、総力を挙げて細田作品を後押しした。
金曜ロードショーで過去3作品を連続放送し、情報番組やバラエティでは特集を組み、キャストも多数出演した。地上波という巨大メディアをフルに稼働させた戦略だった。
しかし、結果的に興行への寄与はほとんど見られなかった。
理由は明確だ。映画を観るかどうかの意思決定は、すでにテレビから離れている。
金ローでの放送が「週末に映画館へ行く」導線になったのは過去の話で、今の若年層は地上波を見ないまま公開日を迎える。映画選びの基準はSNSの“生の口コミ”へ移行し、テレビの影響力は急速に後退した。
SNSでは次のような声も目立った。
「テレビの推し方が昔のまま」
「宣伝の量と作品の強度が噛み合っていない」
「金ロー放送はもう初動ブーストにならない」
テレビ局がいくら力を入れても、観客の判断軸は変わってしまった。
その構造的なズレが、『スカーレット』の初動の弱さを決定づけたと言える。
『国宝』が示す“本物の作り方” 記録更新の裏にあるもの
そして同じ週末、実写映画『国宝』が歴史的な興行記録を更新した。
22年間破られなかった『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』の興収を静かに追い抜いたのである。
脚本は2年をかけて磨かれ、主演の吉沢亮と横浜流星は1年半歌舞伎を稽古した。製作はアニプレックスとミリアゴンスタジオ。テレビ局主導ではなく、劇場映画としての作り込みが徹底されている。
“テレビの後押し”ではなく、“映画としての純度”そのものが観客を引き寄せた格好だ。
『スカーレット』との対比は残酷なほど鮮明で、映画界が進むべき方向を示している。
テレビ依存の終焉、映画は純粋な競争へ
90年代、テレビ局映画は邦画界を救った。しかしその役割はすでに終わりつつある。
2010年代以降、ネットの台頭とともに観客の鑑賞行動が変わり、ヒット作はテレビの枠外から次々と生まれた。
今回の『スカーレット』の苦戦、アニメ勢の熱狂、そして『国宝』の歴史的更新。
三つの現象が並ぶことで、映画界の現在地ははっきりと浮かび上がる。
ヒットを生むのは――テレビの力ではなく、映画そのものの力である。