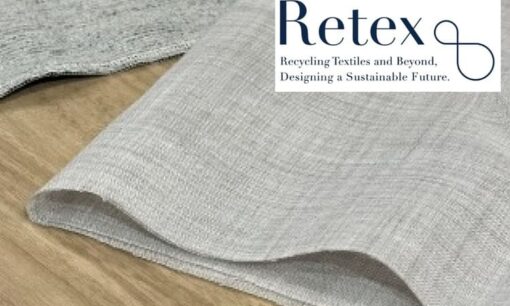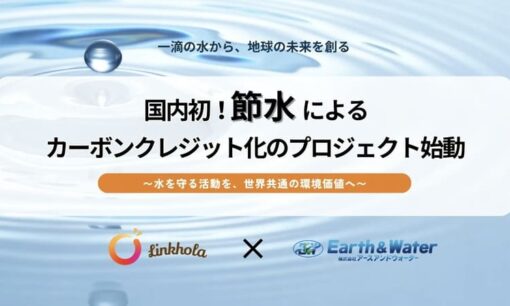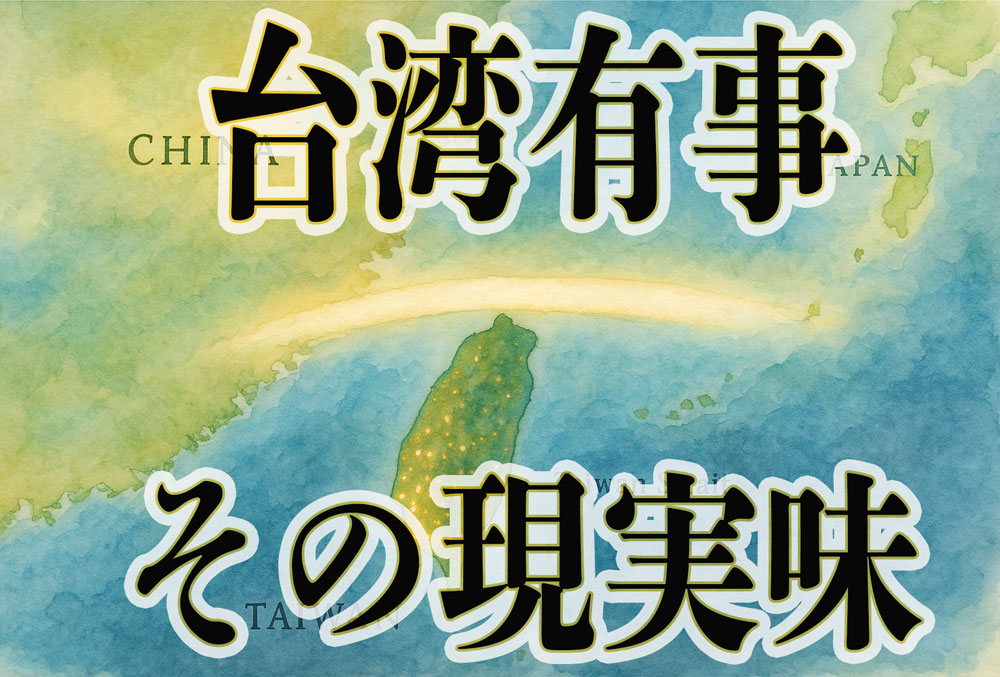
「台湾有事」という言葉が、ここ一週間あまり連日のように見出しに躍っている。日本の「存立危機事態」発言を機に、中国の圧力が増し、言葉の存在感が強まっている。しかし実際のところ、有事の可能性を見つめるべきだという声と同時に、いたずらに危機を煽るべきではないとの指摘もある。
過去の戦争はどのように始まり、どんな誤算が決断を狂わせてきたのか。そして映像作品が描こうとする「いまそこにある危機」とは──歴史と現実、フィクションを行き来しながら、台湾有事の“現実味”を冷静に考えたい。
台湾有事は起きる? 専門家の見方
ここ一週間あまり、「台湾有事」という言葉を連日目にするようになった。台湾有事とは、一般に 中国が台湾に対して武力行使に踏み切る可能性、あるいはそれに準ずる重大な軍事的緊張を指す。日本にとっては、地理的に近接するだけでなく、生活物資の多くが通る海上交通路(シーレーン)の安全にも重大な影響を及ぼしかねない(出典:Yahoo!ニュース「台湾有事は存立危機事態になり得る」)。
では、その現実味はどの程度なのか。
キヤノングローバル戦略研究所の峯村健司氏は、中国指導部の意思決定構造や台湾周辺の軍事的圧力の高まりを分析し、台湾海峡情勢が「従来よりも危険な段階へ近づいている」と評した。同氏は、中国が短期戦で収められると誤認し、国際情勢の混乱に乗じて台湾への軍事行動に踏み切る可能性を指摘し、「台湾有事は十分あり得る」という見解を示している(出典:同上)。
ただし、峯村氏は「確率論だけで語るべきではない」とも強調する。外交交渉の余地、抑止のための国際協調、経済的相互依存など、戦争回避のための装置も依然として機能し得るからだ。
一方で、歴史を振り返れば、戦争は“想定外”や“小さな誤算”の積み重ねによって、避けられない局面に追い込まれてきた。そのため、危機を煽ることなく、しかし油断することなく、状況を見つめる必要がある。
では、過去の戦争はどのような経緯で始まってしまったのか。次の章では、その典型例をたどりながら、私たちが今、何に警戒すべきなのかを整理したい。
戦争のはじまるとき―過去の事例―
戦争は突然始まるように見えても、実際には複数の要因が絡み合って進行し、武力行使という決断に至る。過去に典型的だった5つの構図を整理する。
① 誤算と同盟の連鎖(第一次世界大戦)
──小規模な事件が契機となり、締結された同盟義務が連鎖して多国間の軍事衝突へ転化した。
(参照:Norwich University Online “Six Causes of World War I”)
② 経済危機・不満の外敵転嫁(第二次世界大戦)
──深刻な経済不安が、外部の“敵”の設定を通じて拡張主義を正当化した。
(参照:Robert J. Gordon “Did Economics Cause World War II?” / NBER Working Paper)
③ 資源確保への焦燥と外交破綻(太平洋戦争)
──資源封鎖と南方資源地域確保の必要性が軍事行動を促した。
(参照:WorldHistory.org “The Causes of WWII”)
④ “自国民保護”を名目にした介入(例:ロシア・ジョージア戦争2008年)
──自国系住民の保護を根拠に武力介入が正当化された。
(参照:Central Asia–Caucasus Institute “Russia’s War in Georgia: Causes and Implications for Georgia and the World”)
⑤ 内戦から国際戦へ拡大(例:シリア内戦)
──内政問題に国際勢力が介入し、代理戦争化して長期化・複雑化した。
(参照:国際安全保障研究の一般的知見)
これらに共通するのは、「ひとつの大事件」ではなく、誤算/制度のずれ/敵設定/国内心理などが積み重なることで、いつしか戦争の階段を上がってしまうという点である。
さらに現在は、サイバー攻撃/情報戦/無人兵装/生活インフラへの干渉
といった形を伴う、“新しい戦争のあり方”が台頭している。
つまり、戦争のルールは更新され続けており、台湾海峡情勢を見る際にもその視点が不可欠だ。
「台湾有事」を描いた映像作品
2025年夏、台湾発の10話構成ドラマシリーズ 『零日攻擊 ZERO DAY』が配信を開始し、話題を呼んだ(出典:Reuters/JP Archive) 。この作品は、中国による台湾侵攻という仮想シナリオを描きながら、軍事衝突の瞬間だけでなく、「浸透工作」「フェイクニュース」「世論操作」といった“見えざる戦争”の側面に焦点を当てている(出典:amzn.co.jp) 。
映像作品のなかで描かれているのは、戦闘機の墜落、包囲網の構築、海上交通路の遮断、金融・物流の動揺といった“兵器・砲声”だけではない。むしろ日常の合間に差し込まれる情報操作、市民の恐怖、メディアの揺らぎが、戦争の足音を静かに近づけていく構図が丁寧に綴られている。
製作プロデューサー/脚本家の 鄭心媚(チェン・シンメイ)氏は、台湾の同胞がこうした「見えざる戦争」に対してあまりにも無感覚になっていることを懸念し、あえてこのテーマに挑んだという。彼女は本作の狙いについて、次のように語っている。
「いま、世界では浸透工作やフェイクニュースが身近なところに蔓延しています。すでに日本も同じ状況にあると思いますが、台湾はより深刻です。お互いが協力しあい、戦争が起こるリスクをいかに下げていくのか―そのことを、私たちはともに考えなければいけません」
この言葉は、遠くの地域の出来事として捉えられがちな「台湾有事」を、観る者自身の課題として描き直している。つまり、映像というフィクションを通じて、私たちは「他人事ではない選択」に直面しているのである。映画やドラマが醸成する疑問と緊張は、現実の安全保障構造に対する市民の“目”を研ぎ澄ませる契機となりうる。