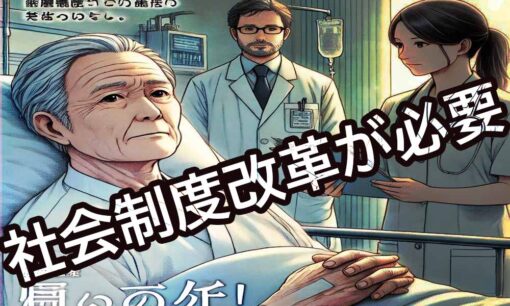SHIROは、廃棄予定だった店舗制服を天然素材で染め直し、一点物の制服として再生させる取り組みを始めた。北海道の悉皆屋・野口染舗と連携し、廃液などの未利用資源を活用した循環型アップサイクルの実践が動き出している。
廃棄予定の制服を天然染めで再生するSHIROの新プロジェクト
SHIROは、店舗スタッフが着古した制服を天然染料で染め直し、再び制服として生まれ変わらせる取り組みを開始した。広島ミナモア店で導入した藍染制服に続くプロジェクトで、倉庫に保管されていた廃棄予定の制服をアップサイクルし、世界に1枚だけの制服として再生する試みだ。
この染め直しには、北海道札幌市で染色・クリーニングを営む「野口染舗」と、天然染めブランド「BetulaN」を立ち上げた野口繁太郎氏が協力した。白樺やヨモギの蒸留廃液など、本来なら捨てられる素材を染料に活用し、7種類の天然素材を用いた染色を実現した。
すでに今年オープンした渋谷PARCO店では、スタッフが好みの色の再生制服を選んで着用している。他店舗でも順次導入される予定だ。
廃液・規格外素材・白樺の枝を活かす「7素材アップサイクル」の挑戦
今回のアップサイクルは、染色の領域でも前例の少ない挑戦となった。届いた制服には、油染みやメイク汚れが残っていたほか、生地にポリエステルが30%含まれており、天然染料が浸透しづらい特性があった。
通常であれば化学染料を用いる判断が妥当だが、SHIROの「自然素材を使い切る」という思想に共感した野口氏は、天然染料のみでの染め直しに踏み切った。約3カ月にわたり、クリーニング、下処理、濃度調整を繰り返し、白樺の枝やヨモギの廃液など未利用資源を染料に転換して濃度の高い発色を実現した。
野口氏は、これらの廃液を“宝”と表現した。視点を変えるだけで、廃棄物は価値ある資源へと生まれ変わる。その気づきこそ、本プロジェクトの独自性を象徴している。
着物文化の“循環思想”とSHIROの廃棄ゼロ宣言が重なり合う理由
着物の文化には、染め直し、仕立て直し、布の再利用、最後は灰にして染料の助剤とする循環の思想が根付いている。野口氏が長年向き合ってきた悉皆(しっかい)の営みには、資源の寿命を最大化するという日本の技が息づいている。
SHIROは2023年に「SHIRO 15年目の宣言」を掲げ、廃棄物ゼロを目指す循環型のものづくりへ舵を切った。ガラス容器の回収や衣類のリユースプロジェクトなど、既存資源の価値を見つめ直す取り組みを継続しており、今回の制服再生もその延長線上に位置付けられる。
循環の哲学を企業文化として定着させようとする姿勢は、単なる環境活動にとどまらず、ブランドの芯を形づくる役割を果たしている。
資源の再定義がブランド価値を高める“循環型ものづくり”の実装
SHIROの試みは、企業が保有する廃棄物や副産物を単なる負債として扱わず、クリエイティブを通じて価値に変換するモデルを示す。制服再生は、単に物を再利用するだけでなく、スタッフが「自分の色」を選べるという体験価値も生んでいる。
今後はワッペンやパッチワークなどの装飾を施し、制服ごとの個性をいっそう引き出す構想もあるという。循環を前提にしたものづくりは、地球環境への負荷を減らすだけでなく、ブランド体験そのものを豊かにする。資源を未来につなぐ視点が社会の新しい標準になり得ることを、SHIROは示し続けている。