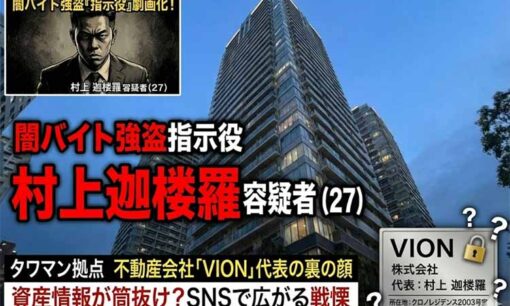中国政府が日本への渡航を控えるよう国民に求めた問題が、外交の枠を超えて議論を呼んでいる。
高市早苗首相の国会答弁を発端に日中関係の緊張が高まる中、元内閣官房参与で経済学者の高橋洋一氏は、自身のX(旧ツイッター)で“日本側にとっての思わぬ利点”を指摘した。
観光、治安、不動産、安全保障、多方面の課題が一気に可視化され、SNSでは賛否が交錯している。
高市首相の答弁が引き金に。外交の応酬は観光にも波及
この問題の起点となったのは、高市早苗首相が7日の衆院予算委員会で述べた「台湾有事は日本の存立危機事態となり得る」という答弁だ。中国側は即座に反発し、両国が互いの大使を呼び出して抗議する異例の事態に発展した。
やがて火種は観光分野へも飛び火する。
中国外務省は日本への渡航を当面控えるよう国民に呼びかけ、これが一気に拡散。
「渡航自粛」の二文字は、観光地、経済界、さらには一般の生活者まで巻き込む社会的議論へと広がっていった。
高橋洋一氏の“逆転の発想” 「むしろ日本にプラス」説
事態が注目を集める中、高橋洋一氏は17日、自身のXでこう投稿した。
「中国が中国人の日本渡航自粛を言い出したのはラッキー。オーバーツーリズム是正になるし、経営管理ビザ見直しや不動産規制もやり易くなる。このまま来ないと不動産没収かもWWW」
あえて“利点”に触れたこの投稿は大きな反響を呼び、
「その視点はなかった」「確かに今の混雑は異常」といった声が次々と寄せられた。
問題が外交から生活の実感へ、議論の軸が滑るように移動していく瞬間だった。
SNSのざわめき 空港の行列、観光地の混雑…生活者のリアルな声
渡航自粛が報じられた直後、SNSのタイムラインはざわつき始めた。
関西空港の国際線エリアで、巨大なスーツケースが連なり、荷物検査場の前では乗客が蛇行する列を作る。
係員の声が反響する中、ある投稿者はその光景を写真と共に投稿した。
「通路はぎっしり。7割が中国人観光客。渡航自粛は正直、助かるかもしれない」
投稿には瞬時に共感が集まり、
「渡りに船」「日本人が観光地へ戻れる」
といった肯定的なコメントが広がっていった。
京都の寺社や大阪の繁華街で、夜遅くまで観光客が行き交う光景を思い出しながら、
「一度落ち着いてほしい」とつぶやく人も多い。
しかし、反応はそれだけではない。
「中国国内の雇用悪化による若者の来日は続くだろう」
「誤った認識のまま訪日した旅行者がトラブルを起こす可能性の方が心配」
混雑のストレスだけでは語り切れない治安への不安が、コメント欄の深部で静かに膨らんでいた。
外交姿勢に対する期待と不安も交錯し、
「毅然とした対応が必要」
「感情的な応酬ではなく、冷静な外交こそ重要」
と意見が割れる様子が、SNS全体の緊張感をより際立たせていた。
インバウンド依存の転換点へ。観光・不動産・安全保障をつなぐ線
今回の渡航自粛は、インバウンド依存の影に隠れていた課題を照らし出した。
夕暮れの住宅街、古い木造家屋が突如リノベーションされ、知らない外国語の看板が掲げられている。
スーツケースの車輪が夜の路地に響き、周辺住民がそっとカーテンを閉める。そんな光景を目にしてきた人は少なくない。
SNSでは、
「外国人による不動産取得を厳しくすべき」
「民泊の急増で生活が変わった」
といった声があふれ、特にメガソーラーの設置や水源地周辺の土地買収問題は、安全保障の観点からも疑問視されている。
観光地では、コロナ後に急激に増えたインバウンドに押され、「日本人が観光地に行きづらくなった」という不満もあった。
今回の渡航自粛が長期化すれば、観光客の構成比が再び変わり、地元企業が日本人回帰へ舵を切る可能性もある。
外交上の配慮が必要な中で、生活者としての視点と安全保障としての視点が絡み合い、日本社会が抱える構造的な課題が一気に噴き出したかのようだ。
求められるのは「静かだが強い外交」
渡航自粛の呼びかけをめぐり、SNSには
「中国の方が困る」「日本は冷静でいい」
といった意見も見られる。
中国国内の若年層の雇用悪化、企業の東南アジア・インドへの生産移転。
国際関係の力学が大きく変わりつつある中、日本に求められるのは静かだが揺るぎない外交姿勢だ。
強硬すぎず、弱腰にもならず。高市首相の答弁から始まった今回の騒動は、
観光、治安、土地問題、経済安全保障など複数の課題を一度に照らし出した“警鐘”とも言える。
日本はどの領域を守り、どこを開き、どこを見直すのか。
その判断が、今後の日中関係にも日本の未来にも直結していく。
中国の渡航自粛呼びかけは、単なる外交的応酬にとどまらず、オーバーツーリズム、不動産取得、治安、経済安全保障、インバウンド依存の構造問題といった日本社会の深層まで揺さぶった。
高橋洋一氏の“逆転の視点”がどこまで現実になるかは未知数だが、今回の議論が日本の観光政策や受け入れ体制を見直す契機になるのは間違いない。