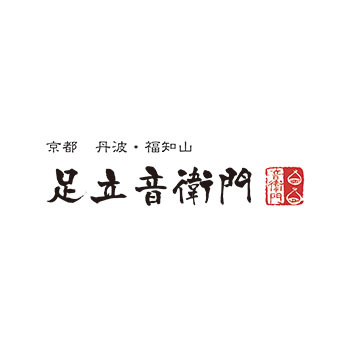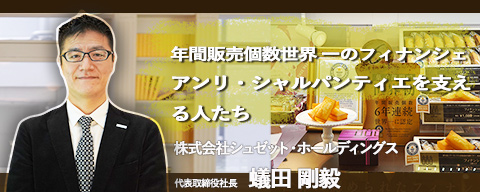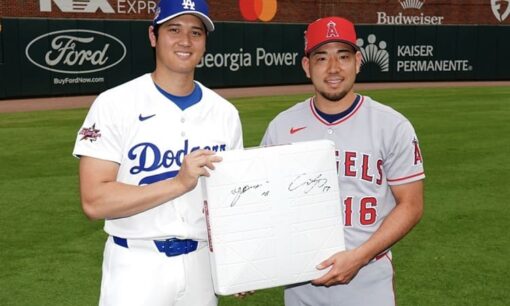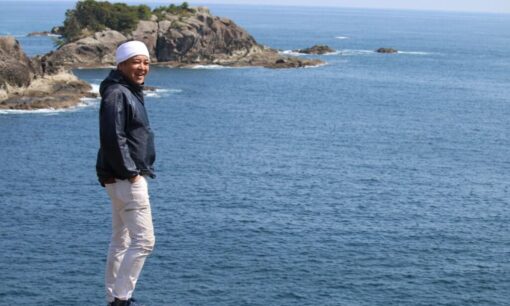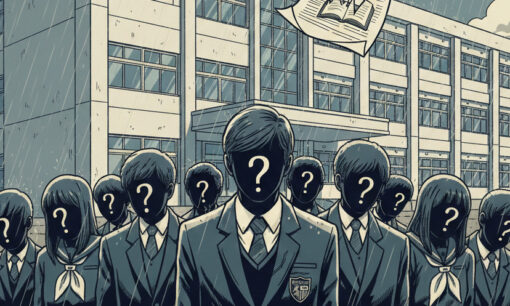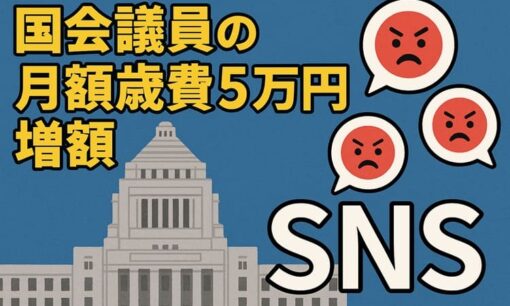京都・丹波の福知山城近くで、1本1万円の「栗のテリーヌ」で知られる菓子工房が、地域ぐるみの挑戦に踏み出している。株式会社足立音衛門。年商は約9億円(2025年10月期)、従業員はパートを含めて約130名。
京都市内の老舗和菓子とは少し距離を置きながら、丹波の里山で独自の道を歩む存在だ。営業部長の土田和典さんに話を聞いた。
栗のテリーヌで知られる地方発ブランド「足立音衛門」
足立音衛門の本店は、京都府福知山市、福知山城のほど近くに構える。丁寧に仕立てた焼き菓子を中心に、手作りのぬくもりと厳選素材にこだわる工房だ。
創業は平成3年(1991年)、代表の足立音衛門さんが、脱サラして小さなケーキ店を始めたことにさかのぼる。その後、現在の菓子づくりに軸足を移した。現社名で株式会社化したのは2005年だという。
現在は自社工房で菓子を製造し、本店とインターネット通販、さらに全国の百貨店約10店舗の売り場で販売している。定番として常時扱うアイテムは約80種類、開発済みの商品まで含めると200種類以上のレシピを抱える。
看板商品は、テレビ番組にもたびたび登場する栗のテリーヌ「天」だ。代表の足立氏は、かつてのインタビューでこう振り返っている。
「想定していたお客様は、正直言うと“自分”でした。こんな高いお菓子は誰も買わないだろうと思っていたのですが、面白がってお買い上げくださる方がこんなに多いとは、驚きの連続でした」
1本1万円超の価格帯にもかかわらず、評判は広がった。
2004年には関西ローカルの情報番組「ちちんぷいぷい」で和三盆糖を使ったシンプルなパウンドケーキ「音衛門のパウンドケーキ」が紹介され、一気に注文が殺到した。
足立氏は「2月末から4月、桜が散るころまで、コンクリートの床に寝袋を敷いて厨房で寝泊まりしながら作り続けた」と笑う。貧乏の淵から引き上げてもらった恩は、今も忘れていないという。
和三盆と丹波栗、原価率4~5割でも譲らないものづくり
足立音衛門の特徴は、素材への徹底したこだわりにある。
菓子づくりに使う砂糖ひとつとっても、最初期から「お砂糖を見直さなければいけない」と議論してきたという。代表が和菓子の世界で使われてきた和三盆糖に注目したのは20年以上前のことだ。
「当時、和三盆や抹茶は“和菓子の素材”であって、フランス菓子に使う人はいなかったんです。私たちは夏限定のわらび餅で使っていた和三盆を、洋風の焼き菓子に持ち込んだ。事象としてしか語れませんが、少なくとも私たちは20年以上前から和三盆をケーキに本気で使い始めていたと自負しています」
栗の使い方も徹底している。
「かつて『栗入り』といえば、小さな欠片が少し入っているか、フレーバーで香りづけする程度がほとんどでした。でも代表は、『バカじゃないか』と言われてもいいから、大きな栗がゴロゴロと入ったお菓子を作りたかった。そこから私たちの栗菓子が始まりました」

一般的な菓子店では、原材料費が売価の2~3割に収まるように設計することが多い。だが同社の栗のテリーヌは、栗とバター、和三盆などの原材料だけで4~5割に達するという。
「だから誰も真似しないんです」と土田氏は苦笑する。
「会社としてはずっと薄利です。お商売としてこれで本当に継続できるのかという課題は、ずっと抱えています」
それでも、機械化には安易に踏み込まない。家庭でも使うようなサイズのミキサーで、1回に仕込めるケーキはせいぜい30本。大手メーカーのように100本、200本と一気に仕込むことはしない。
「大きなミキサーで一気に生地を回すと、最初に流れ出る生地と最後に出る生地の状態がまったく違ってきます。大手さんはそこを切り捨てることもあるでしょう。でも、私たちは“家で作るお菓子の延長”でありたい。非効率でも、全部をきちんと形にして、お客様に届けたいんです」
社員の働き方についてもこう語る。
「パティシエだから休みが少なくて労働時間が長い、というのは雇う側の勝手な理屈です。人も原材料も高く買って、製品も高く販売できる会社だけが、これから生き残っていけるのではないかと考えています」
年商9億円の菓子屋が、文化財と廃校に踏み切った

足立音衛門の“無茶”は、原材料だけにとどまらない。会社の器=拠点づくりでも、大胆な一手を打ってきた。
まず2009年、福知山市内にある約800坪の福知山市内を整備したとされる旧土木建築商の邸宅を取得し、本店として改装した。この建物は現在、京都府の登録指定文化財となっている。
「従業員が30人ほど、年商が数千万円から3億円に届くかどうかという頃に、1億円の借入をして、その邸宅を購入しました。当時の年商を超える額の投資で、正直『何年で返せるんだろう』と、半分は楽しみ、半分は不安でした」
それでも、格式ある建物を本店に構えたことで、百貨店への出店交渉も前に進んでいる。
東京・日本橋三越への出店も、その延長線上に生まれたチャンスだという。田舎のちっぽけなケーキ屋と自嘲しながらも、都心の一等地で老舗ブランドと肩を並べる日々を、「毎日が勉強」と語る。
次の勝負は、さらに大きかった。
福知山市内の山あいでは、小中学校の統廃合が進み、すでに廃校となったもの、今後見込みのものも合わせて約20校とも言われていた。市としても活用策に頭を悩ませていたところへ、足立音衛門はその1校を丸ごと買い取る決断をする。
「商売としての年商が8億円くらいの頃に、小学校1校を丸ごと改装することにしました。改装費は合計で約4億円。ものづくり補助金として100万円だけお世話になりましたが、残りはほぼ金融機関からの借入です」
市街化調整区域にあるため、用途変更や各種申請が必要だった。
市議会でも議論が重ねられ、取得が決まったのは検討開始から約1年後。校舎ではなお児童が授業をしているさなかに、将来の活用を想像しながら教室を見て回ったという。
竣工を迎えたのは2021年秋。コロナ禍のさなか、かつての教室は菓子工房や倉庫、イベントスペースとして生まれ変わった。
卒業生が帰ってくる工房 里山とともに育つ“開かれた小学校”

廃校を拠点にしたことで、思いがけない効果も生まれている。
「一番大きいのは、人の歴史を受け継げたことだと思います」と土田氏は言う。
校舎をできる限り当時のまま残しているため、卒業生がふらりと立ち寄ることが日常になった。黒板や廊下、階段の軋みまで含めて、かつての記憶がそのまま残っている。
「通っていた方が、懐かしそうに校舎を眺めて『取り壊されなくて良かった』と言ってくださる。ここで働くスタッフの中にも、かつての卒業生が10人ほどいます。近所の方々も、車で数分の場所に新しい働き口ができたことで、空いた時間にパートとして来てくださるようになりました」
地域との関係は、雇用だけにとどまらない。地元の人々による朝市も開かれるようになった。もともとは午前中だけの開催だったが、弊社敷地内のイベント時には午後まで延長することも増えてきた。
「私たちが一方的に『こうしてほしい』とお願いするのではなく、お互いに『こういうことをしたいので協力し合いましょう』というスタンスでやっています。お互いにメリットがあって、お互いに“使える存在”でいようと話し合ってきました」
足立音衛門にとって、この廃校は単なる工場や物流拠点ではない。里山の暮らしと地元住民、そしてお菓子づくりを結びつける「開かれた小学校」そのものだ。
「お菓子はなくても生きていける」だからこそ、地方から届けたいもの
足立音衛門の理念を、土田氏はこう説明する。
「お菓子は、食べなくても生きてはいけます。ご飯をきちんと食べていれば、人は生きていける。でも、毎日の暮らしの中に、ほんの少しの幸せがあるとき、そのそばにはお菓子があってほしい。私たちのお菓子が、その役に立てたらいいなと思っています」
その幸せは、食べる人だけでなく、作る人にも向けられている。
「お菓子を作る会社が、地域の方々と一緒に豊かになっていく。そこで働く一人ひとりの社会性が育ち、個人としても豊かになっていく。地方にある小さな会社の小さな取り組みかもしれませんが、その積み重ねが地域全体を少しずつ豊かにしていくと信じています」
京都の老舗和菓子の世界から見れば、「変わり種の集団」に映るかもしれない。
丹波の山あいで、原価率4~5割の栗のテリーヌを焼き続け、廃校を丸ごと工房や店舗、自由に出入りできる公園に変え、里山の暮らしとともに歩む菓子屋がいる。
その存在を支えているのは、「自分の子どもに胸を張って食べさせられるお菓子を作る」という、驚くほどシンプルで頑固な信念である。