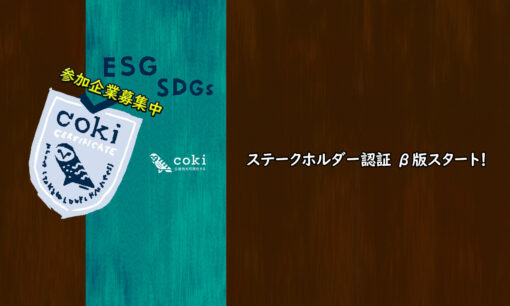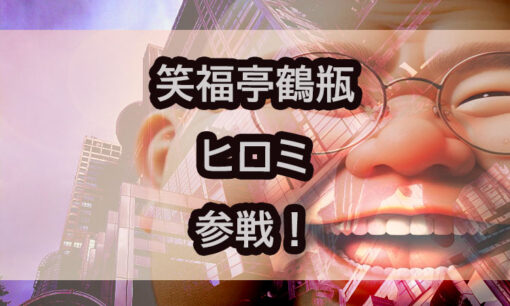産経新聞報道、吉村洋文知事、「赤旗」問題を再燃
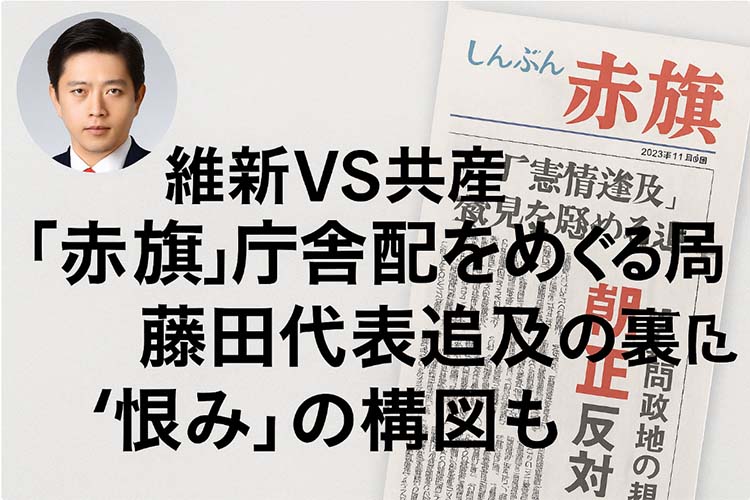
維新と共産党の機関紙「赤旗」との間で、いま全面戦争が起きている。きっかけは大阪府の吉村洋文知事がした10月末の発言だった。「共産党がそんなに政党助成金の返上が好きなら、庁舎で赤旗を売るのをやめたらどうですか」。赤旗をめぐる政党活動と税金の関係に、改めて火がついた。
この“赤旗問題”は今に始まったことではない。吉村氏は2019年にも同様の指摘を行い、「役所は税金で成り立つ公的空間。政党機関紙を庁舎で販売するのはおかしい」と警鐘を鳴らしていた。だがその後も自治体の現場では、地方議員による購読勧誘が続いているという。
「役所は税金で成り立つ公的空間。政党機関紙を庁舎で販売すること自体、常識的におかしい」 吉村氏は当時もそう述べていた。
「押し売り」と報じた産経新聞の衝撃
この問題が再び注目を集めたのは、10月30日付の産経新聞による報道だった。
「赤旗の押し売り」と題された記事は、日本共産党の地方議員による自治体職員への購読勧誘を「議員の立場を利用した押し売りにも等しい」と指摘。
記事によれば、東京都新宿区が実施した調査で、管理職115人のうち約8割が共産党議員から購読を勧められた経験があると回答。そのうち6割以上が心理的圧力を感じたとし、「断っても繰り返し勧誘を受けた」という声も複数あった。
神奈川県鎌倉市や千葉県市川市でも類似の証言が相次いでおり、産経は「全国の庁舎内での販売・勧誘禁止」を求める社説を掲載した。
現場職員が語る“黙示の圧力”
実際に、関東地方の市役所に勤務していた男性はこう語る。
「係長以上の職員は購読が事実上“必須”でした。断れば共産党議員から議会で所属部署に関する質問攻めを受け、重箱の隅をつつくような嫌がらせを受けました。日常業務に支障が出るほどで、事実上の“赤旗税”のようなものでした」
話を聞いた相手は一人であるため、これが全てに当てはまるとは言えないが、インタビューした相手の発言自体が産経の調査結果と重なり、政治的圧力の構図が“公然の秘密”として存在していた可能性を否定できない。
共産党「思想の自由への侵害」と猛反発
一方で、共産党側は強く反発している。党機関紙「しんぶん赤旗」は11月2日付の公式声明で、「『押し売り』の認識は産経の主観的決めつけにすぎない」としたうえで、「職員は自らの意思で購読している」と反論。
声明では、庁舎内勧誘禁止の動きが「統一協会や勝共連合系団体の影響を受けた反共キャンペーン」であるとまで主張し、産経新聞を「自民党の別動隊」と批判した。
さらに、「赤旗」は外国特派員協会の報道の自由賞を受賞していることを挙げ、「権力監視の報道機関としての存在意義を貶める攻撃だ」と強調した。
火種は維新と共産の長年の対立構図へ
大阪ではすでに、維新主導のもとで庁舎内の赤旗販売は中止されている。
それでも全国の自治体では、いまなお“慣行”として残るケースがある。維新の会は今後、国政でも庁舎内勧誘禁止の明文化を目指す構えなのだろうか。
一方、共産党は「報道の自由と政治活動の弾圧だ」と反発を強め、地方議会での維新批判を強化する方針を取るとみられる。
政治的な余韻 “恨み”の構図?
維新と共産の対立は、単なる制度論にとどまらない。
高市政権発足後、維新の藤田文武代表をめぐる「公金還流疑惑」報道で、共産系メディアや左派論客の追及が続いている。
ある政治関係者はこう語る。
「維新が役所での『赤旗販売』を問題視したことを、共産党は根に持っている。藤田代表への執拗な攻撃の背景には、その“恨み”があるのではないかと邪推したくもなりますね」
公的空間での言論と政治活動の線引きをめぐる論争は、いまや単なる庁舎問題を超え、政党間の対立を浮き彫りにしている。
赤旗が社会にはたしてきたスクープは数多くある。 媒体としての意義は大きいが、その体制の維持に、半強制的に購入を強いるような構造があったのだとしたら、ここらで改める必要があるのではないだろうか。