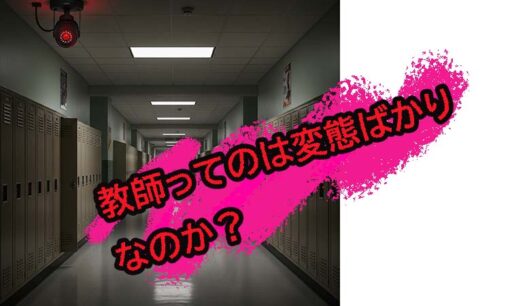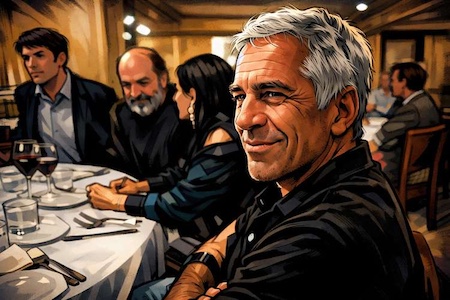ロンドンの秋の夜、荘厳なロイヤル・アルバート・ホールの前に「横綱」「大関」と書かれた幟がはためいた。
太鼓の音が鳴り響くと、観客の胸がざわめく。34年ぶりに開催された大相撲ロンドン公演。塩が宙を舞うたびに歓声が起こり、取組が終わっても観客は誰ひとり帰ろうとしなかった。
伝統の枠を超えた“SUMOフィーバー”は、文化の垣根を越えて、英国の心を揺さぶった。
ロイヤル・アルバート・ホールが「国技館」に変わった夜
1871年に建てられた英国を代表する音楽の殿堂が、この夜だけは異国の熱気に包まれた。
舞台上には土俵が築かれ、つり屋根が吊るされ、周囲には「ロンドン公演」「横綱」と書かれた幟。
「普段はオペラが鳴り響くホールが、まるで両国国技館のようだった」と現地記者は語る。
観客席では老夫婦が双眼鏡をのぞき、若者たちが力士の四股に歓声を上げる。
そこにあったのは、文化の違いを越えて“儀式”として受け止められた相撲の姿だった。
塩まきに喝采、弓取式に静寂。英国人が感じた“神聖さ”
力士が塩を投げる。ただそれだけで、場内がどよめいた。
「塩をまくだけで大歓声が起きた」と現地記者。
取組が終わっても観客は席を立たず、最後の弓取式を見届けるまでじっと見入っていたという。
「勝敗だけでなく、その奥にある精神性に注目していた。伝統を重んじる英国人らしさを感じた」。
スポーツを超え、神事に通じる“静と動の美”。
日本の形式美が、異国の観客に“神聖なるスポーツ”として届いた瞬間だった。
ロンドンに根づく相撲文化
今やロンドンには十数の相撲クラブがあり、定期的にトレーニングが行われている。
15歳のイングランド出身少年が日本の湊部屋で修行を始めたというニュースも話題だ。
背景には、琴欧州、把瑠都、安青錦らヨーロッパ出身力士の活躍がある。
YouTubeで相撲の魅力を知り、道場へ通う若者も増えている。
SNSには「#SUMOinLondon」「#Yokozuna」がトレンド入りし、日本発の伝統スポーツが新しいカルチャーとして受け入れられつつある。
“宇良フィーバー”が象徴する新しい相撲の形
土俵入りで「Ura!」と名前が響くと、ホール全体が揺れた。
英語アナウンスの後に「うらぁ!」と再び日本語の呼び声が重なる。
その瞬間、拍手と「Wowww!」の歓声が交錯した。
幕内の宇良は、試合後にロンドンの館内従業員からビールを差し入れられ、「最高ですね」と笑顔。
現地メディアも「宇良はロンドンで最も人気の力士」と評した。
SNSには「神聖で美しい」「黒紋付き姿が痺れる」とコメントが相次ぐ。
相撲が“力のぶつかり合い”を超え、“心を交わす文化交流”へと進化した夜だった。
パリへ続く相撲の旅
『BBC』は特集でこう報じた。
「力強さ、パワー、そして伝統と精神性。相撲のようなスポーツは他にない」
英紙『ガーディアン』も「高額なチケットが即完売」と報じ、熱狂を伝えた。
34年ぶりの英国公演は成功裏に幕を閉じ、来年6月にはパリ公演が予定されている。
相撲はいま、“日本の国技”から“世界の文化遺産”へと歩み出している。