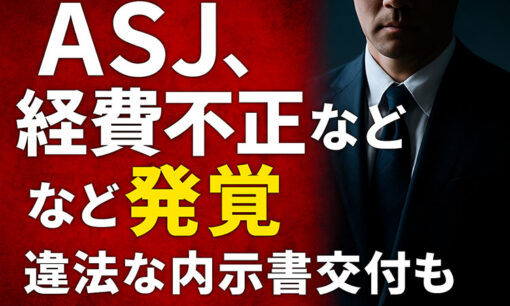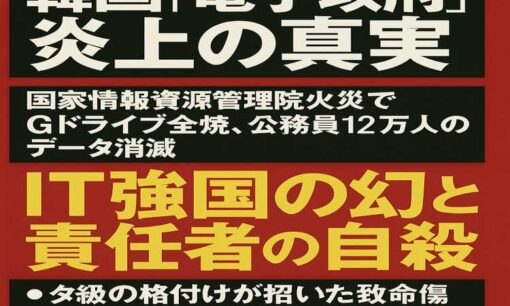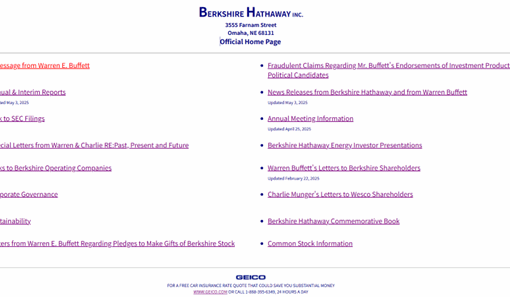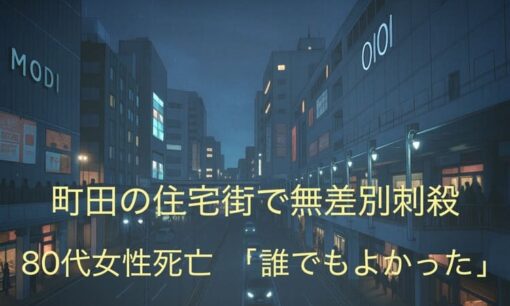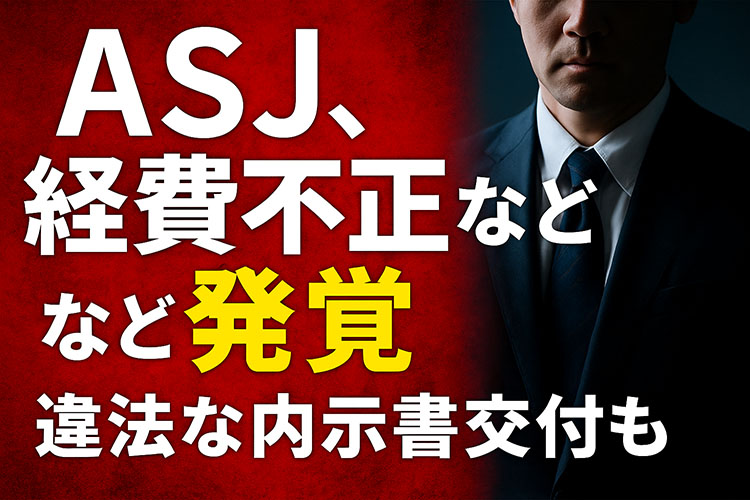
建築家ネットワーク事業を全国展開するアーキテクツ・スタジオ・ジャパン(ASJ)(東証グロース、6085)は、建築家と工務店、施主をつなぐ独自のプラットフォーム「ASJ建築家ネットワーク」を運営する企業。2007年の設立以来、住宅建築のマッチングを軸に業界内で一定の認知を築いてきたが、近年は「住まい」から「暮らし」まで事業領域を広げる構造転換を模索していた。
しかし、2020年3月期以降は6期連続の赤字に陥り、監査法人からは「継続企業の前提に重要な不確実性がある」と指摘される厳しい経営環境が続いていた。そのなかで今回発覚したのが、元社長による不正経費の私的利用と、取締役会決議を経ない違法な契約行為である。
金額自体は50万円と小さいが、上場企業としての信頼を揺るがす“公私混同”の象徴的事案といえる。
経費を虚偽申告、総額約50万円を不正流用
調査委員会によると、元・代表取締役社長、現取締役会長の丸山雄平氏は2022年6月から2024年9月までの間、福井県内の市役所関係者や組合幹部との会食費などとして経費を申告したが、実際には会食や業務活動の実態が存在しなかった。対象者本人もヒアリングで「すべて借名による虚偽申告だった」と認めており、虚偽の経費申告によって会社資金を流用していたことが確定した。
報告書では、不正経費として約50万円が実際に支払われたことを認定。さらに、調査過程で約400万円を超える疑わしい支出が新たに浮上しており、デジタルフォレンジック調査を継続しているとした。
丸山氏は「母が福井市で学生を支援するアートキャンプに協力しており、食費などを立て替えた」と弁明したが、委員会は「対象会社業務との関連性はなく、母の個人的支出である」と退けた。
「独断での内示書交付」も発覚 取締役会を経ずに発注を装う
さらに、調査報告書で明らかになったのは、丸山氏が2023年6月、上場企業A社の子会社B社に対し、取締役会決議を経ずに2450万円の亜臨界水反応装置の内示書を交付した事実である。ASJでは過去に一度も内示書を発行したことがなく、内部監査部が「取締役会承認が必要」と警告していたにもかかわらず、丸山氏は手続きを無視して発行を強行した。
内示書は、ASJが正式に発注する意思を示す文書であり、その金額は同社の純資産を上回る規模(約2億4500万円)。委員会は「会社法362条に定める重要な業務執行に該当するにもかかわらず、丸山氏の独断で違法に行われた」と断定した。
当該内示書を受けてA社側が「大型案件を受注した」と発表した結果、虚偽の適時開示につながった可能性も指摘されている。報告書では「丸山氏の行為は、社内外の信頼を著しく損なうもので、発注を装った不正行為である」と強調した。
特別背任罪の可能性も 「責任は重大」と結論
調査委員会は、不正経費申告について「会社法960条に定める特別背任罪に該当する可能性がある」と明記。虚偽の経費申請を未遂に終えた案件についても「未遂罪の構成要件を満たす」とした。報告書は「経費の多寡ではなく、企業統治を揺るがす悪質な行為である」と指摘し、丸山氏に深い反省や自省の欠如がみられると厳しく非難している。
再発防止へ、ASJがガバナンス強化策を提示
報告書の最終章では、再発防止に向けた提言として、以下の改革策を挙げた。
- 役員・管理職への定期的なコンプライアンス研修の義務化
- 役員経費の承認ルール明文化と現金清算の原則禁止
- 内部監査機能の強化と監査等委員会との連携
- 取締役会の議題設定ルールの見直しと社外取締役の増員
同社は「引き続きデジタルフォレンジック調査を行い、残る約400万円の疑いを含め全容解明に努める」とコメントしている。
経営再建への道のり
ASJは2007年の設立以来、建築家と施主をつなぐネットワーク事業を展開してきたが、2020年以降は6期連続赤字。監査法人から「継続企業の前提に重要な不確実性がある」との指摘を受けていた。今回の不正は、厳しい財務状況の中で経営体制の脆弱さを露呈する形となった。
同社は「株主および取引先に深くお詫び申し上げる」とコメント。今後は取締役会で丸山氏の解任議案を上程するかどうかを検討するとしている。
2025年11月4日記事修正