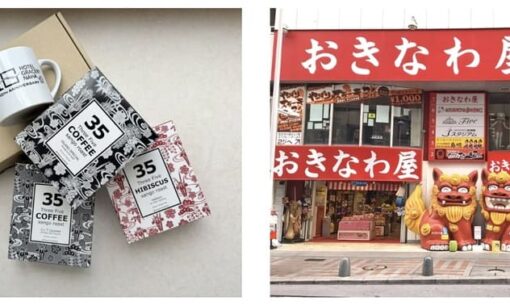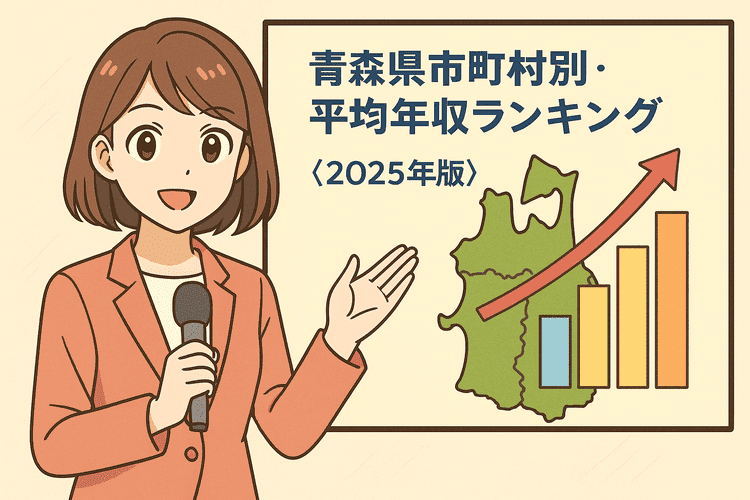
青森県は、農業や水産業といった一次産業に加え、観光、エネルギー、基地需要など地域ごとに特色ある産業構造を形成している。りんごやホタテなど全国的に名を馳せる産品の一方で、原子燃料サイクル施設や航空基地といった特殊要素が地域経済を支えているケースもある。本稿は nenshuu.netが公開する市町村別平均年収統計 と、青森県庁オープンデータ(2025年8月1日現在) の人口データを突合し、県内20自治体を対象に「平均年収」の最新ランキングをまとめたものである。ランキングを通じて、各自治体の産業基盤と暮らしの実像、さらに人口動態と税収の課題を浮き彫りにする。
20位 階上町|平均年収:280万4,474円
主な産業と経済構造
階上町は青森県南端に位置し、八戸都市圏(スクラム8)の一角としてベッドタウン的性格が強い。町域は山林と海岸線に囲まれ、農業では「階上早生そば」をはじめとした畜産や高原野菜の栽培が行われる。沿岸漁業も盛んで、ウニやたこ、いか、ワカメなどが代表的な水産資源である。一方で住民の通勤・就業先は八戸市内が多数を占め、町民の生活と経済活動は周辺都市との結びつきに依存している。産業構造としては一次産業の存在感を残しつつも、実態としては近隣都市への通勤就業が町の経済基盤となっている点が特徴である。
この町のリアル
人口12,394人(2025年8月1日現在)。町内にはスーパーや病院など基礎的な生活機能はあるものの規模は限られ、より高度な医療や大型商業は八戸市に依存する生活スタイルが一般的である。交通の便は自家用車利用が約9割とされ、公共交通の利用はわずか数%にとどまる。階上岳と太平洋の双方に近い地理環境から、登山や漁業体験など自然と共生する暮らしが身近にある。平均所得は県内下位に位置し、住民税収の絶対額は小さい。地方交付税への依存度が高い財政構造にあり、人口減少と高齢化が進むなかで定住人口の確保と持続可能な産業育成が課題となっている。
19位 東北町|平均年収:284万8,356円
主な産業と経済構造
東北町は小川原湖の南岸に位置し、淡水資源と農畜産業を基盤とする町である。湖では大和しじみをはじめシラウオやワカサギなどの漁業資源が知られ、特産としてブランド化が進められている。農業では稲作のほか、ながいも・にんにく・ごぼうといった根菜類や畜産が盛んで、青森県内でも食料供給の拠点としての役割を担う。近隣の三沢市や十和田市、七戸町との結びつきが強く、青い森鉄道沿線の通勤利用や周辺都市への就業も多い。湖を核とした観光やレジャー利用も一定の存在感を持ち、地域経済は一次産業と近隣都市圏への通勤依存の両輪で成り立っている。
この町のリアル
人口15,826人(2025年8月1日現在)。町域は小川原湖と田園に囲まれ、自然環境に恵まれた静かな暮らしが営まれている。日常の移動手段は自家用車が中心で、公共交通の利用は限定的である。高度な商業施設や医療機能は三沢市や十和田市など周辺都市に依存する傾向が強い。平均所得は県平均をやや下回っており、人口規模も大きくないため、住民税収の絶対額は相対的に小さい。町の財政基盤は厚みを欠きやすく、人口減少と高齢化が進むなかで、地域資源を活かした産業振興と定住促進が今後の課題となっている。
18位 五所川原市|平均年収:286万3,312円
主な産業と経済構造
五所川原市は津軽平野の中核で、稲作比重が高い水田地帯に果樹(りんご)が広がる。市の水田は主食用米・飼料用米を中心に作付が進み、作付の約7割超を水稲が占める。市街地はJR五能線・津軽鉄道・バスが集まる交通結節点で、つがる総合病院や「立佞武多の館」など公共・観光機能も集積する。工業団地には果汁・果肉製品を手がける食品加工企業の立地が見られ、農・食と製造が連動する地域構造が特徴だ。
この町のリアル
人口49,213人(2025年8月1日現在)。市街地に商業・医療・行政機能がまとまり、周辺町村の生活拠点としての役割を担う。人口規模に裏付けられた住民税収が比較的安定感をもたらす一方、県全体の人口減・高齢化の影響は免れず、都市機能の維持と産業の稼ぐ力の強化が課題となる。
17位 七戸町|平均年収:287万8,700円
主な産業と経済構造
七戸町は上北郡に属し、広い農地と畜産業を基盤とする農業の町である。水稲に加え、にんにく・ながいもなど青森県を代表する畑作物の栽培が行われ、乳牛・肉牛の畜産も盛んである。工業団地も立地するが産業構造は農畜産が中心で、地域の雇用や所得の根幹を支えている。2010年に開業した東北新幹線七戸十和田駅によって、首都圏や仙台方面とのアクセスが飛躍的に改善され、観光や交流人口の拡大につながった。新幹線駅周辺では宿泊施設や飲食店などサービス業の展開もみられ、町経済の裾野を広げている。
この町のリアル
人口13,814人(2025年8月1日現在)。町域は山林と田園が広がり、自然環境を身近に感じられる暮らしが営まれている。移動は自家用車が基本で、日常の買い物や医療は町内と十和田市など周辺都市を使い分ける傾向が強い。公共交通は新幹線駅や路線バスがあるものの利用範囲は限られており、車依存の生活構造が色濃い。人口減少や高齢化が進行する中で、農業と観光資源を活かした地域振興や定住促進が今後の課題となっている。
16位 横浜町|平均年収:289万5,884円
主な産業と経済構造
横浜町は下北半島の太平洋側に位置し、農業と漁業を基盤にしている。特に全国有数の菜の花栽培地として知られ、毎年5月に「菜の花フェスティバル」が開催されるなど観光資源とも結びついている。水産業ではホタテやナマコ、カレイを中心とした沿岸漁業が営まれ、町の基幹産業の一つとなっている。加えて、風力発電設備も整備されており、再生可能エネルギー関連の取り組みも進められている。小規模ながら農漁業と観光、再エネの複合構造で地域経済を支えているのが特徴である。
この町のリアル
人口3,988人(2025年8月1日現在)。小規模町であり、少子高齢化と人口減少が顕著に進む。町内には基礎的な生活機能が備わるが、大規模商業や専門医療はむつ市や野辺地町に依存する生活スタイルが一般的である。観光シーズンには菜の花畑が一面に広がり、交流人口の拡大につながる一方、平常時の税収規模は人口の少なさから総額で限られる。持続可能な財政運営のためには、農漁業資源の高付加価値化と再生エネルギー関連産業の育成が今後の課題となっている。
15位 野辺地町|平均年収:294万3,856円
主な産業と経済構造
野辺地町は陸奥湾の湾奥に位置し、古くから港町として発展してきた。基幹産業は農業と水産業で、稲作や野菜栽培に加え、ホタテ養殖が盛んに行われている。陸奥湾は日本有数のホタテ養殖地であり、野辺地町もその一翼を担う。林業も一定の役割を果たし、山間部から木材資源が供給される。近年は港湾機能を活かした流通・物流の拠点性も持ち、町の経済は農林水産業と港を軸とする複合型の産業構造を形成している。
この町のリアル
人口11,703人(2025年8月1日現在)。町の中心部に商業施設や医療機関、行政機能が集まっており、周辺地域からの生活利用も受け止めている。小規模ながら日常生活に必要な機能は揃っており、移動は自家用車中心である。人口規模は限られるが、平均年収は県平均をやや上回る水準で、住民税収は町財政の安定に一定の寄与をしている。ただし長期的には人口減少と高齢化が進んでおり、産業振興と若年層の定住促進が課題となっている。
14位 外ヶ浜町|平均年収:295万6,727円
主な産業と経済構造
外ヶ浜町は津軽半島の東岸に位置し、津軽海峡に面する港町である。基幹産業は漁業で、ホタテ・アイナメ・タコなど多様な水産資源が漁獲・出荷されている。これらは県内外へ流通し、町の主要な収入源となっている。また、観光も大きな柱で、青函トンネル記念館や竜飛崎、さらには津軽海峡を望む自然景観が観光客を引きつけている。農業は小規模ながら一部で水稲や野菜が営まれ、地域の自給的な役割を担っている。
この町のリアル
人口4,885人(2025年8月1日現在)。冬季は日本海側特有の荒天が続き、交通や日常生活が制約される。町内には小規模ながら生活に必要な機能は備わっているが、医療や大型商業は青森市に依存する部分が大きい。人口が少ないため住民税収入の総額は限られ、町財政は地方交付税に依存せざるを得ない構造となっている。観光シーズンには観光客で賑わうものの、恒常的な人口減少と高齢化が進んでおり、産業振興と生活基盤の維持が課題となっている。
13位 六戸町|平均年収:297万6,481円
主な産業と経済構造
六戸町は青森県上北郡に位置し、農畜産と周辺都市圏への通勤就業が共存する。農業はながいも・にんにく・ごぼうなどの畑作が中心で、特にごぼうは県内でも有数の作付面積を持つ主要作物のひとつとなっている。畜産では肉用牛の飼養も行われており、農業全般が町の経済を支える基盤を形成している。また、三沢市や八戸市に近い立地から工業団地が整備され、自動車部品関連をはじめとする製造業や物流業の立地もみられる。農業と工業の二本柱に加え、通勤圏としての性格が強く、町の就業構造は多様化している。
この町のリアル
人口10,473人(2025年8月1日現在)。三沢市のベッドタウンとして住宅地の開発が進み、町内には新興住宅地が形成されている。移動は自家用車中心で、日常の買い物や医療は町内施設に加えて三沢市・八戸市を利用するケースが多い。農業の基盤を残しつつ、周辺都市への通勤就業が家計を支える現実があり、暮らしは都市圏との結びつきが濃い。人口減少や高齢化といった課題はあるが、住宅需要の受け皿として一定の人口規模を維持している。
12位 十和田市|平均年収:301万5,891円
主な産業と経済構造
十和田市は農畜産と食品関連、商業・医療がバランスする地方中核都市である。農業は稲作に加え、畑作・畜産が並立し、市の公式資料でも農林畜産を基盤とする地域像が示される。市街地には総合病院の十和田市立中央病院が立地し、上十三医療圏の中核的役割を担う。都市構造面では、官公庁が並ぶシンボルロード「官庁街通り」が街の骨格を形づくり、日本の道100選に選定。さらに十和田市現代美術館と一体で展開する「Arts Towada」により、中心市街地の文化・観光機能が強化され、飲食や来街者消費を呼び込んでいる。
この町のリアル
人口56,886人(2025年8月1日現在)。中心市街地には官庁街通りや美術館、カフェ・飲食店が点在し、文化施設と日常の商業機能が近接している。医療面は十和田市立中央病院を核に地域の基礎的医療が確保され、周辺町村の生活圏も受け止める。交通は自家用車利用が主流だが、観光では奥入瀬渓流・十和田湖方面への来訪とあわせた回遊もみられる。暮らしの利便性と自然・文化資源の近さが同居するのが十和田らしさだ。
11位 佐井村|平均年収:302万7,908円
主な産業と経済構造
佐井村は下北半島の北西端に位置し、津軽海峡に面する良好な漁場を持つ。基幹産業は漁業で、ヤリイカ・ヒラメ・タラなど多様な水産資源を背景に、漁獲と加工が村の経済を支えている。特に「仏ヶ浦」や「津軽海峡文化館アルサス」を中心とした観光資源があり、観光シーズンには飲食・宿泊などのサービス業も賑わいを見せる。近年は漁業者の高齢化や資源管理が課題とされるが、地域資源を活かした観光との複合で経済基盤を維持している。
この町のリアル
人口1,588人(2025年8月1日現在)。県内でも最小規模の自治体のひとつで、少子高齢化と人口減少が深刻に進んでいる。日常生活では基礎的な行政・商業機能はあるものの、専門医療や大型商業はむつ市など周辺都市に依存する。税収総額は極めて小さく、村財政は地方交付税に強く依存している。観光期には仏ヶ浦などへの観光客が交流人口を押し上げるが、平常時は静かな漁村の姿を保っている。
10位 おいらせ町|平均年収:306万783円
主な産業と経済構造
おいらせ町は上北郡に属し、三沢市と八戸市の中間に位置する立地特性から、通勤圏としての性格が強い。町の南部には住宅地が広がり、ベッドタウンとして人口が増加傾向を示してきた。一方で、町域には水田や畑地も残り、稲作や畑作(大根・にんじん・山芋、ごぼう等)が営まれている。農業協同組合(JAおいらせ)を中心に、地域ブランドの確立や農畜産物の販路拡大が進められている。商業面では大型ショッピングセンター「下田イオンモール」が立地し、周辺市町村からの購買需要を吸収している点も町の経済的な特色である。
この町のリアル
人口24,995人(2025年8月1日現在)。新興住宅地が増加し、若年層や子育て世帯が多く居住している。生活利便性は高く、日常の買い物や医療は町内で完結できるほか、三沢市・八戸市との広域的な生活圏を形成している。移動は自家用車中心で、鉄道利用は青い森鉄道線の下田駅が拠点。税収規模は人口規模の裏付けがあり、町の財政基盤は比較的堅調である。
9位 青森市|平均年収:312万783円
主な産業と経済構造
青森市は青森県の県庁所在地であり、行政・医療・教育が集積する県都機能を担っている。市内には県庁や各種行政機関、大学・専門学校、総合病院が立地し、公共サービスと高次都市機能が集中している。さらに、青森駅周辺の再開発や「アウガ」跡地活用など中心市街地整備が進み、商業・小売・流通の拠点性を強めている。青森港は青函連絡の要衝で、青森湾フェリー航路をはじめとした物流・観光の玄関口としても機能する。観光ではねぶた祭をはじめとした伝統行事が世界的に知られ、交流人口の拡大を後押ししている。
この町のリアル
人口260,562人(2025年8月1日現在)。県内最大の都市であり、日常生活に必要な商業・医療・文化機能をほぼ自足できる環境が整う。周辺市町村からの通勤・通学需要も取り込み、広域都市圏を形成している。冬季は積雪寒冷地ならではの生活負担がある一方で、公共交通網や都市機能は県内で最も整備されている。人口規模と高めの平均所得を背景に、県内で最大級の税収基盤を誇るが、人口減少と高齢化は着実に進行しており、持続可能な都市経営が課題である。
8位 むつ市|平均年収:314万5,659円
主な産業と経済構造
むつ市は下北半島の中心都市で、広大な市域を持つ。産業の柱は公共部門とエネルギー関連、そして漁業・林業である。市内には海上自衛隊大湊地区総監部が置かれ、関連施設や隊員の消費が地域経済に影響を与えている。さらに、東通原子力発電所や使用済燃料再処理関連の拠点が立地し、エネルギー産業が地域経済の一角を担う。漁業では陸奥湾や津軽海峡を舞台にホタテやイカなどが水揚げされ、林業も豊かな森林資源を活かして行われている。観光面では恐山や釜臥山展望台など自然・文化資源が多く、観光客を呼び込む要素にもなっている。
この町のリアル
人口50,758人(2025年8月1日現在)。下北地方の行政・経済の拠点として周辺自治体からの通勤・通学需要を吸収している。市域は広大で、市街地と周辺農漁村地域との生活環境の差が大きい。日常の生活基盤は市街地で充足するが、周辺部では車依存の生活が中心となる。平均所得は県内でも高めで、人口規模の裏付けと合わせて税収基盤は下北地方の中で際立っており、財政面では安定性が高い。
7位 弘前市|平均年収:316万5,329円
主な産業と経済構造
弘前市は津軽地方の中心都市であり、日本一のりんご産地として全国的に知られている。りんご栽培は市の農業の基盤であり、関連する食品加工業(ジュース・菓子など)が集積している。また、弘前城や弘前公園の桜まつりをはじめとする観光資源が豊富で、国内外から観光客を呼び込んでいる。教育面では弘前大学を擁し、地域の高等教育・研究の拠点としての役割を果たすほか、医療機能も県西部を支える中核的存在である。農業・観光・教育・医療が並立する複合型の産業構造が特徴だ。
この町のリアル
人口157,963人(2025年8月1日現在)。県西部の中核都市として、周辺市町村からの通勤・通学や購買需要を受け止めている。中心市街地には商業施設や文化施設が集まり、生活利便性が高い一方で、郊外には広大なりんご畑が広がり農業の存在感も強い。観光シーズンには桜やりんご関連イベントで交流人口が急増する。人口規模と高めの平均所得に支えられ、税収は県内でも上位の安定感を持つが、人口減少と空き家増加など都市課題も顕在化している。
6位 八戸市|平均年収:317万1,175円
主な産業と経済構造
八戸市は太平洋に面した港湾都市で、古くから水産業の拠点として発展してきた。八戸港は全国有数の水揚げ量を誇り、サバやイカ、イワシを中心とした漁業と加工業が地域経済を支えている。さらに臨海工業地帯には鉄鋼・化学・製紙など多様な製造業が立地し、港湾を基盤とした流通・物流機能と一体で発展している。東北新幹線や自動車道も整備され、東北南部や首都圏とのアクセス性が高いことから、青森県南部の経済中核として位置づけられている。
この町のリアル
人口212,988人(2025年8月1日現在)。市街地には百貨店や大型商業施設、医療機関、文化施設が集積し、生活利便性が高い。周辺市町村からの通勤・通学も受け入れており、南部地方の広域都市圏を形成している。県内では青森市に次ぐ規模の都市で、平均所得と人口規模を兼ね備えた税収力は県内屈指である。一方で、少子高齢化と産業構造の変化に対応しながら、持続的な都市経営が課題となっている。
5位 東通村|平均年収:317万5,737円
主な産業と経済構造
東通村は下北半島の北東部に位置し、発電関連施設や再生可能エネルギーの導入が進む自治体である。村内には東通原子力発電所が立地しており、地域経済に大きな影響を与えてきた。また、近年は風力発電設備の整備が進み、再生可能エネルギー分野の比重が高まりつつある。沿岸漁業ではサケ、ヒラメ、コンブなどの水産資源が漁獲され、農業では畑作や酪農が営まれ、一次産業も依然として地域を支える基盤を形成している。エネルギー関連と農漁業の複合的な産業構造が特徴である。
この町のリアル
人口5,439人(2025年8月1日現在)。小規模自治体でありながら、発電関連の存在によって一人あたりの所得水準は県内でも高い部類に入る。とはいえ、人口規模が限られるため住民税収入の総額は大きくなく、財政運営には地方交付税や発電関連交付金への依存も見られる。日常生活は自家用車に依存し、買い物や医療の一部はむつ市や六ヶ所村など周辺自治体に頼る傾向がある。
4位 平内町|平均年収:322万4,281円
主な産業と経済構造
平内町は青森市の東隣、陸奥湾に面する町である。基幹産業は水産業と農業で、特にホタテ養殖は全国的にも知られており、陸奥湾は日本一のホタテ生産地のひとつに数えられる。町内では陸奥湾の豊富な水産資源を活かした養殖・出荷が盛んで、加工業も付随して展開している。農業では水稲や野菜栽培が営まれ、都市近郊型農業として県都・青森市の市場にも供給される。漁業と農業の両輪が町の経済を支えるとともに、観光面では「ほたて広場」など地元資源を活かした取り組みもみられる。
この町のリアル
人口9,621人(2025年8月1日現在)。小規模町ながら、所得水準は県平均を大きく上回る水準にあり、税収基盤は比較的安定している。生活は自家用車中心で、日常の商業や医療の一部は青森市を利用する住民も多い。町内にはホタテを活かした観光拠点や直売施設があり、交流人口の拡大にもつながっている。一方で人口減少と高齢化は顕著であり、基幹産業の持続性と地域振興策が今後の大きな課題である。
3位 大間町|平均年収:329万9,065円
主な産業と経済構造
大間町は下北半島の北端に位置し、全国的に知られる「大間まぐろ」の産地として名高い。津軽海峡の好漁場に恵まれ、クロマグロ漁を主軸に漁業が展開されている。一本釣りで水揚げされる大間まぐろはブランド価値が高く、首都圏市場を中心に高値で取引され、地域経済に大きく寄与している。漁業関連の加工・流通業も派生し、観光面でも「まぐろ一本釣り体験」やイベントを通じて交流人口の増加につながっている。町の経済は水産業を核としながら、観光・流通へ波及効果を広げているのが特徴である。
この町のリアル
人口4,592人(2025年8月1日現在)。県内でも小規模自治体に属するが、全国的な知名度を持つ「大間まぐろ」により高い平均所得を実現している。税収総額は人口規模が小さいため大きくはないが、ブランド力を背景に外部資金の流入が期待できる点が強みとなる。生活は自家用車依存が中心で、専門的な医療や商業はむつ市に依存する面がある。一方で観光期には交流人口が増え、漁業と観光が一体となった地域経済を形づくっている。
2位 三沢市|平均年収:333万9,815円
主な産業と経済構造
三沢市は上北地域の中核都市で、米軍三沢基地と航空自衛隊三沢基地を擁する航空都市である。基地関連の雇用・需要が地域経済を大きく支え、所得水準を押し上げている。また、基地と連動した公共部門やサービス業が厚く、飲食・小売・住宅など多様な業種が展開している。農業では水田や畑作に加え、酪農も営まれており、都市機能と農業基盤が併存するのが特徴である。観光分野では航空祭や航空科学館などが集客力を持ち、地域の交流人口を拡大している。
この町のリアル
人口37,044人(2025年8月1日現在)。米軍基地の存在から外国人居住者が多く、多文化的な環境が根づいている。市街地には商業・医療・教育施設がまとまり、生活の利便性が高い。所得水準と人口規模の双方を備え、青森県内でも比較的安定した税収基盤を有する自治体の一つである。
1位 六ヶ所村|平均年収:352万2,983円
主な産業と経済構造
六ヶ所村は上北郡に属し、原子燃料サイクル関連施設が立地する全国的にも特殊な性格を持つ自治体である。核燃料再処理工場やウラン濃縮工場、使用済み燃料貯蔵施設などが集積し、雇用と所得を押し上げている。これら原子力関連施設は村の基幹産業となり、関連事業者の立地や工事需要も村経済を下支えする。加えて、風力発電など再生可能エネルギーの導入も進められており、エネルギー関連が地域経済の中心を形成している。
この町のリアル
人口9,585人(2025年8月1日現在)。平均年収は県内トップで、住民税収入も村の規模からみて厚みがある。さらに、公共投資や原子力関連交付金の効果も加わり、財政面の潤いは青森県内でも際立っている。生活は自家用車が前提で、大規模商業や高度医療は三沢市や八戸市に依存する部分が多い。少子高齢化の進行は課題だが、豊富な財源を活かした地域振興の余地が大きい自治体である。
総評
青森県全体の総人口は 1,147,374人(2025年8月1日現在、青森県庁オープンデータ)。出生者数は 410人、死亡者数は 1,589人、人口増減数は ▲1,179人 と、自然減の傾向が顕著である。平均年収ランキング上位の自治体では、エネルギー関連や基地需要など特殊な産業要素が所得水準を押し上げている一方、農漁業を基盤とする町村は人口減少や高齢化が進み、税収基盤の脆弱さが課題となっている。今後は、地域ごとの強みを活かしつつ、人口減少に対応した持続可能なまちづくりが求められる。