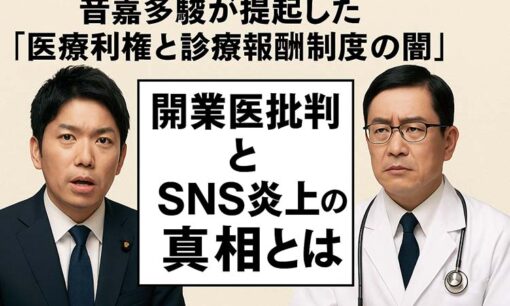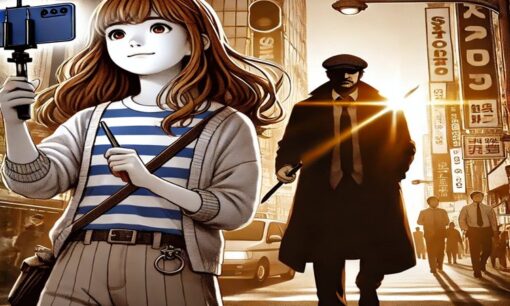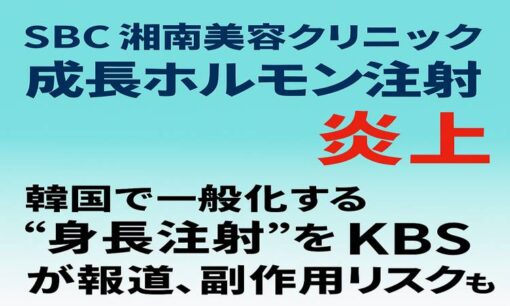化粧品会社「ディー・アップ」に勤務していた新入社員の女性が社長によるパワーハラスメントを苦に自殺した問題で、東京地裁は同社側に1億5千万円の調停金の支払いを決定した。異例の内容として社長の辞任も盛り込まれており、調停はすでに確定している。
命を奪ったパワハラの実態:新入社員を追い詰めた叱責
東京都港区に本社を置く化粧品メーカー、ディー・アップに2021年4月に新卒で入社した里実さん(当時25歳、名字は非公表)の人生は、わずか8カ月後に大きく暗転することとなる。遺族側の代理人弁護士によると、里実さんは同年12月、同僚との業務上の小さなトラブルがきっかけとなり、坂井満社長に呼び出された。
面談は長時間に及び、その場で坂井社長は里実さんに対し「大人をなめるなよ」「会社をなめるな」などと一方的に叱責を繰り返したという。さらに、別の報道記事によると「お前、世の中でいう野良犬っていうんだよ」「力のない犬ほどほえる」といった、人格を否定するような言葉も浴びせられた。約50分間にわたる一方的な叱責と侮辱的な言動は、真面目に仕事に取り組んでいた里実さんの心を深く傷つけた。
このパワハラを機に、里実さんの精神状態は悪化し、翌2022年1月には医師からうつ病と診断され、やむなく休職することとなった。しかし、休職期間が満了した2022年8月、里実さんは自殺を図り、意識が戻ることなく、約1年後の2023年10月に息を引き取った。入社からわずか2年半でのあまりにも早すぎる死であった。
労働基準監督署も認定したパワハラとの因果関係
里実さんの死後、遺族は坂井社長によるパワハラと里実さんの死亡との因果関係を証明するため、労働基準監督署に労災申請を行った。そして2024年5月、労働基準監督署は遺族の主張を認め、坂井社長のパワハラが里実さんの自殺につながったとの因果関係を正式に認定した。これは、企業におけるパワハラが個人の命を奪うという深刻な結果をもたらす可能性があることを公的に認めるものであり、極めて重い判断といえる。
労基署の認定を受け、遺族は会社と坂井社長に対し損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。裁判は当事者双方の合意による解決を目指す民事調停の手続きに移行し、話し合いが進められていた。遺族側は、金銭的な賠償だけでなく、坂井社長による直接の謝罪と、会社がパワハラが自殺の原因であることを公式に認めることを強く求めていた。
異例の調停成立:1億5千万円支払いと社長退任
そして2025年9月9日、東京地裁の松下絵美裁判官は、民事調停における決定を下した。その内容は、遺族の主張がほぼ全面的に認められるものであった。
決定によると、化粧品会社ディー・アップは里実さんの遺族に対し、調停金として1億5千万円を支払う。さらに、会社側は坂井社長のパワハラが里実さんの自殺につながったことを正式に認め、遺族に心からの謝罪をすることも義務付けられた。特筆すべきは、今回の調停決定に、坂井社長が辞任するという異例の措置が盛り込まれた点である。
通常、民事調停は当事者間の話し合いによる合意で成立することがほとんどであり、社長の辞任までが盛り込まれることは極めて珍しい。これは、パワハラが個人の人権を深く侵害し、生命を脅かす行為であるという社会的認識の高まりを反映したものだと考えられる。
この決定は双方が異議申し立てをせず、すでに確定している。坂井社長は決定の翌日である10日付で退任したことを、ディー・アップ社も公式に認めた。
遺族の悲痛な思いと社会への切なる願い
決定が下された翌日、遺族側の代理人弁護士は記者会見を開き、調停成立の経緯を説明した。そこには、深い悲しみと怒りを抱えながらも、里実さんの名誉を回復させ、二度とこのような悲劇が起きないことを願う、遺族の切実な思いがあった。
里実さんの母親は、里実さんが「全力で人を愛し、優しく、周囲を笑顔にしてくれる存在でした」と、生前の姿を振り返りながらコメントを寄せた。「目の前から娘がいなくなってしまったことを、今でも信じることができません」と語るその言葉は、娘を失った母親の底知れない悲しみを物語っていた。母親は、新入社員やこれから社会に出る若者たちのために、安全で職場環境の良い会社が増えることを心から願っていると述べた。
また、里実さんの姉は「生きている間に社長に謝ってほしかったです」と会見で声を震わせた。里実さんがどれほど頑張り屋で、好きなことに一生懸命だったかを語り、「頑張っている人を潰すようなことはやめてほしいし、温かく見守る社会になってほしいです」と訴えた。この姉の言葉は、企業だけでなく社会全体に対し、過度な競争やプレッシャーの中で孤立する若者たちに目を向けてほしいというメッセージだと受け取れる。
信頼回復に向けた会社の対応と今後の課題
今回の決定を受け、ディー・アップ社は会社のホームページにコメントを発表した。「亡くなられた元従業員とご遺族に対して衷心よりおわび申し上げます」と謝罪し、10日付で坂井社長が退任したことを正式に明らかにした。
さらに、再発防止に向けた具体的な取り組みについても言及した。ハラスメント防止規定の見直し、管理職を含む全社員向けの研修の実施、社外の相談・通報窓口の開設など、社内体制や職場環境の改善に全力で取り組む姿勢を示している。
これらの措置は、パワハラを根絶し、健全な組織風土を醸成するための第一歩として評価されるべきものである。しかし、失われた命は二度と戻らない。同社が社会的信頼を回復するには、今回の事件を風化させることなく、全社一丸となって、言葉だけでなく行動で真摯な姿勢を示し続けることが求められる。
今回の調停決定は、企業におけるパワハラの責任を明確にした事例であり、今後、同様の事案が発生した場合の大きな指針となるだろう。企業には、個人の尊厳を守るため、ハラスメントに対するより厳格な姿勢が求められている。
参照:新体制及び代表取締役の交代について(ディー・アップ)