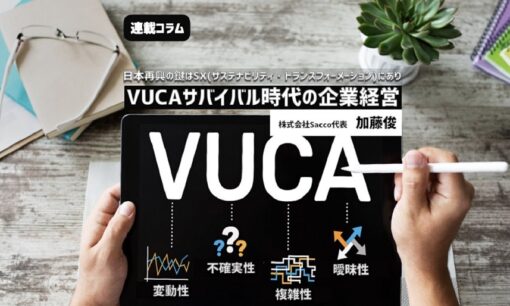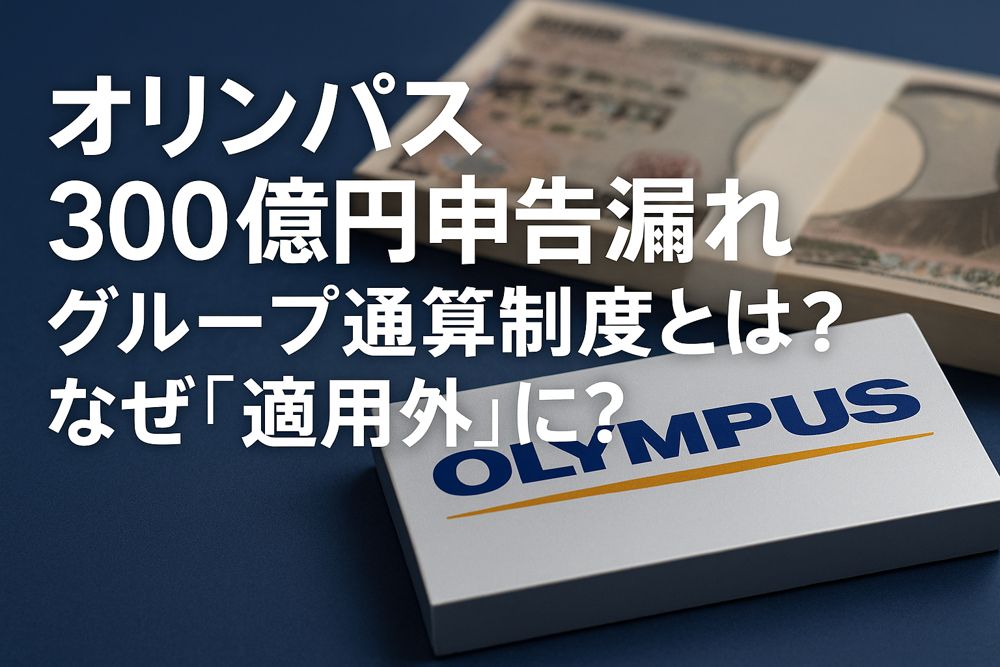
「オリンパスが申告漏れ」。一報を聞き、驚いた読者も多いだろう。なぜ、日本を代表する大企業が、これほど巨額の税金の申告を誤ったのか。東京国税局が指摘した申告漏れの金額は約300億円にのぼり、追徴税額は110億円超。意図的な脱税ではなく、企業の再編と税法の解釈をめぐる複雑な問題が背景にあった。この記事では、今回の申告漏れの核心に迫り、その背景にある「見解の相違」とは何だったのか、専門用語をかみ砕いて分かりやすく解説する。
大企業に突きつけられた税務調査のメス
2024年3月期までの2年間で、精密機器大手オリンパスが東京国税局の税務調査を受け、約300億円の申告漏れを指摘されたことが明らかになった。過少申告加算税を含む追徴税額は約110億円に上る。今回の問題は、単なる経理上のミスではない。事業再編に伴う子会社の税務処理を巡り、同社と税務当局との間で「見解の相違」が生じたことが発端となっている。
報道各社によると、今回の指摘は、オリンパスが分社化した子会社「エビデント」の税務申告を巡るものだった。オリンパスはグループ内の赤字と黒字を合算できる「グループ通算制度」を適用し、エビデント社の赤字をグループ全体の黒字と相殺して申告していた。しかし、東京国税局はこの制度の適用要件を満たしていないと判断し、申告漏れを指摘した。
オリンパスは取材に対し、「見解に相違はあったが、指摘を真摯に受け止め納税した」とコメント。既に追徴税額を納付済みだという。この一連の流れは、大企業であっても複雑な税法解釈をめぐり、税務当局との間で意見が食い違う可能性があることを示している。
キーワードは「グループ通算制度」と「エビデント」
今回の申告漏れを理解する上で、鍵となるのが「グループ通算制度」と、子会社の「エビデント」という2つのキーワードだ。
グループ通算制度とは?
グループ通算制度とは、2022年4月に導入された新しい税制度で、連結納税制度に代わるものだ。親会社と子会社の利益と損失を合算して税金を計算し、納税する仕組みとなっている。グループ全体で損益を通算できる点は以前の制度と同じだが、子会社が個別に税務申告を行うことが可能になったことで、親会社の事務負担が軽減された。この制度は、複数の事業を展開する大企業にとって、グループ全体の税負担を軽減する重要な仕組みだ。
しかし、この制度には厳格な適用要件が定められている。今回の申告漏れは、この要件を巡って、オリンパスと税務当局の間に解釈の隔たりがあったことから生じた。
エビデントとは?
もう一つのキーワードであるエビデントは、オリンパスが顕微鏡などの科学事業を担う子会社として、2022年に分社化して設立した企業だ。分社化後、2023年にはアメリカの投資ファンドに売却されている。実は、このエビデントの「分社化」と「売却」という経緯が、今回の税務上のトラブルに深く関わっている。
税務当局との「見解の相違」とは?
では、なぜ今回の申告は「グループ通算制度」の適用対象外と判断されたのか。
オリンパスは、経営再建を目的として、収益性の低い科学事業を分社化し、エビデントを設立した。このエビデントが、分社化後に計上した赤字を、グループ内の黒字と相殺する形で申告した。この申告は、グループ通算制度のルールに基づいたものだった。
しかし、東京国税局は、この一連の取引が制度の要件を満たしていないと判断したとみられている。一般的に、グループ通算制度の適用は、グループとして一体的に事業を継続することが前提とされている。報道記事によると、今回のケースでは、分社化からわずか1年足らずで米国の投資ファンドに売却されている。つまり、設立当初から売却を前提とした事業再編だったと判断された可能性が高い。
税務当局の立場からすれば、売却を目的として設立された企業は、長期的なグループの一員とは見なされず、制度の趣旨から外れると判断したのだろう。一方、オリンパス側は、あくまで経営再建の一環として、正当な手続きで事業再編を行ったと主張したとみられる。
この「事業の継続性」に対する解釈の違いが、両者の間に「見解の相違」を生み出した最大の原因だ。報道によると、オリンパスは「税務当局と議論を続けるなかで当社との見解の相違があった」とコメントしており、この複雑な解釈が、申告漏れにつながったことを示唆している。意図的な脱税ではなく、税法の解釈をめぐる専門家同士の意見の対立が、今回の事態を引き起こしたといえる。
今回の問題が社会に与える影響と教訓
今回のオリンパスの申告漏れは、すでに納税が完了しており、事態は収束に向かっている。しかし、この一件が社会に与える教訓は大きい。
まず、大企業であっても、税法の複雑な解釈を巡ってトラブルになる可能性があるということだ。税法は頻繁に改正され、企業の事業再編は多岐にわたる。企業の経営判断が、税務上のリスクを伴うことを今回の問題は改めて浮き彫りにした。今後、他の企業が同様の事業再編を行う際には、税務当局との見解の相違がないよう、より慎重な対応が求められるだろう。
また、我々一般消費者にとっても、今回の件は無関係ではない。大企業が納めるべき税金は、公共サービスの財源となる。その税額が企業の「見解の相違」によって減ってしまうことは、社会全体にとって見過ごせない問題だ。
今回の件は、意図的な脱税ではなく、あくまで制度の解釈を巡る問題であった。しかし、その根底には、経営再建という大義名分のもとに行われた事業再編と、それを厳しくチェックする税務当局の間の構造的な対立がある。この「見解の相違」は、今後も複雑化する企業の経済活動と税法の間で、繰り返し生じる可能性がある。今回のオリンパスの事例は、その警鐘を鳴らす出来事といえるだろう。