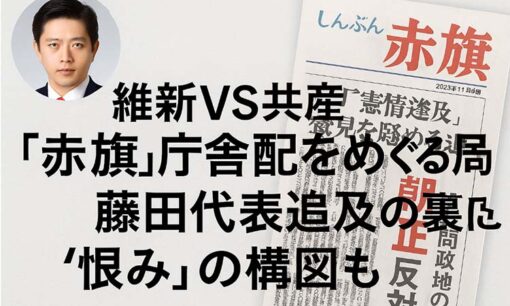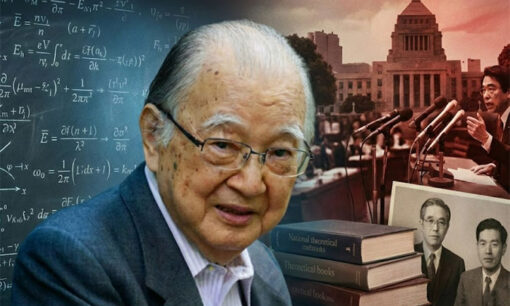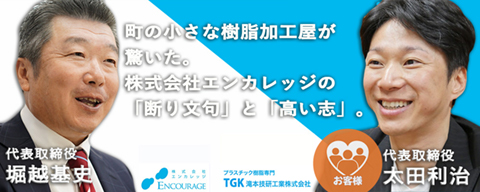先祖代々受け継がれてきた「お墓」の在り方が大きく揺らいでいる。継承者不在や管理負担を理由に「墓じまい」を選ぶ人が過去最多を更新する一方、墓を持たない「ゼロ葬」など新しい供養の形も広がっている。費用や手間、継承の要不要を比較すると、現代社会における「供養」の選択肢がいかに多様化しているかが浮かび上がる。
増え続ける「墓じまい」
近年、日本で「墓じまい」をする人が急増している。総務省や業界団体の調査によると、2013年度に約8万8000件だった件数は、2023年度には16万7000件と過去最多を記録し、10年でほぼ倍増した。背景には、少子高齢化や都市部への人口集中、遠方にある先祖の墓を維持できないといった事情がある。
「墓じまい」とは墓石を撤去し、更地にして墓地の使用権を返還する行為であり、遺骨は共同墓や納骨堂に改葬されることが多い。石材店によれば、費用は平均で1基あたり30万〜40万円前後、完了までに1〜2カ月を要するという。
「無縁墓」の増加と管理負担
墓じまい増加の背景には「無縁墓」の存在もある。無縁墓とは継承者がいなくなり、管理費も支払われず放置された墓を指す。総務省が2023年に発表した調査によれば、公営墓地や納骨堂を持つ市町村の約6割に無縁墓が存在し、管理費滞納額は4億円を超えた。寺や自治体にとっては撤去費用の負担が重く、墓地の荒廃も深刻な課題となっている。
墓を持たない「ゼロ葬」という選択
こうした状況のなか、そもそも墓を持たない「ゼロ葬」という選択肢も広がりつつある。ゼロ葬は、火葬後に遺骨を収骨せず、すべて火葬場に委ねる方法である。墓地の管理費や墓石の購入費用が不要となるため、身寄りのない人や、後に墓守を担う人がいないと分かっているケースで利用が増えている。死後事務支援協会によれば、通夜や告別式を省いた火葬のみのプランは11万5000円から契約可能だという。
供養の選択肢一覧(費用・管理・継承の要否)
| 名称 | 説明 | 費用の目安 | 管理の手間 | 継承の必要 |
|---|---|---|---|---|
| 墓じまい | 墓石を撤去し、更地にして返還。遺骨は納骨堂や共同墓に改葬 | 30万〜40万円前後/1基 | 解体・申請手続きあり(石材店が代行可) | 不要 |
| 共同墓・合祀墓 | 複数の遺骨を一緒に埋葬。寺や霊園が管理 | 10万〜30万円程度(永代供養料) | 以後の管理不要、寺が供養を継続 | 不要 |
| 納骨堂 | 屋内施設に骨壺を安置。ロッカー式や仏壇型など多様 | 契約時30万〜100万円前後+管理料 | 年間の管理料が必要 | 不要 |
| 樹木葬 | 墓石の代わりに樹木や花を墓標とする自然葬 | 10万〜50万円程度 | 基本的に施設側が維持管理 | 不要 |
| 海洋散骨 | 遺骨を粉末化して海へ撒く葬送法 | 10万〜30万円程度 | 管理不要、自然に還る | 不要 |
| ゼロ葬 | 火葬後に収骨せず、遺骨を火葬場に委ねて埋葬 | 火葬のみプラン11万5000円〜 | 完全に手間不要 | 不要 |
| 従来型墓 | 家単位で建墓し、代々受け継ぐ。供養や墓参が可能 | 建立100万〜数百万円+管理料 | 墓参・清掃・管理料支払いが必要 | 必要 |
変わりゆく「供養」の形
かつては一家の象徴とされた先祖代々の墓も、時代の変化とともにその役割を大きく変えつつある。家族の形が多様化し、親族が離れて暮らす現代において、墓の維持は大きな負担となりやすい。そのため、共同墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨、そしてゼロ葬など、「無理なく続けられる供養」の選択肢が広がっている。
石材業者は「お墓を建てることも、墓じまいをすることも、ご先祖を敬う思いは同じ」と語る。今後は、故人をどのように偲び、遺された人々がどのように関わるかという「供養の在り方」そのものが、個々の事情に応じて再定義されていくことになるだろう。