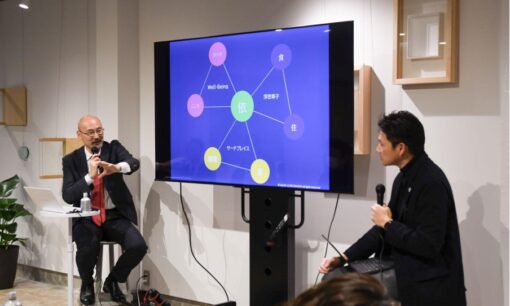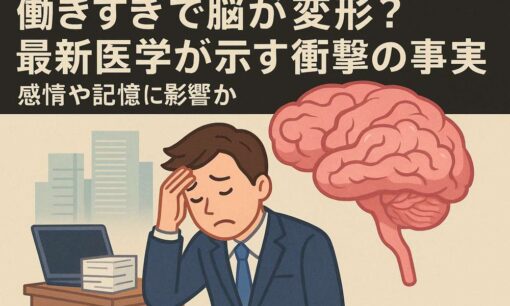13日未明、青森県弘前市上空で「流星クラスター」と呼ばれる極めて珍しい天文現象が発生した。活動中のペルセウス座流星群に由来し、約1秒間に19個の流れ星が一斉に出現。弘前市の「星と森のロマントピア天文台『銀河』」が撮影に成功し、その映像はSNSで急速に拡散されている。
世界で10例ほどしかない「流星クラスター」
国立天文台の渡部潤一上席教授によれば、流星クラスターは1997年のしし座流星群で初めて観測された。これまで世界で確認されたのはわずか10件ほど。
原因は完全には解明されていないが、流星体が宇宙空間を移動する過程で分裂し、その破片がほぼ同時に地球の大気に突入することで起きると考えられている。今回のようにペルセウス座流星群で観測されるのは、さらに珍しい事例だ。
弘前市の天文台が捉えた瞬間
現象が発生したのは13日午前0時57分ごろ。天文台敷地内の固定カメラが、北東から南西へ向けて1秒間に19個の流れ星が流れる様子を記録した。
天文解説員の山下諄(しゅん)さんは、記録映像をチェックしている際に、いつもと違う流れ星の動きに気づいたという。「これは流星クラスターだ」と直感し、その瞬間をSNSに投稿。すると、予想を上回る反響があり、14日午後7時の時点で閲覧数は302万件、「いいね」は2.1万件に達した。
ペルセウス座流星群とは
ペルセウス座流星群は、スイフト・タットル彗星がまき散らしたちりの帯を地球が横切ることで発生する。毎年8月12日前後に活動のピークを迎える「三大流星群」の一つで、条件が良ければ1時間に30〜40個の流星が見られる。
今年は月明かりの影響で観測条件はやや不利だったが、一部地域では明るく長い尾を引く流星が確認された。
流星クラスター観測のポイント
珍しい現象だが、条件を整えれば流星群そのものは多くの地域で観測できる。
- 場所選び:街明かりが少なく、空が広く見渡せる場所が理想。
- 時間帯:深夜から明け方にかけてがベスト。月が出ていない時間を狙う。
- 観測方法:双眼鏡や望遠鏡は不要。肉眼で広い範囲を眺める方が流星を捉えやすい。
- 服装と準備:夜間は夏でも冷えるため、上着やレジャーシートを用意すると快適。
今月24日までチャンス
国立天文台は、ペルセウス座流星群が8月24日ごろまで観測できる可能性があると発表している。条件が整えば、数分に1個程度の流星に出会えることもある。
今回のような「流星クラスター」は極めてまれだが、夜空を見上げれば思わぬ天体ショーに出会えるかもしれない。